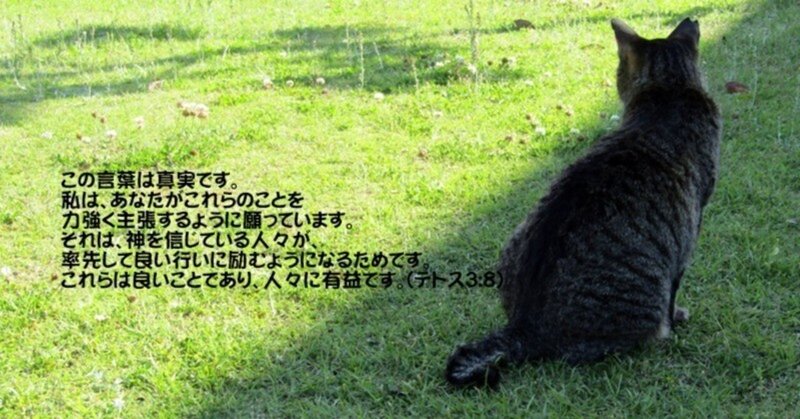
真実な言葉の裏
テトス3:1-11
「この言葉は真実です」(8)が強く響きます。この言葉は信じられる、と言い切っています。清々しいものがあります。テトスへの手紙が、信仰者へ、特に伝道者へ向けてのマニュアルのような役割を果たすとすれば、伝道をするべく立てられた専門家はもちろんのこと、信じる者すべてに、このメッセージが刻み込まれていなければなりません。
「これらのことを力強く主張するように願っています」とあるからには、「これらのこと」がここに明示されているはずです。権力者に服すべし、というところからこの段落は始まりますが、その話題は、寛容で優しく接すべきこと、それから自らが、かつては道に迷い、平和ではなかったことへ、と話が進んできたのでした。
やはり己れの常態を正しく把握することが、救いへの第一歩であることがよく分かります。かつての自分がどうであったか、これを蔑ろにしての赦しや救いはありません。但し、これが真実の正体ではなく、救い主なる神の愛が何であるか、を語るところにこそ、真実があるわけです。行いによらず、神の憐れみによって、新しい命に生かされるのです。
しかもそれは、聖霊によるのです。これがきっぱりと書かれています。神が聖霊を、イエス・キリストを通して私たちに注いでくださったことで、私たちは義とされました。イエス・キリストの恵みの故に、この救いが与えられました。そして、永遠の命を受け継ぐ者とされました。このことを告げる神の言葉こそが、真実であったのです。
さあ、これを力強く主張するのです。そうして神を信じる者は、「よい」行いに導かれることになります。表記上の問題ですが「善い行い」(1)と「良い行い」(8)との違いが、私にはよく分かりません。が、「よい」ことよりもむしろ、「愚かな議論、系図、争い、律法についての論争」というほうが具体的で、当時教会の問題だったのでは、と思われます。
「分裂を引き起こす人」は、戒めた上で除名処分だ、とまで厳しく書かれています。きっと厄介だったことでしょう。それはいまの教会でも全く同じです。それは「心がねじ曲がっており、自ら悪いと知りながら罪を犯している」者だといいます。非常に具体的に言及されていることのほうが、読者の心に残ってしまうような気がしてなりません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
