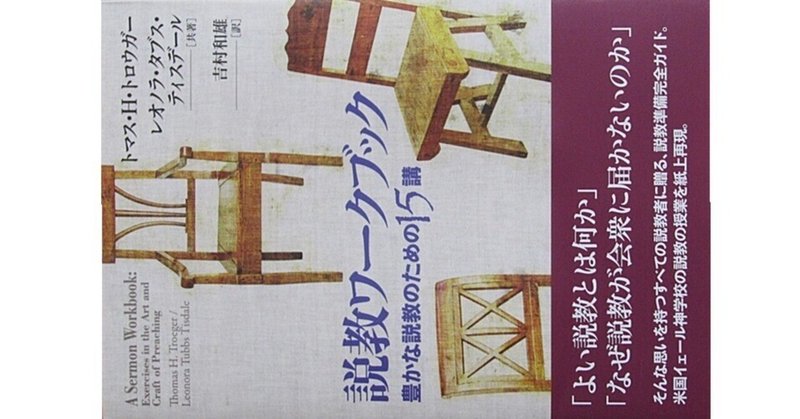
『説教ワークブック:豊かな説教のための15講』
(トマス・H・トロウガー;レオノラ・タブス・ティスデール・吉村和雄訳・日本キリスト教団出版局)
私にとって3000円+税とは高価な本だ。だが、気になっていた。キリスト教の礼拝説教というものに執着のある私だから、テーマが気になる、というのも事実だ。だが、この共著の一人が、トロウガーであるという点が、どうしても見逃せなかった。『豊かな説教へ 想像力の働き』を読んだからだ。日本の説教塾でも、説教と想像力ということの大切さが強く叫ばれる。トロウガーを知ったのも、その関係であったかもしれないと思う。
本書は、イェール神学大学の学生へのレッスンという場面を演出している。実際教科書としても使われるものである。それで、実践的な授業の形態も各章の終わりに掲載されている。これをそのまま、神学校で用いることができるということである。
目次で断り書きがあるように、本書は、原著の半分である。ここにあるのは第1部だけであり、第2部は一切翻訳書にはない。それは、「英語で説教を書く」ことがテーマであるらしいため、収めなかった、というのである。訳しにくいのかもしれないが、私は見たいと思った。これはぜひ検討して戴きたい。
冒頭から、実は「想像力」ということが表に出てくる。説教が、イマジネーションを持ってものごとを考えさせてくれるということを明らかにしている。この方針がもし気に入らない人は、最初からこの本には関わらなくてよい、ということかもしれない。しかしそういう人も、本書を辿れば、想像力の必要性や魅力を、きっと感じることになると私は期待したい。
そこでは、本書が「ワークブック」であると宣言されている。そうだ。だから本書のタイトルに「ワークブック」がまず掲げられているのだ。しかし、それにしては理論が殆どの頁を占めている。読み物としても申し分のない内容である。
こうした手法を批判する人がいるかもしれない。必要なのは信仰だ、テクニックではない、などと。そう、本書はこのような信仰をもつべきだ、というような信仰論に沿って書かれてはいない。信仰を育もうと目論んで本書を開く人はいないだろうとは思うが、知らず識らずのうちに、そうしたものを求めてこうした本に触れる人もいるだろう。だから、どんな信仰を聖書に対してもとうか、などという動機が、いかにものテクニックに辟易するのだ。
だが、私は思う。信仰というものは、前提されているのだ、と。つまり、ここに書かれてあることは、聖書に対する一定の信仰がある人には、ずばずばと斬り込んでくる説明となっており、逆に、神に出会ったことがなく信仰が実はないという人間には、さっぱり書いてあることが分からないのである。
なにげなく書いてあることに、ハッとさせられることもある。私がふだん考え、あるいは批判しているようなことが明確に書かれていて、驚くこともある。中でも忘れられないのが、「この話は前に全部聞いた」症候群、という言葉(p166)だった。もう噴き出してしまった。会衆が、説教に、この話は知っている、と心に蓋をしてしまう性質である。いくら説教者が新たな視点や深い黙想への誘いをそこに含めていても、「知ってる、知ってる」で終わってしまう、というものだ。しかしこれを打破するのが、真の説教となるであろう。
学校でも、生徒がまたあの話か、と退屈するような授業は、それをする先生のほうに工夫がない。生徒の目を生き生きとこちらへ向けるためのテクニックは、ただノウハウを学んでもできない。私は分かる。それで飯を食わせてもらっている身だ。熱意が必要だ。そして、何よりも生徒との関係を築くということが大切なのだ。その上で初めて、テクニックを学んで役立てることができるということになる。
説教もパラレルに考えられると思う。もちろん、説教は神の言葉を語る。その信仰が根柢にあって成り立つ場であるから、学校の授業とは根本的に違う。だから、魂の配慮が必要になる。ただ、本書はそこを扱い育もうとするものではない。悪いが、信仰のない人がいくら表面的に本書を取り入れても、何の役にも立たないであろう。ベタな説教しか本当にできない、又聞きやお勉強の作文を披露するだけの人物には、無縁の書である。その映画を観て感動したことがない人が、映画の批評だけを読んで、映画の魅力を語ることができないのと同様である。
アメリカ的な、しかも現代的な説教論であるかもしれない。「説教塾」が、しばしばドイツの説教をモデルに考えていたことも、私は大好きなのであるが、その説教塾でも、近年はアメリカ的なものを非常に大きなものとして取り入れているように見受けられる。事実、説教塾の読書会においては、これから盛んに本書がテキストとして取り上げられる予定である。
日本の教会は、アメリカから半世紀ばかり遅れている、などと言われることもあるが、ここへきてようやく、半世紀前のそこになじんできた教会も現れ始めた。それ以前の教会もまだ多々ある。また、アメリカが必ずしもよいわけではないから、それを真似するのがよい、などとも私は決して考えない。しかし、「なぜ説教が会衆に届かないのか」という、帯に書かれているセンセーショナルな文句には、私たちは素直に頭を垂れてよいと思う。
やはり、明治期の豪傑な日本の説教者のスタイルからは、変化している。それは、聖書や信仰が変化したという意味ではない。まして、イエス・キリストが変化したのでもない。ただ、人間社会と人間精神が、変化しているのだ。それを弁えつつ、次の時代を生み出すための、新たな道を見出すことが求められる。そのためには、根柢に信仰が置かれなければならない。そして、それに基づいて生まれる説教、つまり神の言葉の取り次ぎが、聴く者を生かさなければならない。説教が、形だけのお勤めではなく、人を生かす場であることを願うものである。それが、神に栄光を帰すことであり、神と人とのつながりが結ばれることであると信じるからである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
