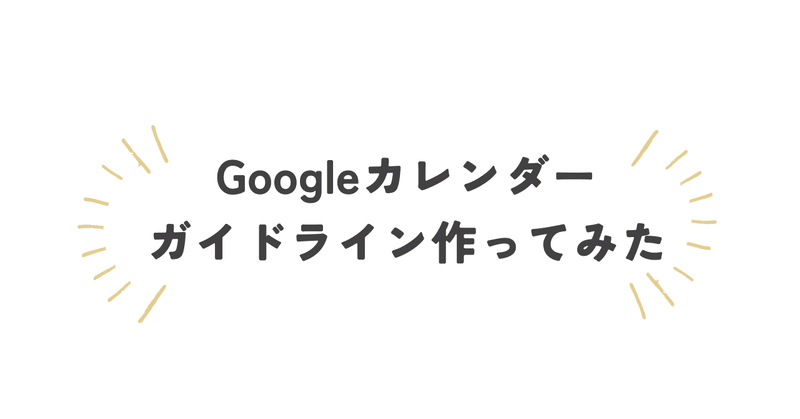
Googleカレンダーガイドライン作成と通じて感じたこと
皆さんの会社にはGoogleカレンダーなどの媒体に限らず、社員のスケジュール登録のガイドラインってありますか?
弊社は今まで存在せず、フレックス制度にともなって作成してみました。
そこで感じたことをまとめてみます。
ガイドラインを作ろうと思ったきっかけ
社員のスケジュール登録や確認をGoogleカレンダーを使っていますが、特にガイドラインは今まで存在しておりませんでした。
私は自分のスケジュールは漏れなく登録して、誰かに話しかけたりするときも今空いてるかな?とスケジュールを確認するようにしています。
そのときは、しっかり登録されている人・いない人といるなあとも感じつつ、そのままにしちゃっていました。
そんな折、会社でフレックス制度が導入されることになりました。
現在も、物理出勤やリモートワークの社員が入り混じっており、その人のデスクに行けば状況が把握できる!ということは減ってきました。
また、実際にとある社員が「仮でもスケジュール登録してもらわないと予定の調整が出来ないので困る」という発言をSlackで行っていたのも目にしていたんです。
フレックス制度が導入され、時間も場所も自由になると、さらにあの人は…?と確認するのが困難になってくるのが予想されます。
少しでもスムーズにコミュニケーションができるようにガイドラインをつくろう!と決心しました。
草案作成~バックオフィスに確認依頼
ガイドラインの草案を作る
ガイドラインを作成…といっても、社員のスケジュール登録に関する取り決めをした経験がないので、インターネットで先駆者の皆様のお知恵を借りようと調べました。
参考にさせて頂いたのが以下の記事です!
この場を借りて御礼申し上げます。
Googleカレンダーで予定が空いていれば、Slackなどで確認しなくても登録OK!
スケジュール調整中の仮スケジュールも登録する(その際はタイトルに仮をつける)
スケジュールの種類を弊社に合わせて設定し、スケジュールタイトルの頭につける(【外出】~【MTG】~)
通常と違う場所で働いている場合は場所を記載(リモートワークなのか?サテライトオフィスなのか?)
有給やフレックス制度に伴う不在の場合は、「不在」でスケジュール登録をする(スケジュール招待されても自動的に辞退してくれるため)
スケジュール招待されたら、出席有無のボタンを押すこと
と、参考にさせて頂きながら、自分のカレンダーでスケジュール登録テストして見栄えをチェックしながら上記をとりまとめました。
全社に発信する前に上司に確認してもらい、その後バックオフィスに確認をお願いしました。
バックオフィスに確認してもらいました
バックオフィスに確認してもらった理由は、電話対応をしてもらっているからです。(ありがとうございます!)
電話転送の際に、今その人に繋いでいいかどうかカレンダーで予定を確認しているそうです。
その作業の中で、スケジュール登録されている人いない人の差については課題に感じていたそうです。
バックオフィスの社員から、以下の課題を新しくもらいました。
会議室もカレンダーで予約できるようになっているが、予約していないのに使っている社員が見られる
予約時間を過ぎても使っている社員がいて、スムーズな入れ替わりが出来ていない
出張や外出のスケジュールに移動時間も含まれているのかわからない
確かに、私も予約していた会議室を別の人に断りもなく使われていたことがあり、会議室を変更した経験が何度かあります(汗)
ガイドラインを通じて、スケジュール登録だけではなく、会議室予約に対しても課題があることを知ってもらえたらと思い、以下の文章を追加しました。
会議室を使用する場合は、前後のスケジュールに配慮する
使用を延長する場合は必ず登録されているスケジュール変更を行う
外出や出張に伴う移動時間もスケジュール登録
追加したガイドラインの内容で上司からもバックオフィスからもOKが出たのでついに全社発信。
全社発信ですが、最初はSlackで投稿するだけにしようと思いましたが、結局のところ、30分のウェビナーを行いました。
バックオフィスの社員にガイドラインを説明している際、スケジュール登録の操作の中で「不在」登録の方法が知らなかったというのがわかったからです。
社内ウェビナーで全社発信
以下の内容で30分の社内ウェビナーを行いました。
ガイドラインの目的
ガイドラインの内容
操作説明
質疑応答
ガイドラインの内容や操作説明については反応も良好で、大きな反発はありませんでした。
質疑応答では、「社外からスケジュール招待されたタイトルも直さないといけないの?」と質問があがり、それは直さなくてOKですと返しました。
自分もSalesforceさんのセミナー登録して自動的に登録されたスケジュールタイトルはそのままですし、あくまでも社内での登録時にガイドラインに沿うようにお願いします!としました。
全社発信して1か月ほど経過した反応
バックオフィスの社員にその後の様子をお伺いしたところ、大きな問題は発生していないということで安心しました。
その中で新たな課題が出てきました。
「書類確認」など作業をスケジュール登録している人がいるが、電話転送していいか悩む
確かに!と思いました。自分は作業はスケジュールではなく、タスクとして登録しているので盲点でした。
それを上司とどうするか相談したのですが、上司からGoogleカレンダーガイドラインを重く感じている人がいるとお話をもらいました。
会議や移動が多い社員であれば、Googleカレンダーはもちろんのこと必須です。
自分は会議の割合はそこそこあり、リモートワークするときや有給のときには必ず登録するようにしています。
しかしながら、会議がほとんどない、移動もしない、有給とか不在のときも普段登録していない社員から見たら、ガイドラインはただただ登録の面倒が増えるだけです。
正直、この話を聞くと、じゃあ自分のスケジュールどうやって管理しているんだろうとか、せめて不在のときは登録しようよって思うんですけど、登録しなくても本人は困ってはないんですよね。
真っ白なそのカレンダーを見て連絡していいものか困っている人がたとえいたとしても、本人は困ってない。
会議室を予約していないのに使用する、後の予定があるのに会議室を使い続けるというのも同じ心理なのかな?と思いました。
前回、Slackのガイドラインを作成した話を公開しましたが、ありがたいことに良い変化があったりました。
しかしながら、Googleカレンダーに関しては、Slackほど社員全員が業務で絶対必須!ではないんですよね。
なので、ガイドラインにはこれ以上内容は追加しないようにしました。
バックオフィスには「会議でも会議以外の作業予定のスケジュールでも、何かしら登録されていたら電話転送はしない」ようにバックオフィス内で認識してもらった方がストレスがないと思いますと検討をお願いしました。
まとめ
自分はGoogleカレンダーがないと仕事するのは難しいです。
あの人に連絡してもいいかな?あの人会議に招待しても大丈夫かな?って判断に迷うストレスを考えると、カレンダーでぱっと確認出来た方がいいと思っています。
でも、自分から会議招待する機会が少ないなど、カレンダーの利用度が低い社員にとってこの考えは重い。
ITリテラシーや利用度の差はどうしてもあるので、押し付けすぎはよくないなと改めて感じました。
しかしながら、会社としてスケジュール確認をGoogleカレンダーで行っているよ、困っている人もいるよ、なるべくこういう風に登録してね、と言語化出来たのはよかったのかなとは思います。
自由に個人任せにしすぎて統率がとれないのも困りますし…会社として多少のこうしましょうは必要だとは思うんです。
特に新しく入社された方に対しては、会社でスケジュールはこうしてますってお伝えした方が困惑しないと思うんですよね。
どこまでが押し付けになってどこまでが必要な道なのか…バランスが難しいですね。
バックオフィスも普段の電話転送の際やフレックス制度に向けて私と同じような課題は持っておりますし、今後様子を見ながら何が会社に合っているのか?定期的な見直しをしていこうと思います。
カレンダーガイドラインってどうなんだろう?って悩んでいる方などに参考になりましたら幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
