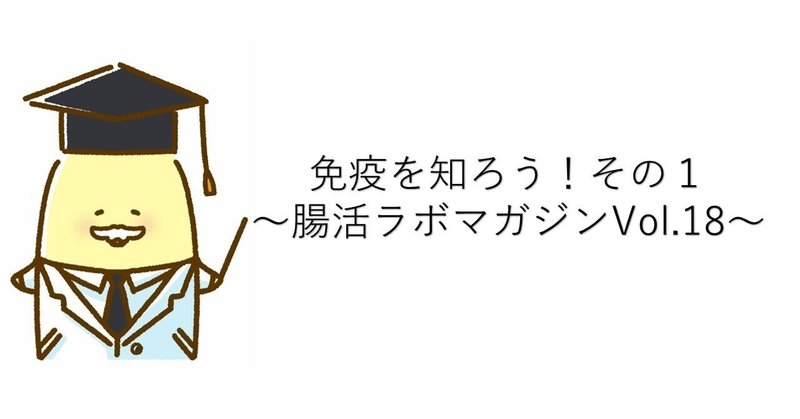
免疫を知ろう!その1~腸活ラボマガジンVol.18~
はじめに
こんにちは、やまだです。これまでに腸活ラボマガジンやXでは、腸内細菌叢と免疫についてお話ししてきましたが、そもそも免疫についてあまり深く解説したことがなかったと気づきました。多くの人にとっては、高校の生物で基礎の基礎を少し習うくらいだと思います。そのあと、実生活で触れるとすれば、健康診断の血液検査くらいでしょうか?
今回から自分たちの体を守ってくれている免疫についてわかりやすく、なおかつ面白く解説していければと思います。
免疫の登場人物=免疫細胞たち
そもそも免疫とは、漢字の通り、一度感染症にかかると二度目はかからないという意味でしたが、最近では、病原体から体を守るための仕組みという意味に捉えられるようになりました。
免疫は、ウイルスや細菌などを原因とする感染症から体を守るだけでなく、自己免疫疾患やアレルギー、肥満など様々な症状に関与しています。そして、それらを理解することで生活習慣病などを予防し、健康寿命を延ばすことができるはずです。
血液の成分
では、まず免疫細胞がある血液についてみていきましょう。
そもそも、血液は、血管を通じて体中を循環し、体内の全器官に分配され、栄養や酸素・二酸化炭素・老廃物の運搬、体温や体液量の調節、免疫など様々な働きがあります。
血液は、液体の血しょうと有形成分の血球があります。
表1 血液の成分

血しょうは、6割ほどを占めていて、血球は残りの4割程度を占めています。血球の血液中の割合をヘマトクリット値(Ht値)といいます。男性は、40~50%、女性で35~45%です。
血球は、赤血球、白血球、血小板の3種類があります。そもそも血球は、骨髄にある造血幹細胞から作られます。同じ細胞に由来しますが、血球ごとに分化するときに作用するホルモンが異なります。それぞれの役割を見ていきます。

赤血球
赤血球の一番の役割は、酸素の運搬です。赤血球の中のヘモグロビンが鉄を介して酸素と結びつくことで運搬ができます。
赤血球は、核のない細胞で中央がくぼんでいますが、これによって表面積が大きくなり、酸素のやりとりがしやすく、また変形できるので小さい血管も通ることができます。
末梢組織で酸素が少なくなると、腎臓でエリスロポエチンというホルモンが作られ、骨髄の造血幹細胞から赤芽球が作られます。赤芽球が成熟すると核が脱核して、赤血球になります。核がないので分裂できず、約120日経つと脾臓や肝臓で破壊されて、寿命を終えます。赤血球は、1日に2000億個が生まれ、同数が破壊されています。そのため、常に造血幹細胞では赤血球を作るために分裂が続きます。
ヘモグロビンは、酸素の運搬に関わるタンパク質で、鉄を含むヘムとグロビンタンパク質からなります。ヘムが赤いので赤く見えます。ヘモグロビン1つにヘムが4つ入っています。

赤血球が脾臓のマクロファージという細胞によって壊されるとヘモグロビンが外に出ます。このうち、グロビンは、アミノ酸に分解されて再利用されます。一方、ヘムは、そこから鉄とビリベルジンという緑色の色素になり、そこからオレンジ色のビリルビンに分解されます。鉄は、再びヘモグロビンにリサイクルされます。
一方でビリルビンは、血中ではアルブミンというタンパク質と結合して水溶性になってから肝臓に運ばれます。この状態を間接ビリルビンといいます。肝臓に到達した間接ビリルビンは、肝細胞に取り込まれてアルブミンを放出して、グルクロン酸という物質と結合します。これをグルクロン酸抱合といいます。この状態を直接ビリルビンといいます。これは、胆管を通って小腸に排出されます。
一部は小腸で再吸収され、肝臓に戻り、腎臓に入ってウロビリノーゲンとなり尿中に排泄されます。尿中の黄色の色素としてウロビリンというものがありますが、125年以上ウロビリンの産生に関わる酵素がわかっていませんでしたが、2024年に報告された研究で、腸内細菌叢由来のビリルビン還元酵素(BilR)を同定し、これがビリルビンをウロビリノーゲンに還元し、これが自然分解されることで黄色色素ウロビリンができることが明らかになりました(ref1)。
ほとんどの吸収されなかったビリルビンは、腸内細菌によってステルコビリノーゲンとなり、そこから酸化されて、ステルコビリンとなり、糞便中に排泄されます。便の色が茶色なのは、このステルコビリンによるものです。

血小板
血小板の役割は、止血です。血小板は傷ができるとそこに集まり、止血作用としてかさぶたを作りますが、同時に傷の治りを早める成分である成長因子も含んでいます。これを抽出して、損傷した組織などに注射することで回復させる治療法(PRP(Platelet rich plasma)療法といいます)も存在し、大谷翔平選手をはじめとしたスポーツ選手などに用いられています。
白血球
では、免疫のかなめである白血球についてみていきましょう。
表1 白血球の種類と役割

いただいたサポートは、腸活ラボの運営や調査のために大切に使わせていただきます。
