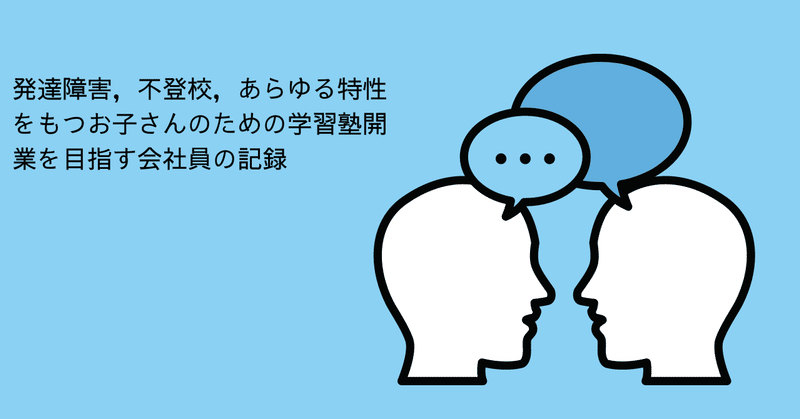
論文紹介:社会コミュニケーションスキルと運動模倣の関係
こんにちは,umenoです.
どんなことにも根拠,裏付けは必要ですよね.科学的な根拠,つまり再現性を担保するためにも,科学論文を読んでいくことは必要です.今回は社会コミュニケーションスキルと運動模倣の因果関係について調査した論文がありましたので,紹介したいと思います.幼児期のお子さんを持つ親御さん,教育や療育関係者の皆さまにとって,少しでも参考になれば幸いです.
1.Body movement imitation and early language as predictors of later social communication and language outcomes: A longitudinal study
今回はこの研究報告について取り上げます.まずは結論から.
Theoretically, results highlight the need to account for the heterogeneity of different language and communication trajectories in children with early language delay and point to the importance of sociocognitive difficulties observed in some of these children. Clinically, this study demonstrated that body movement imitation measures have the potential to improve the identification of pre-schoolers who are at risk of later social communication and language problems.
簡単に解釈すると,幼児期の運動模倣する力が,後の社会コミュニケーションスキルなどに影響を与えるといった内容になります.
②方法を確認
・縦断的研究
・対象は2歳の時点でことばの遅れをみとめ,4歳まで追跡できた29名
・母国語はドイツ語
・ソーシャルスキルの尺度はドイツ語で標準化された親が記入するもの
・ロジスティック回帰分析で結果を解析
③研究の限界を確認
・身体模倣以外で追跡をしていない(他の因子もあるかも)
・サンプルサイズが小さい
④論文を読んだ上で現場で感じること
運動模倣は「準備体操」として,よく行います.今回の論文は縦断的な予測因子としてでしたが,横断的にも関係はあるかなと思いました.
「やりとり」が苦手なお子さんは,模倣が苦手で,苦手な背景が不器用ではなく,「よく見ていない」「みようとしていない」「相手に興味がない」といった背景が多い印象があります.
なので,「相手をよくみて,マネして」という体操の練習であっても,「相手をよくみて,反応をみて,やりとりをする」といった社会コミュニケーション力に繋がるというのは現場感としても納得がいく印象があります.
以上です.気になる方は是非原本を読んでみてください.
今後もこういった関係の論文を少しずつ紹介していきたいと思います.
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
