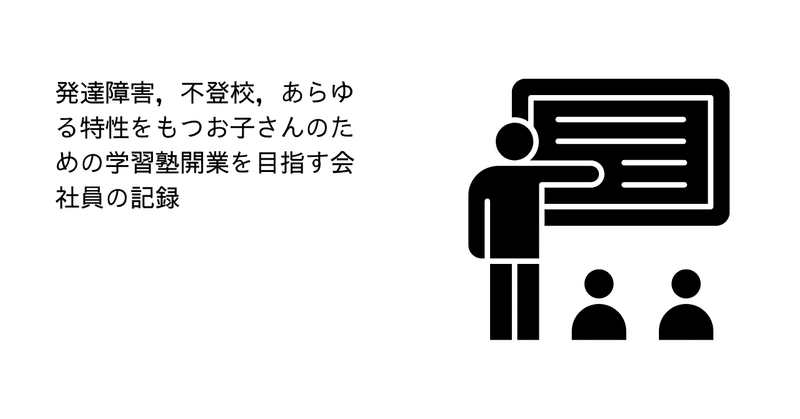
教育の根拠を考える【EEF編】
こんにちは,umenoです.
イギリスのThe Education Endowment Foundation(以下EEF)はご存じでしょうか.教育分野において不利な環境にある子どもたちの学力向上を目的として,2011年に設立された公益団体です.スタッフは統計学,事業評価,教育の専門家から構成されており,研究に基づくエビデンスを,実務者や政治家の施策導入判断や教員の教育実践を助けるためのThe Teaching and Learning Toolkit(ツール・キット)として翻訳・情報発信しています.
以下にEEFに関する情報が載っている文部科学省の「教育投資の効果や必要性を社会に示すための方策について」のリンクを貼っておきます.
リンク先の資料にもある通り,「教育政策の評価に関する質的・量的な研究は不十分であり、指標や測定方法の在り方に関する研究も 十分なされていない」とあり,教育者の感覚的なところに頼っていることが多いというのが現状だと思われます.そして,エビデンスという言葉があまり一般的ではない分野なのかもしれません.その点で,悩まれている先生方も多いのではないかと思います.
しかし,EEFでは研究結果から導かれたエビデンスに基づく教育を推奨しています.その上,誰でも見る事のできる状態になっています.私も参考にさせてもらっていることが多いので,今回はEEFを使ってみた感想も含め,簡単にまとめてみたいと思います.
1) 教育と学習のツールキット
EEFのツールキットのページを開くと,導入コスト,根拠の強さ,影響を与える長さといった項目で,それぞれの教育手法がどの項目でどの程度なのかということがわかるようになっています.実際ページを開いてみて触ってみる方が早いと思います.以下にリンクを貼っておきます.
2) 導入コストが低く,根拠がしっかりしているものを探す
やはり導入コストが低く,根拠がしっかりしているものが直ぐに導入しやすいと考えます.検索してみると,文字を教えること,フィードバックをすること,小グループで学習することメタ認知と自己調整をすること,といったように直ぐに出てきます.ページの中でそれぞれの詳細を確認することが出来ます.
3) 感覚的に良いだけではなく,科学的に良いも一緒に考える
導入の部分でも書きましたが,私自身現場で働いていると教育は感覚的になりやすい分野でもあると思います.もちろん経験,感覚も大切ですが,科学的な部分を取り入れていくことも必要だと思います.科学的であることは,再現性があるということであり,教育にムラが出来にくくなると考えられるからです.
4) まとめ
EEFの取り組みは不利な環境にある子どもたちの学力の向上を目指しているものです.我々も教育格差が起きないよう,積極的に参考にしていきたいですね.
本日も最後まで読んでいただき,ありがとうございました.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
