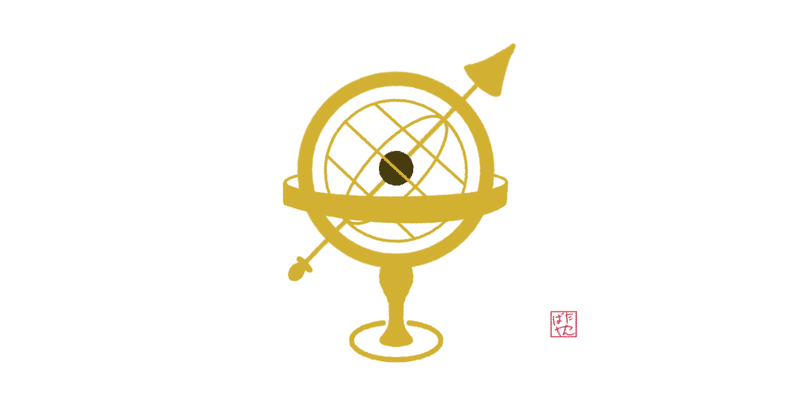
コペルニクス的転回のススメ 篇
ぼくが学生時代を過ごしていた25年前と比べて、と書くと、嗚呼、オレも歳くったもんだなぁと、それはソレで感慨深くなって黄昏れてくるわけですけれども、社会においては、まだまだヒヨッ子なのであります。
いや、ホントに、そんなもんですよ、皆さん。オジさんだとか言っちゃ駄目ですよ。まだピッチピチのプリップリです。
きっと、50歳になっても、そういう感覚というのは、特に前を向いて生きている人の中には残り続けていて、我が敬愛する松下 幸之助翁なんかも、「青春とは心の若さである」なんて言っちゃうわけです。元ネタは、サミュエル・ウルマンですけれども。
「青春」
青春とは人生のある時期ではなく
心の持ち方をいう。
バラの面差し、くれないの唇、しなやかな手足ではなく
たくましい意思、ゆたかな想像力、もえる情熱をさす。
青春とは人生の深い泉の新鮮さをいう。
青春とは臆病さを退ける勇気
やすきにつく気持ちを振り捨てる冒険心を意味する。
ときには、20歳の青年よりも60歳の人に青春がある。
年を重ねただけで人は老いない。
理想を失うとき はじめて老いる。
歳月は皮膚にしわを増すが、情熱を失えば心はしぼむ。
苦悩、恐怖、失望により気力は地にはい精神は芥(あくた)になる。
60歳であろうと16歳であろうと人の胸には
驚異にひかれる心、おさな児のような未知への探求心
人生への興味の歓喜がある。
君にも我にも見えざる駅逓が心にある。
人から神から美、希望、よろこび、勇気、力の
霊感を受ける限り君は若い。
霊感が絶え、精神が皮肉の雪におおわれ
悲嘆の氷にとざされるとき
20歳だろうと人は老いる。
頭を高く上げ希望の波をとらえるかぎり
80歳であろうと人は青春の中にいる。
と、話が逸れていったわけですけれども、何の話だっけ。そうそう、ぼくの学生時代のときと比べて、学生さんの「キャリア意識」というものが、すこぶる高ぶりを見せていて、ここに極まれりな様相を呈しているのであります。学生さんに留まらず、若い社会人の皆さん、それぞれ自社における立ち位置や転職も含めて、キャリアに縁のないぼくなんかにしてみたら、世の中、キャリアキャリアで、もうゲシュタルト崩壊を起こしそうになるわけです。
ぼくは福岡市で、フッと吹けば飛ぶようなカフェ・バーを経営しているわけですが、そこにもちょうど啓蟄を迎える頃になると、地下からうねりだしてくる生き物のように力強く、就職活動なんかを始めた学生さんが訪ねて来るわけです。そして、案の定、ぼくの就活、どうしたら良いでしょうか、みたいな質問をぶつけて来る。
ぼくは心の底では、自分の始末は自分で付けろよ、と感じているのですが、実際には、フルパワーで対応します。だって、コーヒー代の五百円を支払っていただけますから。無下にはできない。せこいですが。
そこで話を聞いてみると、やはり皆さん自分のキャリアをどう形成していくか気にしていらっしゃるのですね。一つだけ言っておくと、ぼく自身は個人のキャリア志向について、否定的な見方はしていません。だって、人生はフィクションですから。人生を終えて葬式をやるときには、棺桶に
「この物語はフィクションです」
とか書いてあったとしたら、誰が、それを否定し得ようか。ここまで来ると、デカルトくらいまで遡って壮絶な議論ができそうですが、そこはまた別稿にて。
まぁ要は、人生自体がフィクションなのですから、キャリアというフィクションを自分という役者が作り、演じていくというのは、すごく合理的なわけです。
ただ残念ながら、キャリアという言葉の地位向上に伴って、学生諸君の多くは、どうやらキャリアはフィクションだぞ、何となく自分で作れそうだぞ、と気付き始めているのとは裏腹に、自分の人生に対しては、何といいますか、全く設計する意志を感じられません。
どういうことかと言いますと、たとえば5、6歳くらいの女の子に将来について質問したとします。
「お花屋さんになりたい、ケーキ屋さんになりたい」
と答える、これはキャリア形成。
「お嫁さんになりたい、お母さんになりたい」
と云う、これは人生設計。
どちらも間違いじゃないんです。
けれど、何故だか成長して大人になっていく過程の中で、後者の人生設計の方だけが捨象されて(おそらく現行の教育システムがそうさせるのでしょう)、キャリアばかりを気にする人が増えてくるようなのだます。
結果として、キャリア形成は上手くいっても、何だか分かんないけどミスマッチが起きて、また新しいキャリアについて考えるんだけれども、解決する糸口が見えない、という人が、最近、特に多い気がしています。
だから、ウォール街でバリバリ稼いでるアメリカ人みたいに、40歳まで働いてあとはリタイアだぜ、みたいな人生がしっくり来ない。これは経済構造的に無理な問題でもあるんですが、思想的にもきっとそうなのだと思います。
これは、生き方とかキャリアに関わらず、この国自体が、もっと言えば世界全体が必要としていることなのかもしれませんが、いま必要なのは、コペルニクス的転回なのであります。
コペルニクス。本名は、ニコラウス・コペルニク。15世紀から16世紀にかけて活躍したポーランドの天文学者です。なんと、彼はローマカトリック教会の聖職者でありながら、ギリシア思想の影響を受け、肉眼による天体観測に基づいて地動説を提唱しました。
ちなみに、彼が生きた時代は「暗黒の中世」と言われるヨーロッパであり、キリスト教は絶対であり地球は神の造りたまひしモノです。早い話がローマ教皇が「俺、絶対的権威なんだもんね」とのさばっており、「地球はイエス・キリストの生まれたところなんだから、太陽が地球の周りを回れよオラッ」的な天動説が主流の時代であります。
こういう時代にあって、
「いやいや、実は地球が回っちゃってるのよね」
と声を上げる気持ち良さ。これはもう、絶世の美女に向かって「口がクサイ」と指摘するのに等しい快感なのです。この快感を哲学に引用したのがドイツの哲学者カントです。
カントは、主観は対象に従いそれを写すとする従来の認識論を逆転させ、対象が主観に従い、主観の先天的な形式によって構成されるとして、認識対象は現象にすぎず、物自体ではないことを主張しました。
要するに、「リンゴがそこにあるからリンゴが見える」という従来の学説を覆し、「リンゴを見ようと思うからリンゴが見えるんだもんね」と主張したのです。この認識対象の逆転についての学説は「カントのコペルニクス的転回」と呼ばれます。
学生時代のぼくは、
「何も食ってないから腹が減っているのではなく、腹が減っていると思うから何か食いたいのだッ!」
と言い聞かせたりして金が無い時間を過ごしたりしていました。要はこのカントのコペルニクス的転回を最大限に利用していたのである。この考えの応用がもっとも効果を発揮したのは大学の期末試験のときでした。実は大学の教授の中には
「出席してないと単位あげないモンネ」
という頑固なスタンスを維持している者が非常に多いのです。しかも基本的に面白くない講義に限ってそういう教授である比率は高いのであります。
「面白く無い授業には出席せんで単位とっちゃるもんね」
という信念の持ち主であったぼくは、往々にしてこういった教授たちと戦いを繰り広げてきました。
たとえばテスト明けのある日、某講義の試験結果が大学構内の掲示板に張り出されたときのことです。試験のデキには自信があったにもかかわらず、掲示板に張り出されている「試験不可の者」という一覧表を見てぼくは憤り、すぐに教授の研究室に怒鳴り込みに行きました。
教授の言い分は至極シンプルです。
「冒頭の授業で言ったとおり、3回以上欠席した学生には単位はあげません」
普通の学生であれば、ここでシェーのポーズを3回決めるまでもなく、しおれたチビタの様相を呈して退散するのですが、ぼくにはカントという強い見方がいます。
「先生。先生がもしカントのコペルニクス的展開を理解していらっしゃるならば、出席して実力をつけ、良い点数を取ることも、出席せずに実力をつけ、良い点数を取ることも結果的には同じではないですか。それでも地球は回っているんです」
ここで忘れてはならないポイントは、「もしカントのコペルニクス的転回を理解しているなら」という一文を付けることである。インテリは非常にこの
「オメー、ひょっとして知らねーんだろぉ?」
という脅しに弱いのです。ぼくはこの手で100%の確率で不可だった試験を可にしてきた。9回ツーアウトからゲーム終了した後に審判が
「やっぱりこっちの勝ち!」
と宣告するのです。これはもうメークドラマ、メークミラクルを凌ぐ、もう大逆転なのであります。憧れていてはダメです。憧れるのをやめましょう。
ただコペルニクス的転回を一発カマス時に注意せねばならないことが一つだけあります。それはタイミングです。
コペルニクスと同様、地動説を唱えた天文学者にガリレオ・ガリレイがいます。彼はコペルニクスより随分と後に生まれ、コペルニクスの影響を受けて地動説を唱えたのですが、時は「暗黒の中世」末期。彼は魔女裁判にかけられることになってしまいます。
「火あぶりはイヤだぁ」
とガリレオはあっさりとローマ教会の方針である天動説を認め、裁判は無事終了します。そして裁判所を出る瞬間、ガリレオはこう呟くのです。
「それでも地球は回っている」
これはカッコ悪すぎる。まるで「帰りの会」で論争に破れ、先生に散々絞られた後の小学生のような態度ではないか。ぼくは幼き日の思い出を胸に、ガリレオ的人生は断固拒否するッ!
ただガリレオがその後の科学会に残した功績は大きく、このガリレオの弟子が、天球の楕円軌道を発見した「ケプラーの法則」で知られるケプラーであり、このケプラーの弟子のニュートンは地動説から「万有引力の法則」を導き出しました。
もしガリレオがいなければ人類が月に到達したのが200年遅れていたかもしれないと言われています。この後、ローマ教会がガリレオの正当性を認め謝罪したのは、なんと故ヨハネス・パウロ2世の在位期、阪神タイガースがバース、掛布、岡田とバックスクリーンに3連発を打ち込んで優勝してから5年後の1990年ということです。
もし、ぼくの死後、幼年の砌にぼくを苛めた人たちが、棺桶の前で、
「やっぱりあなたは正しかったわ」
などとノタマってもぼくは絶対にうれしくない(絶対そんなことはありえないのだけど)。
では、コペルニクスはどんな人生を送ったのか。
彼はその代表的な論文、「天球の回転について」を、教会との摩擦を避けて死の直前に刊行し、裁判にかけられることもなく平穏無事な学者としての人生を全うしたのです。
コペルニクスになるかガリレオになるか。これは全てタイミングが決めることであるが、このコペルニクス的転回をカマせた時の気持ち良さ、ぼくは好きだなあ。
(了)
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
