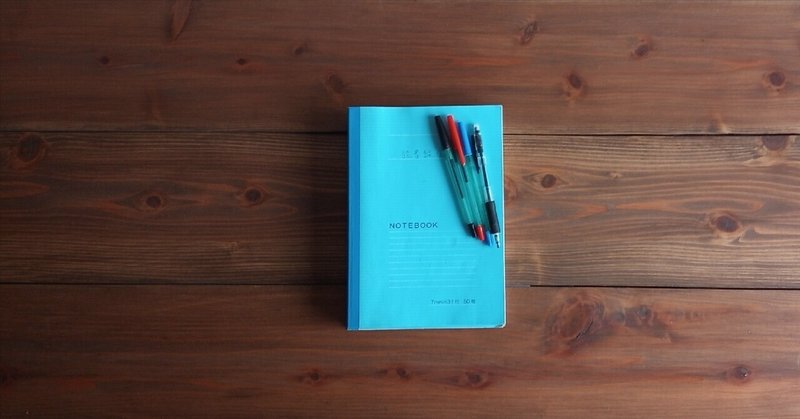
梁石日「血と骨 下」読書感想文
「血と骨」は「母と父」と置き換えることもできる。
古くからある、朝鮮の巫女の歌の中からきている。
「血は母より受け継ぎ、骨は父より受け継ぐ」という一節。
それは、家長制度を象徴する言葉。
血も、骨によって創られていることを前提としているからだ。
死んでも血肉はなくなるが、骨は残る。
「血は水より濃い」というが「骨は血より濃い」のである。
・・・ 梁石日は、そのように書いている。
主人公の金俊平のすさまじい暴力が許容されたのは「骨」である家長制度にもあったとも思われた。
自業自得ではちょっと悲しい
下巻になると、息子が成長して、同時に父親は衰えてくる。
息子は暴力に対抗する。
最後は、高齢で体が不自由になっている父親を、きっぱりと見捨てる。
自業自得といえばそうなる。
が、それまでには、さんざんと父親の圧倒的な暴力が描かれていたので、それはそれで物悲しい。
息子側の気持ちはわかる。
親を大事にできない自分も悩まされた。
結局は、なにをどうしようが、親の心根というのはなかなか変わらない。
ということは、自分の心根も似たようなものだろうけど、それは置いといて、この親子はこうなるしかなかったのかなとモヤモヤが残る読書だった。
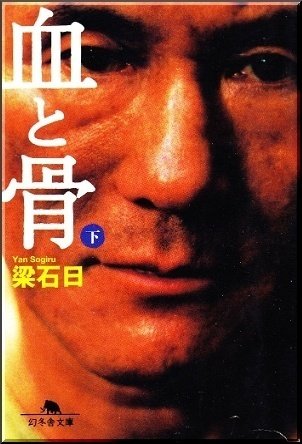
ネタバレあらすじ
戦後の混乱期
戦争が終わる。
戦後の混乱がはじまった。
金俊平は、カマボコに目をつけた。
カマボコが高級品となっていたのだ。
銀行員の初任給が22円のこの頃に、ひとつ2円で売られていたが、それでも品薄だった。
かつてカマボコ工場で働いていた金俊平は、作り方はわかっている。
工場を立ち上げようとするが、行政の認可が必要だった。
食料が統制されていたのだ。
そのため、大阪にはカマボコ工場が2件しかなかった。
カマボコ工場は開設された
工場を設立する資金は、4万が必要だった。
これは妻の英姫が用意した。
“ 頼母子講 ” の親をやったのだ。
いってみれば小さな信用金庫みたいな “ 頼母子講 ” で、毎月、仲間うちで積み立てていくのである。
親をやると、まとまった資金を運用できた。
飲食店を長年やっていた英姫には、在日朝鮮人社会では、信用と人間関係があった。
行政の認可も取得できた。
金俊平の唯一といっていい友人が、協力してくれたのだ。
なかなか認可しないのを恫喝とデモで圧力をかけるという強引な方法だったが、戦勝国である朝鮮人であることが有利に働いた。
カマボコ工場は稼動する。
友人知人も職人として働きにきてくれている。
卸し問屋を回った金俊平は、あまりの売れ行きに、初日から震えが止まらない。
金は付加価値の高いものに集まってくる。
多くの人々が飢えていようと、高級品を欲しがる金持ちもいたのである。
家族が報われることはなかった
カマボコは売れまくって、製造が間に合わないほど。
息子の成漢も、朝晩と働かせられた。
が、家族が報われることはなかった。
金俊平は儲けを独占して、家族のために使うことがない。
どころか、資金を用意した英姫にも返済をしない。
酒を飲んでの暴力も収まることがなかった。
家族に平和が訪れることもなかった。
金俊平の女癖も止まらない。
自宅の近くに愛人と住んでいる。
自ら特製のごった煮を作って食べている。
精力をつけるためだ。
愛人が病気になると、また別の愛人をつくって呼び入れて、介護をさせてもいる。
高利貸しとしても財を成す
金俊平は、稼いだ金は徹底して節約する。
着飾ったり見栄を張ることもない。
誰も信用しようとしない。
カマボコ工場の職人に対しても暴力を振るった。
皆、同郷の在日朝鮮人だ。
友人たちも離れていった。
カマボコ工場を閉めてからは、高利貸しをする。
高利貸しとしても、金俊平は間違いがなかった。
確実に貸金を取り立てて、資産を増やしていく。
金俊平は、70歳になった。
英姫は、子宮癌で死去している。
年齢には勝てなくて、行動力も体力も衰えていた。
老齢になっても、愛人には子供を生ませている。
が、金俊平が脳梗塞で倒れて、後遺症で体が不自由になると、愛人は娘を連れて家出した。
4人の子供が残されて、金俊平は邪険にされていた。
ラスト
息子の成漢である。
東京にいる。
もう14年会ってない。
父親と対決して家を出たのだ。
タクシー運転手をして暮していて、身内と呼べるのは2人の子供くらいなものである。
金俊平は、北朝鮮で死んだらしかった。
半島に建国された北朝鮮は “ 地上の楽園 ” として喧伝されていて、帰国事業が盛んだった。
期待を託して、全財産を持って北朝鮮に渡ったのだ。
タクシーを運転する成漢は考える。
最後に家を訪ねて、久しぶりに顔を合わせたときは、すでに金俊平は体が不自由だった。
が、やはり本性は変わってはなかった。
見切るようにして背を向けて、その家を出た。
そのとき、金俊平は「チャネ、チャネ(あんた、あんた)」と呼び止めていた。
その声を無視して去った自分を冷酷だと思ってはいる。
父を見捨てたのは正しかったのか。
肉親という因果関係に憂鬱だった。
