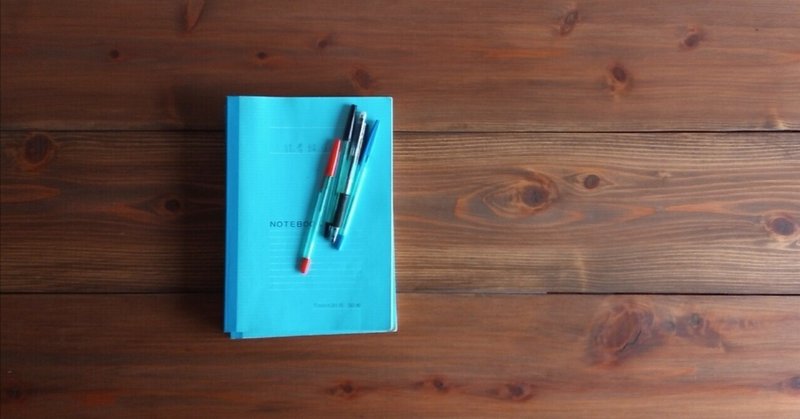
三島由紀夫「永すぎた春」読書感想文
比喩が多彩なのが、三島由紀夫の好きな点のひとつ。
定番の『~のように』とか『まるで~だった』が連発しない。
比喩といっても何種類もあるらしいが、そこは文学者でもないので勉強中ということにする。
で、この比喩の類が陳腐すぎると、かつ安易な小説だと、それだけでおもしろくない。
が、三島由紀夫の放つ比喩は、上手い具合に “ シニカルさ ” を混ぜ込んである。
人物を冷ややかに眺めながら、現実を冷ややかに横目で見て、人々の崇高な行為や想いなども、実のところは鼻で笑っている。
これだけだったら、ただ単に性格がひねくれてるヤツ。
自分もよくしている。
こういう根性が腐った人の成れの果てが受刑者、というのもよくわかっている。
だけど、三島由紀夫は受刑者などにはならない。
ひとくくりの比喩でまとめる。
さほど悪意も感じさせなく、激しい主張もなく、批判などもなく、納得させようという姿勢もない。
変わりに、楽しい想像をさせる比喩を一発ぶちこむ。
三島由紀夫に共感できるところ
これが、ウィットというのか?
文学的というのかもしれない。
教養は感じさせる。
とにかくも、なにかを気がつかせる比喩を散りばめる。
それほどまでに比喩に共感できるのは、普段の自分も、内心では同じようなことをしていてるからかもしれない。
冷ややかに眺めて横目で見て、鼻で笑って、茶化している。
が、自分の場合は、はるかに無能すぎる。
ただの低脳な悪口になってしまう。
皮肉にすらもなってない。
もし口にしたなら、相手を怒らせるのも自覚している。
だから三島由紀夫の、どこかクスリッとさせる、嫌味と皮肉たっぷりの比喩が繰り出されると、うっとりして仕方がない。

感想
手軽に書いた小説らしい。
巻末の解説にそうあった。
肩の力を抜いて読めた。
その分、比喩は手がこんでないが、まったく陳腐ではなくて十分におもしろい。
あらすじを3行でまとまる。
T大法学部の学生が、古本屋の娘と婚約をした。
結婚は1年後で、それまですったもんだがある。
それらを2人は乗り越えて、結婚を迎える。
という内容。
そのまんま「永すぎた春」である。
恋愛小説というのか。
時代が昭和の20年代なので、ちょっと意識のちがいはあるが、当時はそういうものだろうから、そうは気にはならない。
で、定番の “ 上流家庭 ” が登場。
父親が会社の重役で、母親はいわゆる “ 有閑マダム ” で、女中がいて、別荘があってという家庭の息子が主人公。
このあたりは、三島由紀夫の実際と被っていると思われる。
そういうところでいえば、三島由紀夫が、ああいう比喩を繰り出せるのは、余裕があるお坊ちゃまだったからかな、という感想があった。
笑ってしまった箇所
今まで読んだ三島由紀夫の小説で、比喩のほかに「ここがいい!」と思わせるのが、登場人物がはっきりとしているところ。
次から次へと、入れ代わり立ち代わり、無駄に人物を登場させて話を進める、という展開は感じられない。
「あれはなんだったんだろう?」という謎の人物を、そうそうは気軽に登場させない。
そこがいい。
じっくりと主人公を書き上げて、そのほかの人物は、主人公のために登場するという緻密さがある。
が、この気軽に書かれたというこの小説は、中盤になって、唐突に古本屋の娘の兄が登場してくる。
とってつけたように、強引に登場させている。
兄を登場させた強引さには、三島由紀夫は言い訳がましい。
ここが珍しくておもしろい。
笑ってしまった。
いくら三島由紀夫でも、手軽に書きすぎて焦ったのだなと感じたのが、穴を見つけたようで気持ちよかった。
ネタバレあらすじ-宝田郁夫の手記風
木田百子との婚約が決まった
百子との婚約には、母親は不服そうだった。
が、こうしてはっきりと決まってしまうと、今度は木田家の人たちに、自身を精一杯によく見せようとする努力が、ありありと見てとれた。
両家の婚約の挨拶の場が持たれた。
そこでの母親は、まるで天使のようだった。
自身の努力にすっかりと満足して、豊かな果物の果汁のような慈愛が、その小太りの全身にあふれていた。
結婚は1年後。
私の大学卒業と同時にとなる。
そのあと百子とは、銀座の夜の大通りをじっくりと歩いた。
百子は、子供っぽい毛糸の手袋をしていた。
1月の冷たい風が吹いた。
幸福というのは、どうしてこんなに不安なのだろう?
百子のほうは、幸福に酔っていたが、自分は幸福を意識すればするほど、なんだか胸の中を隙間風が通っていく気がした。
宝田郁夫の不満
それからは、大学の帰りに、百子の家に寄るようになる。
大学の正門の前の古本屋が、その家だった。
古本屋とはいっても、湿って埃っぽい店ではなく、けっこう大きな店で、店員も数名いて女中もいる。
2階に上がると、百子の部屋があった。
決めたわけではないが、結婚まではキスをするに留める。
その日も、授業が終わると店に寄った。
私が姿をみせると、店員も女中も挨拶をしてくる。
公認されたことは、なによりの幸福だが、愛情とは別に煩わしさを感じていた。
年上の、本庄つた子の誘いにのったのは、そんなときだった。
画廊で知り合ってから、電話で4度か5度ほどのやりとりがあって、アパートに誘われたのだ。
私は、その誘いに乗った。
百子の嫉妬がみたかったという、言い訳もあった。
実は、1回だけ、百子に対して、嫉妬を見せてしまったのだ。
従兄弟と歩いていただけなのに、それを目にした私は取り乱してしまったのだ。
そのときは、百子は喜んでいた。
ひとつ負けた気がしていた。
本庄つた子の誘惑
6月のその日、世田谷の本庄つた子のアパートに向かう。
雨が強く振る夜だった。
ドアには小さなメモがある。
近くまで出ているので2階で待っていて、とある。
メゾネットタイプの小洒落たアパートだった。
2階は、アトリエとなっている。
部屋に置かれた椅子の上には、つた子の下着が演出のように置いてあった。
それらを眺めながら、窓際の長椅子で横になっていると、階下のドアがひらく音がした。
つた子が帰ってきたようだ。
と、思ったらちがう。
なんと、宮内だった。
28歳の同級生の宮内で、若ハゲで妻子があって、今まで何度も結婚について相談をしていた。
今回のことも、宮内にだけは話していた。
止めることもなかった宮内には、訊かれて相手も時間も場所も教えていたのだったが、このためだったのか。
でもなんのために?
あっけにとられていると、ドアのかげから、職員室に入ってくる生徒のようにして、おずおずと百子が姿を見せた。
びっくりして長椅子から跳ね起きた。
宮内の喝破
宮内に怒りを感じた。
「なんだ!なにもかもメチャクチャにするつもりなのか!」
「メチャクチャにするのは君のほうだ!」
宮内の言葉には、不思議な威厳があった。
百子は「すぐに一緒に帰ろう・・・」というが、宮内はそうさせない。
「君は対決するんだ。このまま帰ったら、百子さんの女房気取りに妥協した世間の男と同じつまらん存在だぞ」
「・・・」
「もし、つた子さんを選ぶのだったら、百子さんの目の前で
遠慮なく飛び込むんだ」
「・・・」
百子は、真っ白な顔をしている。
なにも言わずに、レインコートを脱ぐと、濡れたまま無造作に置いた。
椅子の上の、つた子の下着の上だった。
宮内は続けた。
「対決するんだよ。怖いのか?いいか、こんなこというのは俺の経験からなんだ」
「・・・」
「去年、俺は、妻の昔の恋人とかいう男を、妻の目の前で殴り倒してやったんだ」
「・・・」
「俺は偽善者ではないと信じることができたのは、まさにそのときなんだ」
「・・・」
宮内が悪魔に見えた。
どうして、成算ありげに、こうして人の苦境を楽しんでいるのかがわからなかった。
「人間には憎んだり、戦ったり、勝ったり、そういう原始的な感情がどうしても必要なんだ」
「・・・」
「君たちのは温室の中の愛だよ。そんなものは、今夜、捨ててしまえ」
「・・・」
百子が隣に座って、手を握ってきた。
「百子さん、そんな風に手を握ってはダメだ。自信があるなら、男を完全に自由にしておかなくちゃダメだ」
「・・・」
そのとき、階下のドアが開く音がした。
つた子が帰ってきたのだ。
玄関の靴は隠してあると宮内はいっていたが、部屋のドアが開いてからは、つた子は平静な顔をして3人を見回した。
そつがなく、お互いに挨拶をすませたあとは、宮内が進行係となったようだった。
あとは、自分がどちらかを選ぶのだが、面目丸つぶれの状況に、早くこの場から逃げ出したいだけだった。
宮内は、部屋の隅に立ったまま。
宝田郁夫、目覚める
つた子と百子の応酬がはじまる。
が、つた子のほうが、女としては格上だった。
浴びせられた屈辱に、百子は思わず目を閉じている。
さすがのつた子も、少し気が苛立ったようだ。
椅子にある百子のレインコートを叩き落として、自身の下着を取り出して、隣の部屋に投げ入れている。
それを目にして、なぜか勇気が湧いた。
「レインコートを拾いなさい」
「あら、お友だちがいると勇気がでるのね」
そのとき自分は、心のうちに、強さを、得も知れない力を感じたのだった。
それが言葉を重厚にして、態度を穏やかにさせた。
再度、つた子に命令をした。
「拾いなさい」
「自分で拾ったらいいんだわ」
つた子は悔し紛れに、それでも微笑を浮かべながらも、1言2言返してきたが、自分のほうもおかしくなって微笑がこみ上げてきた。
宮内に聞いた。
「これでいいか?」
「まあ、いいだろう」
百子は涙を浮かべて立ち上がって、腕をつかんできた。
つた子はいう。
「もうおかえりになるの?でも、勝ったの、負けたのって、なんのことだかさっぱりわからないわ」
「レインコートが勝負の山でしたね」
宮内が脇から言っていた。
突如に噴火した木田東一郎
7月になると、百子の兄、・・・木田東一郎というが、その兄がいきなり入院した。
盲腸だ。
店の後継者となる彼だったが、小説家志望といいながら、なにをするのでもなく、頼りがなく、煙ったような存在だった。
百子だって、自身の婚約を優先していて、あまり頭はよくないが心のやさしい兄を、ないがしろにしていたのかもしれない。
この休火山は、突然に噴火して、一家の注意をひくために盲腸になったのかもしれなかった。
そして、休火山というのは、いったん噴火をすると止まるわけでもなかった。
退院したくない、担当の女性看護師の浅香さんと結婚したい、と言い出したのだ。
まさに噴火である。
私は、それを母に話してしまった。
その母が作戦行動に出た。
無沈戦艦でもある母は、こういった話を全部こわすか、まとめるかのどちらかだった。
母の作戦は成功した。
休火山、いや、彼と浅香さんの結婚は、まとまったのだった。
木田東一郎、動く
10月になって、彼の結婚話は破談しかけていた。
浅香さんの母親が、全てをぶちこわした。
支度金のために、百子にちょっかいをだしたのだ。
神田の料理屋で百子に酒を飲まして、私の友人の吉沢が襲う段取りをつけたのだ。
吉沢も、そういうゲスな男だった。
百子は逃げ出して無事だったが、当然として騒ぎになった。
浅香さんの母親が、こんな暴挙に出たのは、1人で育てた娘が幸せになるのに嫉妬したのかもしれない。
なんにしても、百子の兄だけは、いつまでも悩んでいた。
どうしたらいいのか、わからないようだった。
今まで読んだいろんな小説も、自身が書いた小説も、目の前の問題には、なんの解決も与えてくれなかったのだ。
今まで、一生懸命にかじりついてきた、文学そのものに対する疑いも兆しているのか。
だいたいにして、この小説家志望は、他人の心なんかわからない人間だった。
そういう人間が、小説を書き出すとは不思議なことだったが、おそらく他人の心がわかりすぎる人間は、小説なんか書かないのであろう。
彼はヒステリーを起こして、読んでいた小説も、人生読本などいうイカサマな本も、ついでに自身で書いた小説の原稿も破いた。
そうして、戦争中に徴用されたときの、家屋の取り壊し作業のことを思い出した。
破壊のほうだ。
建設よりも破壊のほうが、ずっと自分の力の証拠を目に見せてくれる。
原稿を破っているうちに、だんだんと自分の力を確信できるようになってきたのである。
彼はすぐに行動をおこし、浅香さんの元に向かった。
百子を連れてだった。
もう、12月だった。
ラスト5ページほど
翌朝、百子とは、大学の構内を散歩した。
安田講堂の前を右に右折して、山上御殿の芝生の斜面に2人して座った。
兄の結婚話は、完全に破談となった。
昨日の兄は、妹の結婚のために行動したのだ。
相手の浅香さんも、それをわかって憎まれ口をきいたのだ。
そのように、2人の意見は一致した。
もう、1ヵ月もしないうちに結婚となる頃でもあった。
「そうだわ、誰にもすまないなんて思わない。幸福って、素直にありがたく、もらっていいものなのよ」
「そうだね」
百子が、永い曲折を辿って達した結論が、はじめて本当に、私に自信をつけた。
私は明るい声で応えたあとは、そろそろグランドの周辺に増えてくる制服の群を気にしながら、やさしく百子の肩に手をかけた。
