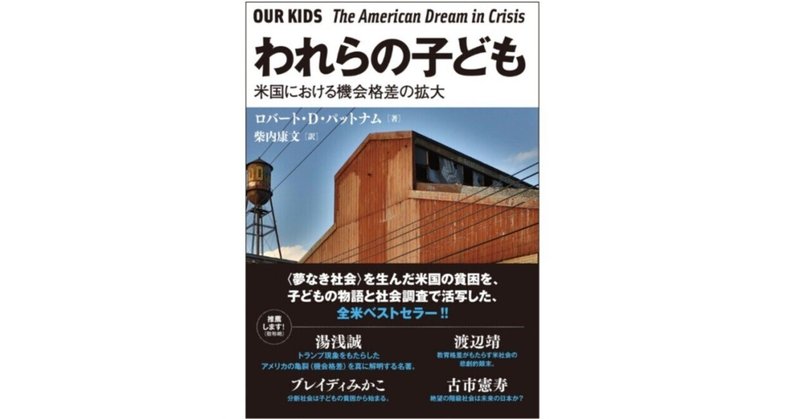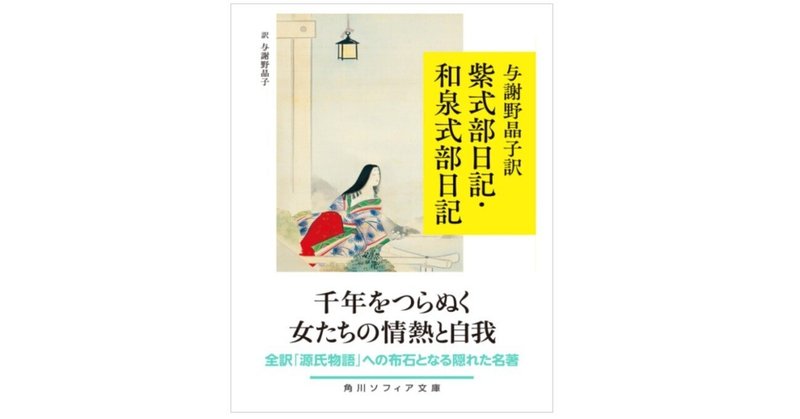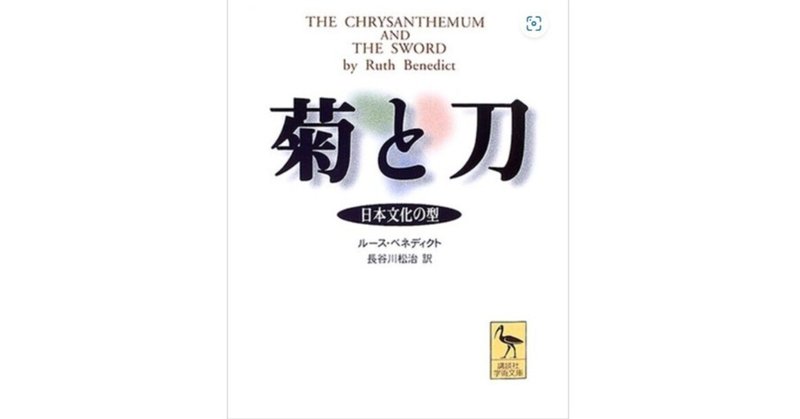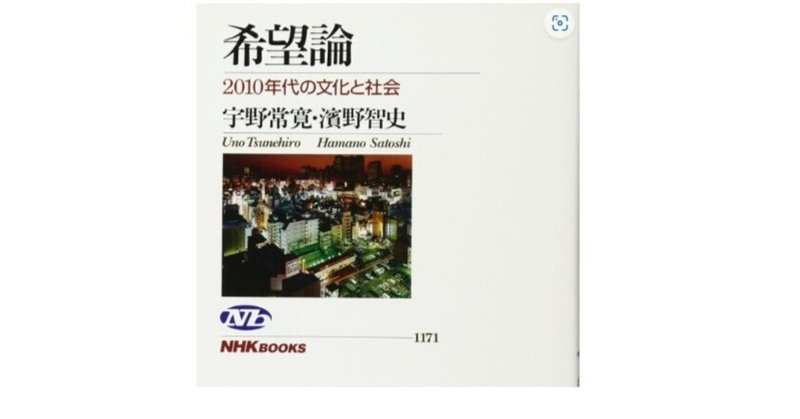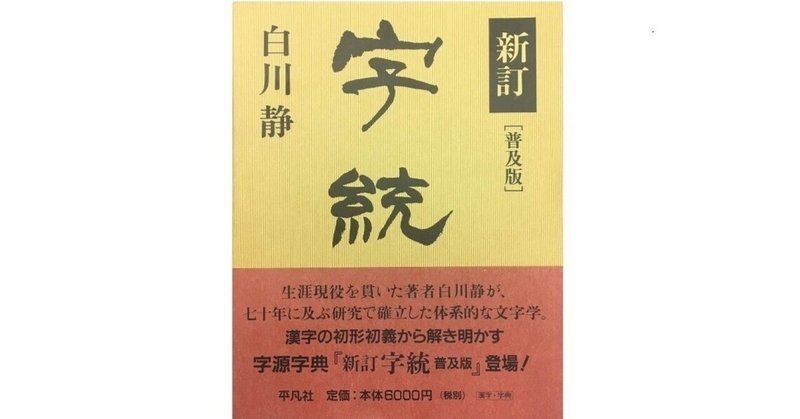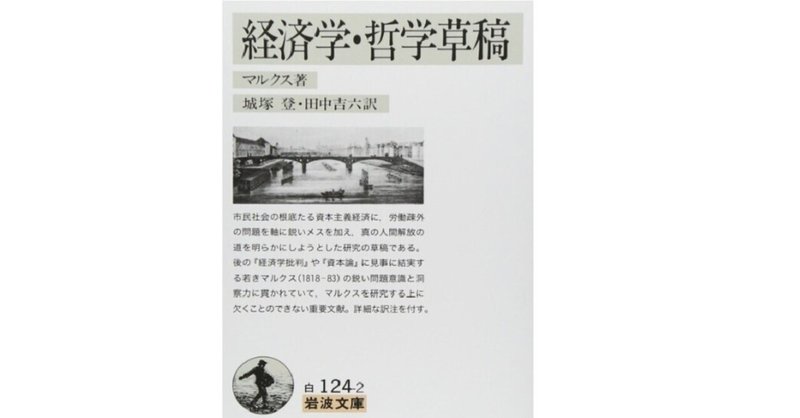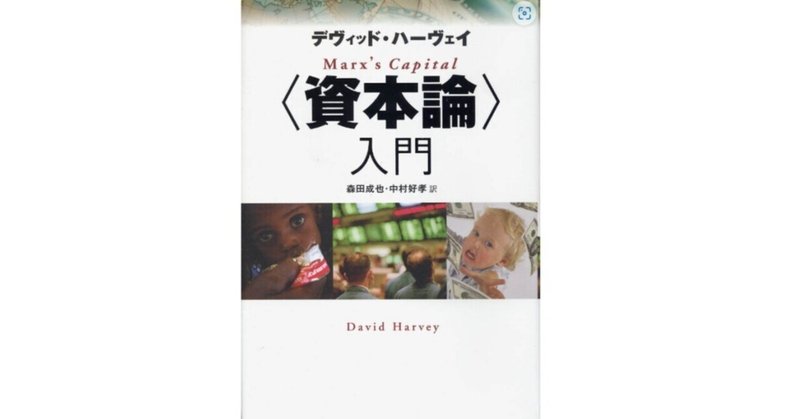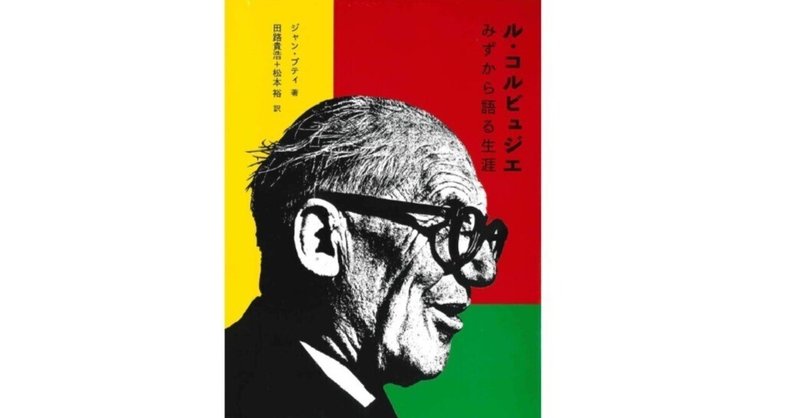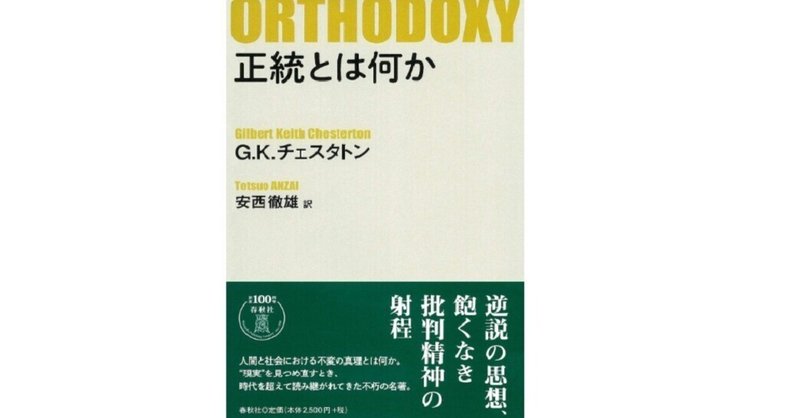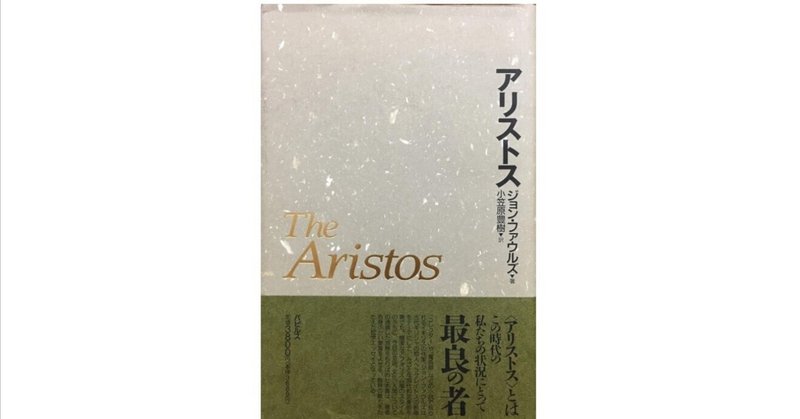記事一覧
【書評】与謝野晶子訳・注解 紫式部日記
「今自分のいる部屋というのは、黒く煤けた一室で、十三絃の琴と七絃の琴とか時々弾かれるものでありながら、自分の不精からアメの二には気をつけて琴柱を倒しておけと侍女達に命じることもしないでいるので、塵がいっぱいに積もっている。琵琶はまた置棚と柱のうしろへ上のところを突込んだまま一つは右に倒れ、一つは左に倒れている。大きい一揃いの置棚の上へ隙間なしに置かれてあるのは、一つの方は歌書と小説類の古い本で、
もっとみる【書評】デヴィッド・グレーバー『万物の黎明』
「現代の社会的不平等の起源はどこに?」
それを解き明かそうとしたのがこの本だ。著作者の立脚点は人類学。
「人類史のなかで、なにかがひどくまちがっているとしたら――そして現在の世界の状況を考えるならば――そうでないと見なすのは難しいのだが――おそらくそのまちがいは、人びとが異なる諸形態の社会のありようを想像したり実現したりする自由を失いはじめた時から始まったのではないか。おそるべき想像力の
【書評】白川静『字統』の理念
白川静とは何者だったのか、中国人がなし得なかった感じの体系的な成り立ちを明らかにした人だ。
甲骨文字から現代に到るまで、感じは3500年の歴史を持つ。象形がいまに生きている。そのなりたちから現在と未来の姿を展望すると、何が見えるか。
「象形文字は世界の模型だ」と白川は言った。「文化の上からは世界は、印欧系、アラブ系、東アジア系に三分され、うち東アジアだけが最も原始的な文字を持つ。そして宗教を
ル・コルビュジエの遺物
「わたしは多くの国々に行き、多くの人々と語り合った。わたしには理念があり目的があった。わたしは多くの病める声を聞いた。貧困があり階級があり差別があった。わたしは解放の唯一の道を説いた」
この言葉は革命家ではなく建築家が発したものだ。彼の名前はル・コルビュジエ。強い社会変革の意思を持ち、それを建築によって具現化しようとした。その彼が労働者のための集合住宅を設計することになった。
マルセイユに<
【書評】ジョン・ファウルズ『アリストス』
序にいわく、「アリストス」とは古代ギリシャ語で、「与えられた状況のための最良の者」というほどの意味だそう。
生きている誰しもが今という状況と向き合っている。その人なりの人生観や世界観を作りつつ、都度の出来事に対処している。著者ファウルズもまたそうで、この本は「1950年代に、一人のイギリス青年と世界とが出会ったさまを記したもの」である。
彼によれば時代は暗い。彼はこう言う。
「この世紀は、