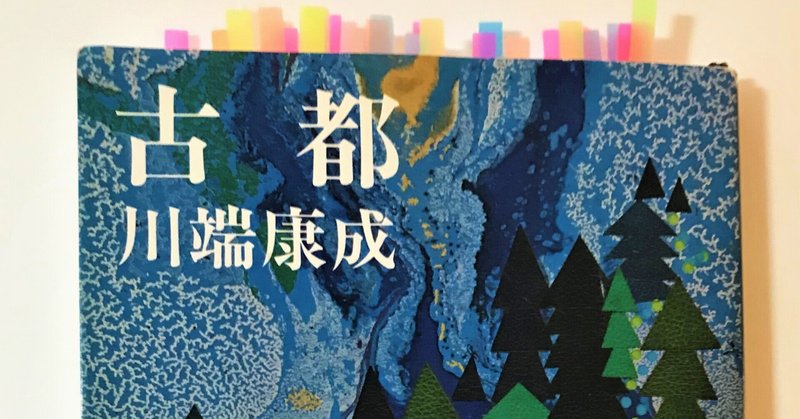
【感想文】古都/川端康成
『ふたりっ子ちゃん』
江戸の蕎麦ッ食いに言わせれば「ものは器で食わせる」そうだが、本書『古都』は「花で読ませる」小説である。
生き別れの姉妹、千重子と苗子の巡り合わせが描かれたこの作品は、第一章「春の花」に始まり最終章「冬の花」をもって終える。冒頭で述べた通り、春の花、冬の花が意味するところを理解するだけで『古都』の真髄を会得したにさも似たり。では早速やってみよう。
▼春の花について:
春の花は「すみれ」である。作中の二株のすみれが千重子と苗子の象徴であることは説明を待たずして明白である為、根拠は割愛する。ここで、物語が進むにつれ、すみれの状態が変化するという点に注目すると、まず冒頭部分で <<すみれの花がひらい(新潮文庫,P.5)>> ており、中盤「北山杉」の章において、千重子が苗子を初めて見かけた次の場面では、<<あ、すみれの花が、いつのまにやなくなってしもた(P.92)>> とある。話は進み、千重子と苗子が再会を果たし、後半「秋深い姉妹」の章では <<幹に宿った、二株のすみれの葉は、薄黄ばんでいた。(P.200)>> と、ここでは花だけでなく、葉も枯れておりこれ以降、すみれの状態に関する描写は無い。
以上の事から分かるのは「千重子が苗子と出会い二人の関係が深まるにつれて、すみれは枯れていく」という相関である。
では、なぜすみれは枯れるのか。思うに、このすみれは千重子を通じて描かれていることから、離れ離れの二株のすみれは千重子の孤独を暗示していると考えられ、千重子と苗子の再会によりこの孤独は解消される。つまり、再会によって、千重子は今後、すみれを見て孤独感に思いを馳せる必要は無く、その象徴でもあるすみれの存在意義が失われた為に、枯れたのである。
▼冬の花について:
冬の花は「北山杉」である。その理由は、<<北山杉は、じつにこずえの方まで、枝打ちしてあって、千重子には、木末に少し、まるく残した葉が、青い地味な冬の花と見えた。(P.222)>> という表記、あるいは、<<じつに真直ぐな幹の木末に、少し円く残した杉場を、千重子は、「冬の花」と思うと、ほんとうに冬の花である。(P.224)>> という非常に印象的な一文が称する様に、後半は北山杉の描写が占めていることからも窺うことができる。
この北山杉が象徴するものは結論、苗子である。
その根拠の説明にあたり、まず、杉の花は一見して褐色がかっており蕾も小さい。それは葉と見間違える程に花には見えず地味という印象を与える。苗子は、呉服屋の千重子とは違って化粧っ気もなければ友人もおらず質素な居住まいの、地味な女性である。また、「北山しぐれ(P.228)」の場面において、北山杉の林立および山々は薄い灰色にもやが掛かり、<<つつまれたように、けじめを失ってゆく。>> そして、もやの <<白いものは消えたり、また、加わったりする。>> とある。北山しぐれにより、消えつ現れつする杉の木立、それはまるで自身を「幻」と称した苗子の様である。
以上二点の結果を踏まえて冒頭に立ち返れば、古都は「花で読ませる」小説だといえる。
といったことを考えながら、ぼんやりしていたところ、『マナがカナをのぞく時、カナもまたマナをのぞいているのだ』と語る哲学者の声が聞こえてきた。
以上
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
