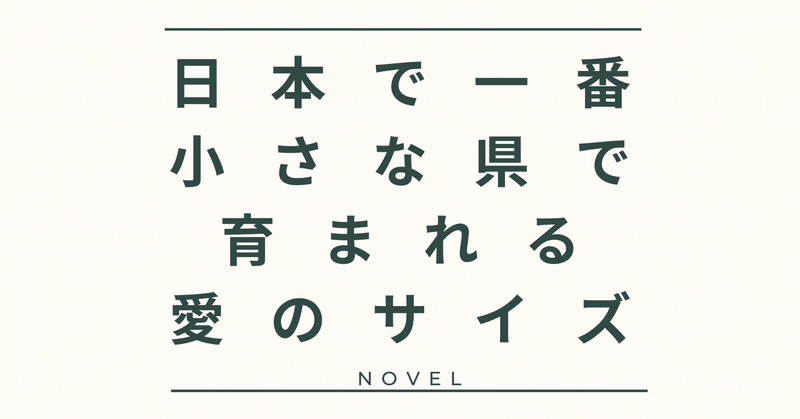
日本で一番小さな県で育まれる愛のサイズ【一話】【創作大賞用】
完読時間目安:50分
あらすじ
一人になった祖母と一緒に暮らすために幸助は高校卒業以来、八年ぶりに故郷である香川県琴平町に帰ってきた。金比羅山の参道口にある讃岐乃珈琲亭はかつて祖父母とよく通っていた喫茶店だ。幸助はそこのマスターに働かせてもらえないかとお願いしたところ快く了承を得た。しかしマスターは雇う条件として、とある宿題を幸助に課した。讃岐乃珈琲亭では幼馴染の春子とも再会することとなる。日本一小さな県である香川県で営まれる愛と青春の行方は。
◇
去年の今頃は、まさかこんな状況になって桜を眺めているだなんて想像すらしていなかった。桜の満開を祝すかのように五年ぶりに開催される歌舞伎の旗が踊っている。
幸助が故郷の香川県琴平町に戻ってきたのは一年前のことだ。高校を卒業して以来の帰郷で、気づけば幸助は二十六歳になっていた。
◇ 春 4月
一年前のその日。
幸助はかつて祖父母とよく来ていた金比羅山の参道口にある喫茶店の前に立っている。緊張した面持ちで喫茶店への扉をまたぐ。マスターと目が合うと、すぐに話かけてきてくれた。
「おう、幸助じゃないか、久しぶりだな。しばらく見ないうちにまた一段と男前になったんじゃないか」
相変わらず気さくに振舞ってくれたのが嬉しかった。
朝のピークタイムを終え、アルバイトらしき人たちがせかせかと後片付けに追われている。
店内は広々としていて、十五テーブルはあるだろうか。
一番奥のソファ席で常連らしき老婆がひとりで珈琲を堪能していたり、入り口に一番近い二人席で観光客らしきカップルが旅の予定について話合ったりしている。
カウンターの中では女性とマスターがゆとりを持って作業をしていて、手元の動きには無駄がなく熟練の風格が漂っている。
この喫茶店で幸助は沢山の初体験をした。初めてのお子様ランチを食べたのもここだし、初めてのクリームソーダもここで飲んだ。ほっぺたが落ちると言う表現を知ってから、思い浮かべるのはここのお子様ランチを食べた時の思い出だ。
ここ、ここ、とばかり言っているがもちろん『ここ』という名前の喫茶店ではない。『讃岐乃珈琲亭』という立派な看板を背負っている。
それなのに祖父母が讃岐乃珈琲亭に幸助を連れて行く時は、いつも、「こうちゃん、あそこに行くか」とか、「こうすけ!ソーダ飲みに行くぞ」としか言わなかったので、この喫茶店にちゃんと名前があることを知ったのは中学生になった時くらいだった。
その頃に幸助は祖父母の真似をして、ブラック珈琲を飲み始めた。初めて飲んだ時は炭をそのまま飲んだかのような苦味が口の中いっぱいに広がった。
だから本当は全部吐き出してしまいたかった。
だけど祖父母のような大人に早くなりたかった幸助は、ここの珈琲を飲めることも大人への近道だと考えて、毎回我慢してブラック珈琲を飲み続けた。
飲み続けた甲斐あって中学を卒業する頃には苦味の奥に潜む珈琲の旨みを知ることができ、それ以来幸助は家でも進んで珈琲を飲むくらい珈琲が好きになった。
黄昏れている幸助をみてマスターが再度声をかける。
「ほら、珈琲サービスしてやるから適当に空いてるとこに座りな」
「マスターありがとう。ただ今日は珈琲を飲む前にマスターに頼み事があるんだ」
真剣な顔つきの幸助に気づいたマスターは幸助をカウンター内にある小さな休憩スペースに導いた。
幸助が今日『讃岐乃珈琲亭』を訪れたのは、珈琲を飲むためでもナポリタンを食べるためでもなく、ここで働かせてもらうためだった。
◇
幸助の育ての親である祖父が去年の秋に他界したのをきっかけに、もう一人の育ての親である祖母の側に居られるにはどうしたらよいかと、幸助はあれこれ考えていた。
祖母を幸助が働いていた東京に呼ぶことも考えたが慣れ親しんだ地元から祖母を引き離すことに幸助は強い違和感を覚えた。きっと祖母もできることなら地元を離れたくはないはずだ。
どうしたものかと悩んでいたが、シャワーを浴びている時に、ふと、自分が仕事を辞めさえすれば祖母の側にいられることに気づいた。気づいてしまえば簡単なことだった。
ただ大きな躊躇はあった。
せっかく運良く得た東京の珈琲屋での仕事は幸助が高校時代に夢見ていた仕事であったからだ。
夢は叶ってしまうと現実とのギャップに落胆するものだが、幸助の場合は、夢見ていた時と夢を叶えた時のギャップはほとんどなかった。しいて言えば夢見ていた時よりも、珈琲屋での仕事は自分の天職だと思えることがよくあった。
自分が大好きな珈琲に携われていることがまず嬉しいことであり、その大好きな珈琲を通して何人もの人に笑顔と安らぎを提供できていることが誇らしかった。珈琲屋の店長は職人気質で幸助もよく叱られたが、全てが珈琲とお客さん、そして幸助のことを想ってくれているのが伝わってきたから、苦ではなかった。
それにそこで働く同僚たちも幸助と同じような考えを持って働いていて、すぐにかけがえのない仲間となった。
同僚たちとは仕事を超えて沢山の思い出を共有した。休みを合わせて鎌倉や仙台に遊びに行ったのは今でも幸助の中で色濃く印象付けられている。
鎌倉では今は元彼女となってしまったが由紀と付き合うきっかけとなった。仙台では桔介(きすけ)と仕事論で白熱しすぎて大喧嘩をしてしまった。その全てが幸助の青春であるのだ。
だからそんな仲間たちと離れて地元に帰ることは大きな決断ではあった。それでも祖母にはもう頼れる身内が幸助しかいないから、祖母の側に居てあげたい想いが勝った。
一度決めたことは必ず実現させる性格の幸助であったが、珈琲屋の皆との送別会では、その決断が揺らいだ。仙台での大喧嘩以来、若干の気まずさを抱えたままだった桔介が送別会が始まってまだ数十分というところで大泣きし始めたからだ。
「仕事の考え方は違ったけれど、俺は幸助の珈琲が世界一好きだったし、幸助のこともこの中の誰よりも好きだ」
なんて恥ずかしい台詞を何度も幸助に送った。
会の終盤では店長が
「幸助、お前の優しさと仕事への情熱に俺も周りの皆も何度も救われてきた。そして今度はその優しさを親に向けることを決断したことを尊敬している」
と言った。この時初めて店長の涙を見た。
店長は続けた。
「距離は遠くなってしまうが俺たちも幸助の家族だと思っている。だから何かあったらいつでも俺たちを頼ってほしい。長い間ありがとう」
終盤は幸助の方が何を言われているのかわからないくらい号泣していた。
送別会が終わって居酒屋の前で皆との別れを惜しんだ。由紀と目が合い、由紀が幸助に届けるように「元気でね」と言ってくれた時は由紀との思い出がフラッシュバックしてきた。
幸助は改めてどれだけ豊かな人たち、かけがえのない人たちが側にいてくれていたのかを身体全部で感じていた。
だからその後のことはあまり覚えていない。
気づいたら香川県行きの深夜バスに乗っていて、既に四国へ上陸していた。
目の周りは真っ赤になっている。
琴平のバス停に着いた頃にはもう夜が明けていた。
第二話以降へのリンク
第二話
第三話
第四話
第五話
第六話
第七話
第八話
第九話
第十話
ここまで読んでいただきありがとうございます。

