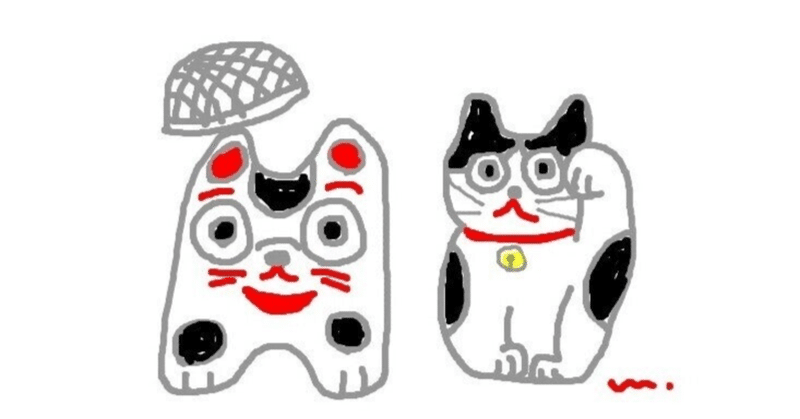
へっぽこフリーライターが退職から開業までにやったお金の手続き(前編)
2022年8月に会社を退職して、10月に開業。1月に再就職手当を受け取るまでの手続きをまとめてみます。あくまでへっぽこフリーライターが実際にやったことをまとめただけなので、正しいかどうかは分かりませんが、今のところ不都合なく暮らしているので参考までに。
お金にまつわる手続きでやったこと
何から手を付けたらいいか分からなかったので「フリーランス 開業準備」とか「フリーライター 開業準備」といったキーワードで一通り検索して、上位記事に書かれている手続きをリストアップしました。
失業手当・再就職手当の受給
開業届・青色承認申請の提出
改めて見ると面倒くさそうな手続きだな~という感じがしますが、退職してから開業まではのんびり過ごしていたので、タスクを一つ一つこなしていくのは苦ではありませんでした。
ここでは、実際にやった手続きをまとめていきます。失業手当等の受給や開業届の提出については長くなるので、別の記事にしようかな。まずは保険・年金・税金の話まで。
国民健康保険への加入
社会保険から国民健康保険に変更するため、役所で手続きを行いました。退職の翌日から14日以内に行う必要があるそうですが手続きしないと医療費が全額自己負担になってしまうので、なるべくすぐに行うのが無難ですね。
手続きに必要なもの
健康保険資格喪失証明書
マイナンバーカード
印鑑(認印)
手続きの流れ
「健康保険資格喪失証明書」は、退職した会社から受け取る書類です。3点を持って市町村の役所に行き「会社を退職したので国民健康保険に加入したいのですが…」と伝えると、20分もかからずに新しい保険証が交付されました。
保険料の通知は、世帯主へ「国民健康保険料決定通知書」が送付されます。国民健康保険は、本人ではなく世帯主が納税義務者なんですね。
あまりのスムーズさに呆気に取られてしまいましたが、これで病院に行くことになっても大丈夫だ…と安心したことを覚えています。
国民年金への加入・前納・口座振替
会社に勤めているあいだは厚生年金が給料から天引きされていましたが、退職したら14日以内に国民年金に加入し、自分で支払いをしなければなりません。扶養を受けていないフリーランスは第1号被保険者にあたるため、保険料は16,590円/月(令和4年度)。
ただし「前納」「口座振替」を行うと納付額がお得に。将来いくら年金が受け取れるか分かりませんが、どうせ納付するならお得なほうがいい。ということで、加入時に前納と口座振替の手続きまですべて行うことにしました。
手続きに必要なもの
年金手帳
マイナンバーカード
本人確認書類
退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書のいずれか
印鑑(認印)
手続きの流れ
国民健康保険の加入と同日に、市町村の役所で手続きを行いました。ただ、その日に行えるのは国民年金への加入までで、納付書は後日送付。口座振替の手続きも納付書が届いてから行うことに。
納付書の束が届いたのは9月下旬。翌々年の3月までの期間、毎月支払う場合と、まとめて前納する場合の両方の納付書が送られてきました。
銀行に行って口座振替にしたい旨を伝えると、納付書が届いている分はいま支払いを行い、次の分から口座振替になるとのこと。
2022年9月から2023年3月までの115,000円を窓口で入金して、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼(以下略)」に必要事項を記入し提出。
次回からは2年分の381,530円が自動で引き落としされます。毎月納付するよりも15,790円割引されるそうです。わーい
iDeCo・国民年金基金の検討
わたしは35才独身なので、老後のために少しでも貯えをと思い会社員時代からiDeCoに加入していました。そのためiDeCoは新規加入ではなく変更のみ、追加で国民年金基金に加入するかを検討しました。
結論としては、国民年金基金への加入は見送り、iDeCoの掛金を増やすだけに。
というのも、会社員時代のiDeCoの掛金は23,000円が上限でしたが、フリーランスや個人事業主の場合は上限68,000円。それに加えて国民年金基金にも加入するとなると、掛金が数倍になります。
事業収支の見込みがまだ立たないので、一旦iDeCoの掛金の増額だけして、数年後に改めて検討することにしました。
手続きに必要なもの
加入者被保険者種別変更届
手続きの流れ
証券会社の案内によると手続きには1.5か月程度かかるそうで、退職前の2022年7月に証券会社のWEBサイトで書類の請求をしました。数日後に、変更届とその他の必要書類などの説明が送られてきます。
わたしの場合は「被保険者種別」「毎月の掛金額」を変更するので、次の通り記入しました。
第2号被保険者から第1号被保険者になった
変更年月日は退職日の翌日
毎月の掛金額を変更
掛金を毎月定額で納付
7月中旬に書類を提出して、掛金が変更されたのは10月1日分からでした。
地方税・国税の口座振替
会社員ではなくなると税金を自分で支払う必要があるということで、脱税が怖すぎるわたしは、口座振替の方法を調べまくりました。それ以前に、地方税と国税の違いすら理解していなかったので、まずはそこから。
地方税:住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税など
国税:所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税、たばこ税、自動車重量税など
とりあえず、住民税と所得税ってことでいいかな…
調べたところ、住民税は年4回(6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日)の支払いらしく、そのタイミングになって納税通知書が届いてから口座振替の手続きを行うことに。一旦保留。
国税は、かつて確定申告でe-Taxを利用したことがあったので、e-Taxのマイページから「ダイレクト納付利用届出書」を提出しました。所得税の納付は、確定申告後ですね。個人事業主としての初めての確定申告については、終わったらまたnoteにまとめようかなと思います。
文字にまとめるとややこしい印象を受けますが、実際は役所や銀行、オンラインで案内に従って手続きをするだけ。わたしがやることはその日のうちに終わって待つだけだし、わからないことは教えてくれるので、戸惑うことはありませんでした。
一番時間がかかって不安だったのが、失業手当・再就職手当の受給。無事終わった今はほっとしていますが、これはほかの手続きと一緒に書くには重すぎるので、また別の記事で綴らせていただきます。
これから独立しようとしている人の、手続きへの不安が少しでも軽くなりますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
