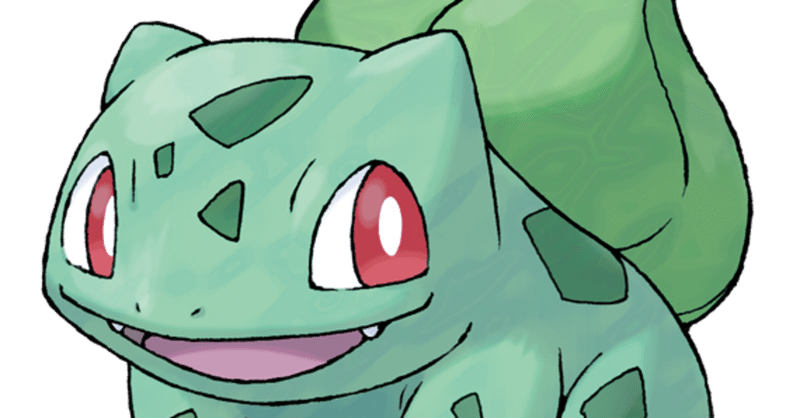
常識合格法① 情報収集について
お久しぶりです!ダネ不死です!
令和2年論文式試験が終わりました。応援してくださった方、ありがとうございました。
けっこう前にリリースした、有料NOTEですが、意外と購入してくださる方がたくさんいて嬉しい限りです。
「第2弾を出してください」って何人かに声をかけて頂いたのですが、とりあえず合格発表があるまでに、その草稿的な位置づけとして、無料NOTEをちらほら書いていきたいと思います。
なお、話を進めるにあたっては、論文の勉強を前提としています。短答生にも通じるものはあると思いますがご了承ください。甘えを赦さないスパルタ式でいきます💪
早速、行きましょう!
僕は「公認会計士試験=高度な情報戦」だと解釈しています。僕自身がクレアールというシェア率が低い予備校に所属している以上、主体的に情報を集めないと一発合格など夢のまた夢だった、という一身上の都合はありましたが、あながち間違いではない等式だと思います。
ですが僕の目から見ると、全員がそうというわけではないですが、多くの公認会計士受験生は脳死で予備校を信じ、主体的に情報を集める努力を怠っているように思えてならないのです。
そりゃ、大原やTACといった大手の予備校生なら、答練で出た問題をできるようにしておけば、相対試験ですから、大幅にコケるということはないわけです。ただ、僕から言わせてもらえば「非常にもったいない!」
他者と同じことをしていては、他者を大きく出し抜けないからです。
そこで、僕なりの情報収集についての考え方やテクニックを披露したいと思います。
①とりあえず試験に有益そうなネット記事全部読め
②過去問は答練よりも重要な資産!
③自校の情報だけじゃ甘すぎる。複数の予備校の動向をつかめ!
①とりあえず試験に有益そうなネット記事全部読め
初歩の初歩からいきます。とりあえず「公認会計士試験 勉強法」「公認会計士 短期合格」とかでググりまくったり、CPAの各科目のエース講師たち(いけべ わたなべ まつもと ながた たかのetc)のTwitterフォローして試験の本質情報を掴んでください。
まさかいないとは思いますが、朝比奈さんとかロディさんのブログ知らない、とかいう人は今すぐぶん殴ります💪ブログが有用か否かはおいといて、ネット検索してない証拠です。無料で手に入る情報があるのに、存在すら知らないのは機会損失です。
オススメのブログとかは、ここには書きませんが、とりあえず膨大な情報のシャワーを浴びた上で、いろんな人たちの主張の共通項、すなわち試験の本質が少しは見えてくるはずです。
②過去問は答練よりも重要な資産!
えてして大手予備校生は答練を崇めすぎです。逆に過去問は軽視されている気がします。
結局、根本にあるものは過去問なんです。いわばカルピスの原液。
予備校の答練は過去問を薄めたり、予備校の傲慢と偏見という名の汁を混ぜたオリジナルジュース。
試験委員はどういう人を受からせたいのでしょうか?予備校の言いなりになってカリキュラム消化した人か、それとも主体的に情報を集め、過去の試験委員が作った過去の問題をリスペクトし出題傾向に沿った勉強をした人か。僕は後者だと思います。
例えば、令和2年の論文式試験の会計学の計算問題に関しては
第1問前半パート 部門別計算
第3問前半パート 個別CF計算書(間接法)
が過去問の類題でした。
これらは過去問を手に入れて分析し過去問の傾向を意識して演習してれば、完答もしくは完答に近い精度で解答できたはずです。
第2問が初見要素強くて難しかったり、第3問後半パートで短答論点かと思われていたソフトウェアがガッツリ出たりとイレギュラーな出題はありましたが、セオリー通り過去問の傾向を掴んで、勉強していればトータルでは他者を出し抜けたはずです。
大手予備校は、ひたすら連キャやら、在外連キャやらを模試などで出してきますが、論文本試験ではそれぞれ1回ずつしか出たことがありません。
僕は、そういう答練・模試では頻出だけど本試でほぼ出ない論点を、予備校特有チンカス論点と呼んでいます。管理のLPモデルとかも典型的な、予備校特有チンカス論点ですね。そんなのに時間使っちゃだめです。
一方、個キャ(間接法)は本試験の第3問において直近で、2,3年に1回のペースで出ており、周期的に今年熱いと踏んでました。予想通り出ましたね。
所詮、答練はフィクションです。予備校からすれば当たったら「多数の的中実績💮」として掲げられますし、外れたら試験委員のせいにすればいいから気が楽でしょうね。そもそも大原やTACにしては、10回を超える数の答練を出して、的中もクソもないだろとは思いますが。
連キャ、在外連キャを保険論点と位置付けず、脳死で答練を復習していた人は、明らかにオーバーワークです。出ないであろうけど、みんなが押さえているから、死なない程度に保険で回すくらいでいいのです
企業法については、新試験制度以降の全ての過去問+αを収録したクレアールの過去問題集を手元に置き、出題傾向を把握していました。大問2-1以外は割と過去問ゲーだった気がします。
科目によりますが、会計学、企業法は割と過去問ゲーだと思います。
租税法、経営学、監査論は、過去問の重要度はそこまで高くないと思ってますが、参考にする価値はあると思います。
③自校の情報だけじゃ甘すぎる。複数の予備校の動向をつかめ!
科目によりますが、大原、TAC、CPAの動向について情報を収集することは有益です。3校でシェア9割くらいあるでしょうから、相対試験である論文式試験で他者を出し抜くには、3校の動向を掴むことは有益です。
まず3校の論文模試は全部受けましょう。僕が公認会計士受験生の親だったら、ぶん殴ってでも受けさせます。社会人で時間が合わなくて受けれなくても、取り寄せてください。僕は2020年に大原全2回、TAC全3回、CPA全2回、全て受験し提出しました。
1回平均7000円くらいかかりますが、一発で受かるなら安いものです。落ちたら30万円くらい予備校に再課金ですからね。一発で合格したかったら、課金を渋るな!ですよ。凡人が課金をケチったら、勝つ要素1ミリもありません。
模試を受けまくった個人的な感想としては、会計学第3問の個キャ(間接法、)第4問の有価証券、監査論の公認会計士法などは大原模試でやったことが本試験に活きたと実感しています。大原模試は質が高い!仮に模試を受験せず、その恩恵を受けれなかったらと考えると、金玉が縮こまる思いです。
模試は予備校が気合い入れて作っているし、出た論点の典型度は高まるので、押さえておくべきなんです。全部を復習する必要は無いですが、要衝は押さえましょう。
後は大手3校の答練の動向ですね。こればかりは別途購入しない限り、自分で解いたりすることは無いわけです。
大原やTACは直前期に受けた模試の特典で出題論点リストを配ってくれました。Twitterで、各予備校の人に教えてもらうとかでも良いですけどね。
CPAなんかは、単科を取っていたりして受講生サイトにログインできるのであれば、本科生でなくても、答練の講評とか優秀答案等が閲覧できるので、出題論点の把握は無料でできます。
特に企業法の他校の動向把握は大事です。問題数が少なくリスクが高い科目なので。僕は、前述した新試験以降の全ての過去問に加えて、大原、TAC、CPA答練出題論点はすべて把握していました。分析した上で、各論点の重要度を決めて回していました。
サイコパス的で狂気染みた情報収集ですが、勝ちたいなら、これくらいやって当たり前です。
僕は、1日10時間勉強することは努力では無いと思います。受からなかったら、ただの自己満足です。1日6時間で落ちた人と何も変わりません。
努力とは、「情報を主体的に集めまくり、いかにすれば楽に成果が出せるか仮説を立てて、実践していくこと」だと思います。
以上、好き放題書きましたが、また今度、別のトピックで書きたいと思います。
バイニャラ🤚
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
