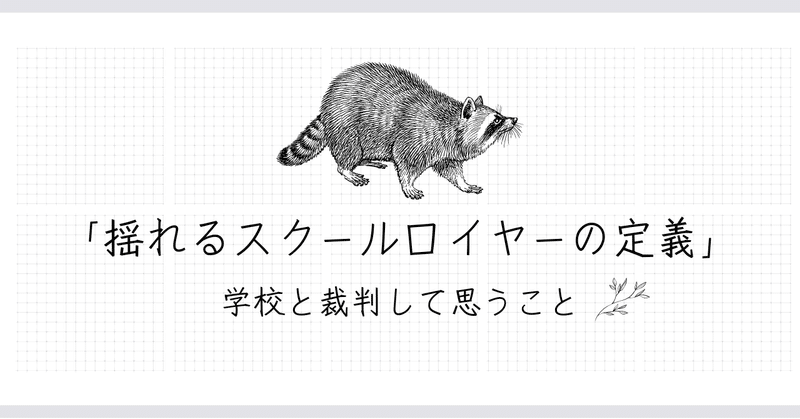
揺れるスクールロイヤーの定義【学校と裁判して思うこと】
法曹資格を持つ教師として有名な神内聡さんの書かれたとてもわかりやすい記事がYAHOOに掲載されています。
2024年3月に日弁連が公表したスクールロイヤーに関する新たな意見書(https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2024/240314_2.pdf)の問題点などを解説したのもので、
2024年意見書で”スクールロイヤーを「専ら教育行政に関与する弁護士」と定義”したことを受けて、”学校教育法は公立学校だけでなく私立も国立も含めた、全ての学校を対象とした「学校運営」に関する法律であって、そもそも「教育行政」に関する法律ではない”ことから、学校教育法施行規則上に位置付けるべきであるとの意見は誤りであることを指摘されています。
(学校・教育委員会の)助言・アドバイザー業務又は代理・保護者との面談への同席等の業務を担う専ら教育行政に関与する 弁護士(以下、本意見書において「スクールロイヤー」という。)をスクール カウンセラー及びスクールソーシャルワーカーと並んで、学校教育法施行規則上に位置付けるべきである。
上記の例をふくめ”知識不足と議論不足”な点を指摘されている現行定義上のスクールロイヤーに”代理人として保護者対応を委ねること”について、実際に弁護士の先生を代理人として依頼しながら学校に在籍してすごした子どもの保護者として、お話ししたいと思います。
※現在係争中のため、事実関係などにつき、あいまいな表現をとらせていただいております。(判決後、加筆修正する予定です。)
保護者対応を代理人に任せると、現場の先生は楽になるのか
我が家の場合、学校が窓口を代理人に依頼したのち協議や説明の場が持たれることもなく、在学中にやむなく訴訟提起をして現在訴訟係属中です。
(この間、私たち保護者側が、しつこく電話したとか面会を求めたとか学校に押しかけたとか、いわゆる世間一般に対応困難だと感じられるような言動をした事実はありません。)
弁護士が「代理人業務」を担い保護者等との交渉の窓口とな る場合であっても、現に当該保護者の子どもが在籍している場合には、 授業や進路相談その他学校における学校と保護者との日常的なコミュ ニケーションも必然的に発生する。
意見書でも上記引用のように述べられているとおり、保護者対応をシャットアウトしたところで、その子どもは学校に行って毎日先生と顔を合わせることになります。当然のことながら日々の細々とした事務連絡や調整が必要です。
これらの日常的なコミュニケーションまでスクールロイヤーが行うのか?について、意見書では、「保護者との間で争いとなっている点については弁護士が窓口となり、その他の日常的な対応については、引き続き保護者と学校で直接やりとり をするように対応を切り分けること」を想定しています。
結局、日々の連絡はこれまで通り現場の先生と子ども(保護者)で行うことになるのです。
個々の事案について保護者と学校どちらが理不尽なのか、ここではおくとして、そもそも対応困難だと学校が判断している保護者だからスクールロイヤーが代理人として出てきているのに、その保護者と円満に日常の連絡のみやり取りすることが果たして可能でしょうか?
また、多くの場合、保護者と学校が対立する原因には何かしらの学校生活上のトラブルがあったはずです。子どもが毎日学校で生活している以上、そのトラブルと日々の生活は地続きでどこからどこまでと簡単に切り離せるものではないでしょう。
わが家のケースについていえば、学校内での日常のすべてが争いになっている点と関係しているとも言える状況でした。
根本に存在しているトラブルの解決自体は棚上げした状態で、
これはトラブルに関係しているからスクールロイヤーへ、これは日常の連絡だから担任教員へ、とやり取りの度に判断するのは大変な作業だと想像します。
その判断は誰がするのでしょうか。
普段から学校に常駐しているスクールロイヤーならいざ知らず、トラブルになった際に急に現れた外部の弁護士と頻繁に相談しながら日常業務をこなすことが果たして本当に可能でしょうか。
例えば、わが家では学校と連絡をとる必要が生じた場合、
子ども本人→子ども側代理人弁護士→学校側代理人弁護士→学校(逆へループ)と伝言を繰り返しており、毎度発生するタイムラグも悩みの種でした。多分学校の先生たちも大変だったと思います。
「専ら教育行政に関与する弁護士」は現場の先生の味方なのか
連絡係になっていた教頭先生と学校代理人弁護士がどのような関係だったのかはわかりませんが、学校内の連携がうまくいっていないのだろうなと感じる出来事は在学中に何度も繰り返されていました。
まず、学校代理人弁護士と話した内容をふまえて、教頭先生と日常生活のお話をしようとしたところ、教頭先生は学校代理人の話は私たち(現場)は一切知らないと言うのです。
これでは、子どもが何に困っているのか、何を訴えているのか現場の先生は何の情報もないまま子どもと接していることになります。子どもの側の精神的な負担は言うまでもなく、子どもの状態を知らずに指導を続けることは学校で現場対応にあたる先生にとっても不適切な対応につながる可能性があり、業務上のリスクがあるのではと思います。
大切なのは「子どもの最善の利益」
この意見書では、代理人となる弁護士において留意すべき点として以下もあげられています。
「子どもの最善の利益」への配慮
まず、弁護士が代理人としての保護者等と直接やり取りをする活動 についても、子どもの最善の利益につながるのかどうかを念頭に置き ながら、当該保護者の子ども(本人)及び本人以外の子どもへの影響 や学校全体への影響等も総合的に勘案して対応するなど、手引きや2 018年意見書の趣旨を踏まえた運用をすることが必要だと考える。 特に、代理人業務を担うに当たっては、現に当該保護者の子どもが在籍しているにもかかわらずその子どもへの支援を念頭に置かない対応 をしたり、子ども(本人)を不当に傷つけるような主張をしたりしないように注意する必要がある。
現状想定されている形でのスクールロイヤーの活用は、果たして本当に現場の先生を救うことになるのでしょうか。
そればかりか、当事者である子どもにさらなる負担を強いるものではないでしょうか。
教職員の先生方にも保護者にも、この件について考えてみてもらいたく、記事の紹介をさせていただきます。
もちろん理不尽な要求を執拗に繰り返す保護者、高圧的で乱暴な言動をとる保護者には毅然とした対応が必要で、教職員の先生方がいたずらに傷つけられることはあってはならないことです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
