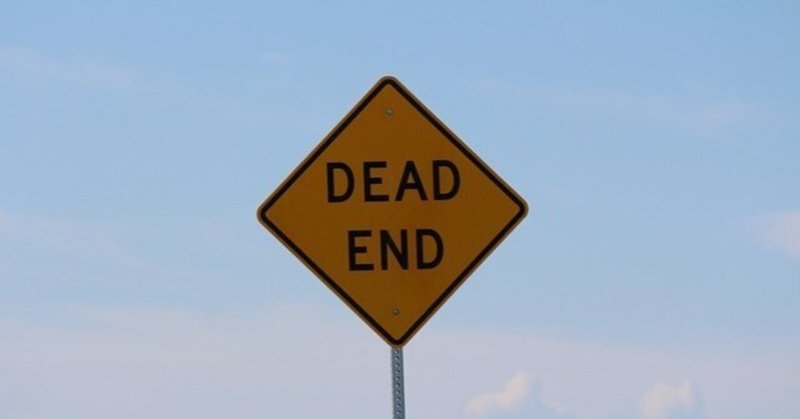
親が決めた中学受験はNG〜その受験、ホントに子どものためになる?
こんにちは。
元大手進学塾トップクラス担当講師で、現在はニュージーランド在住の受験&国際教育コンサルタントのTakuです。
中学受験を始めるきっかけが、
子供にいい環境を与えたいという親心であることは、
意外によく起こるものです。
「子供に少しでも楽をさせたい…」
親としてそう考えるのはよく分かりますが、
それが逆に子供を不幸にしてしまうケースもあるのを、
あなたは理解できているでしょうか。
そこで今日は「中学受験を親が始めるリスク」について、
一緒に考えてみたいと思います。
燃え尽き症候群のリスク
親が中学受験を始める時、
多くの子ども達は中学受験が何たるか、
よく分かってないのが常です。
施設が綺麗な学校に行けるとか、
入った後ゆっくりできるくらいの知識で、
よくわからないままスタートする。
スタート時期が早ければ早いほど、
子どもは親がいいと言ったからやる程度の、
ゆるい意識しかないものです。
そして低学年のうちは塾の回数も少なく、
内容も量もまだハードではないので、
子どもたちもそこまで大変ではないことが多いでしょう。
でも学年が上がるにつれて学習レベルが上がり、
宿題の量も増えてくるので、
徐々にストレスが大きくなります。
そもそも自分で始めたものではないので、
どうしてこんなに辛いことをしなければいけないか、
理解していないままで勉強を続けていく。
そして徐々に受験の合格のためだからと、
好きなことや習い事も諦めさせられ、
気がつけば勉強漬けの生活が始まります。
あけれもくれても終わらない大量の宿題。
終わりが見えない大量の知識の暗記。
それでもとにかく「合格」すれば解放されると、
それだけを心の支えにがむしゃらに、
受験勉強を続けていく。
それが親が始めた子供たちの受験学習の、
よくあるパターンだと思います。
こんな学習を長く続けた子どもが、
受験が終わった時に感じる感情はなんでしょう。
それは歓喜ではなくきっと、
深い深い安堵ではないでしょうか。
そして受験から解放された彼らが望むのは、
未来に向けた学習ではなくむしろ、
勉強をしない時間の確保でしょう。
こう考えると受験後に彼らが、
学習意欲を喪失して燃え尽き症候群になるのも、
無理はないと理解できるのではないでしょうか。
話が違う
にもかかわらず彼らのそんな願いは、
合格後にすぐ裏切られます。
まずのんびりするはずの春休みには、
「中学準備」のためにまた塾に行って、
先取り授業に参加するかもしれません。
また私立中学に入学するや初日から、
「大学受験に向かってしっかり勉強するように」と、
先生から檄が飛ぶこともあるでしょう。
多くの中高一貫校は大学進学実績向上のため、
公立よりもペースの早い先取り学習をするので、
それについていけるような勉強も必要になります。
私立中学に合格さえすれば、
楽な生活が送れると言われていたのに、
楽になるどころかむしろもっと忙しくなった。
「話しが違う!」
私立に行き始めてそう思う生徒は、
実際決して少なくないはずです。
でもこれは親からすれば受験を始める前から、
冷静に考えればわかることです。
また情報収集さえすれば、
こうした事態は回避することもできるでしょう。
にもかかわらずそうしない親がいるのは、
面倒見のいい私立に入れた方が手がかからず、
「楽で安心だから」ではないでしょうか。
確かに公立中に行かせれば、
様々な生徒がいるのでどんな影響があるかわからず、
その上高校受験もあって親としては不安でしょう。
でも親の安心を優先することで、
子どもが必ずしも幸せになるとは限りません。
以下の記事にもその例が書かれていますが、
私自身の経験の中でもこうしたケースは、
過去にいくらでも例を挙げることができます。
失われる思考力と行動力
このような悪いパターンに陥った生徒は、
学校を退学したり不登校になるか、
思考をやめて黙々と従うかのどちらかになります。
もちろん退学や不登校になれば親は大変ですが、
彼らはまだ自分から意思を示して行動し、
次のチャンスを探すことはできます。
一方でそうした状況に対して抗うのを諦めて、
思考を停止して黙々と従うようになるのは、
親が考える以上に深刻な事態だと思っています。
一見するとこうした子どもは一生懸命、
学校の勉強をしているように見えるでしょう。
それを見て親も「頑張っているな」と、
ほっと胸を撫で下ろすかもしれません。
でもこうしたケースで子どもたちは、
自発的に頑張っているのではなく、
ただ目の前のノルマをこなしているだけのことが多いのです。
とにかく何も考えないで、
とりあえず親や先生がやれと言ったものに、
ただ従っているだけになっているだけ。
こんなことを続けていけば、
子ども自身が自分の頭で考えて行動する、
思考力や行動力が育つはずがありません。
その先に待っているものは、
これからの時代に必要なスキルとは正反対の、
受動的な姿勢の人材ではないでしょうか。
まとめ
さていかがだったでしょうか。
こんな例は特別でオーバーすぎると、
一笑に付すのは簡単でしょう。
でもそのレアケースに我が子が当たらないと、
一体何人が断言できるでしょうか。
実際にこうしたパターンに陥った親の誰が、
我が子がそうなると予想していたことでしょう。
私たち親は往々にして自分たちこそが、
正しいと過信するきらいがあります。
親もまた人間なので、当然間違えます。
だからこそしっかりと知恵をつけつつも、
自分も間違っているかもしれないという、
謙虚な態度で子供と接していきたいものですね。
【音声配信やってます】
スタンドFMで音声配信もやってます!
よかったらそっちも聞きに来て下さい。
【質問募集中】
受験や留学、海外育や子育てについて、こんなことを聞いてみたい!という質問を募集します!
ご質問は下記リンクからお気軽にどうぞ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
