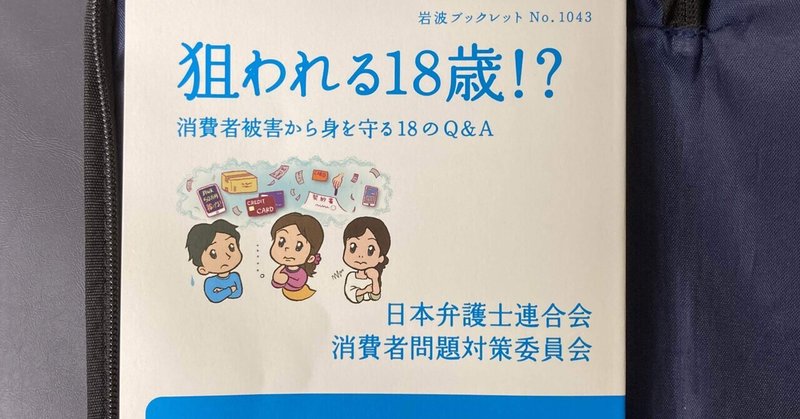
【狙われる18歳!? 消費者被害から身を守る18のQ&A】未成年者取消権が大きな問題
オススメ度(最大☆5つ)
☆☆☆
〜"民法における"成年年齢の引き下げ〜
2022年の4月1日より民法が改正され、成年年齢が18歳に引き下げられた。
まぁ、一般的には成人になるのが「2年早くなった」ぐらいの感覚なのだが、"民法における"成年年齢が2年引き下げられることによる影響はどういうものなのか?
選挙権は2015年に既に18歳に引き下げられていた。別にお酒やタバコは18歳からOKになつてるわけではない。
民法上の成年年齢というのはいったいどういうものなのか?
それにハッキリと答えられるわけではないので、本書でキチンと理解しておこうと思った次第である。
〜強力な未成年者取消権〜
本書において1番問題視されているのが「未成年者取消権」に関する話である。
未成年者取消権は「後戻りのための黄金の橋」「消費者被害の特効薬」「鉄壁の防波堤」「消費者被害の予防薬」と言われ、消費者被害の救済や予防のために強力に働く制度である。
通常、「契約」を一度結ぶと、それを取り消すためには多くの立証と手続きが必要となる。どれだけ自分にとって不利な内容であったとしても、一度結んだ契約の取り消しはかなり困難である。
しかし、「未成年者取消権」を行使すると、契約締結時に未成年であったと証明するだけで、契約を取り消すことができる。そして、その証明は非常に簡単なのである。
この制度は、未成年者を悪徳業者から守る予防線として大いに役にたつ。そもそも、未成年が親の同意なしに契約を締結しても、未成年者だからという理由だけで簡単に契約を取り消してきるのだから、悪徳業者はそもそも未成年者と契約しようとはしないのだ。
民法上の成年年齢引き下げはここに大きく影響する。これまで、悪徳な契約から守られる年齢が20歳までから18歳までに引き下げられたと言える。
18歳と言えば、実際にはまだ高校3年生だ。体感として、大学や社会人になって1年ほど経つ20歳と高校3年生では、体感として全く違う。
自分を思い返してみても、20歳の時と比べて、学校しか知らない高校生の時に同じような判断が出来るとは到底思えない。
民法で守られる年齢が引き下げられた、という観点で見ると、たしかに成年年齢の引き下げは大きな問題だと感じてしまう。
〜そもそも何で成年年齢を引き下げた?〜
じゃあ、そもそもなんで成年年齢を引き下げる必要があったのだろうか?
本書は「成年年齢引き下げ」に対して反対の立場をとっているため、ここからはそのメリットのようなものがあまりわからない。
本書の中では、引き下げるべきという意見として「少子高齢化を迎えるにあたり、若者の大人としての自覚を高めるため」「選挙権年齢と統一したほうが良いため」「諸外国の成年年齢と合わせるため」(イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、カナダなどは成年年齢が18歳)などが挙げられているが、いずれも本書では「説得力に欠ける」と否定している。
成年年齢引き下げに肯定的な人の文章を読んで、それに対するメリットを是非聞いてみたい。
どちらにせよ、子を持つ親の立場としては、18歳が消費者被害にあう危険がある、という現実にはしっかりと目を向けていたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
