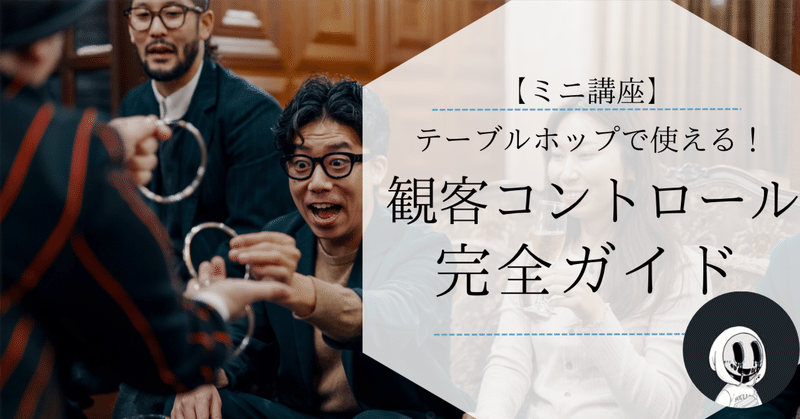
【ミニ講座】テーブルホップで『タネ見破りバトル』になっていた僕の悩みが綺麗さっぱりなくなった方法を全部話す。
今回は【ミニ講座】と題して、
ぼくがテーブルホップで実際に使っているテクニックや考え方を紹介していきます。
突然ですが、こんな悩みを持っていませんか?
・観客が全力でタネを見破りにきてしまう
・マジシャンを困らせようとしてくる
・勝手に物を触ってくる
ぼくも昔はそうでした。
そんな悩みは誰もが通過するもはや"儀式"みたいなものです。笑
でも安心してください!
その悩みは、一生続くものではありません!
この記事を読んで、
現場での"観客コントロール力"を身につけてください。
①間違った解決策
「タネ見破りバトルになってしまう・・・」
その解決策として、
多くのマジシャンは『観客の思考をタネから逸らす』ことを考えがち。
でもこれって実はめちゃくちゃもったいない!
「分からない」ことはマジックの魅力の1つ。
そしてこの「分からない」という感想は、タネを思考したり探ったりしないと生まれない。
つまりタネから思考を逸らすというのは、観客から“マジックの楽しさ”を一つ奪っているのと同じ。
というかそもそも人間は不思議なものを見たら、その原因を探りたくなる生き物。
タネへの思考は無くしようがないし、そのメリットもあまりない。
ではどうすればいいのか?
↓
②本当の原因と対策
“タネ見破りバトル”になってしまうマジシャンに本当に足りないのは以下の2つ。
・「タネがわからない」という事に対する解像度
・パフォーマーとしての信頼度
・観客の自由を制限するスキル
1、「タネがわからない」という事の解像度
多くのマジシャンはここでつまづく時期が来るイメージがある。僕もそうだった。
「消えた」と「消えたように見える」の違いをハッキリさせるのが大事。
前者は「手品」であってタネがわからない
後者は「錯覚」であってタネの想像ができる
ここの解像度が低いと、マジックと称して錯覚を見せることになる。
それによって観客は「コイツのマジックなら見破れそうだぞ」と考え、それが“バトル”を加速させる原因になる。
だからまずは『手品』と『錯覚』の違いをわかるように訓練しよう。
ちなみに『錯覚』のも2種類ある。
・タネがわかる錯覚
・なんとなくそれっぽいタネが想像できる錯覚
わかりやすくするために、いくつか例を挙げる。
タネがわかる錯覚
・リテンションバニッシュ
→ いくら「消えました」と言い張っても、観客は反対の手を疑っている。
リテンションバニッシュは"技法"であって現象ではない。
他の技法と掛け合わせることで、初めてマジックになる。
・オムニデック。
→ 確かにウケるが、観客が「いつすり替えたの?!」と言った時点で"すり替えた"という事実はバレている。
そうなるともう「透明になった」ことにはならない。
なんとなくそれっぽいタネが想像できる錯覚
こちらは、「雰囲気出来そうなタネ」が想像できるマジックのこと。
必ずしもそれが正解でなくても、観客は「分かった」と思ってしまう。
そしてこれの原因として、"演じ方"に問題がある場合が多い。
「観客がどんなタネを想像するのか?」これを客観的に想像できる目を作ろう。
さて、「分からない」ことの重要性はわかってもらえたと思う。
とはいえ
「面白いタイプの『分からない』」と「つまらないタイプの『分からない』」があるから注意が必要。
『分からない』ことが観客にとっての楽しみになっている最大の理由は、『思考を働かせている』から。
逆にいうと、思考が働かなければいくらタネが分からなくても面白みがない。
そこで大事になってくるのが、『考える余地』の存在。
わかりやすく言うと、最強なのは"隠れていること"。
「ハンカチの中で何が起きたんだろう?」
「この怪しい箱の中はどうなっているんだろう?」
のように、考える余地を作ることが観客の楽しみを作る。
逆にあまりにもビジュアルな現象は、
「考えてもどうせ分からない」と、最初から考える気を失せさせてしまう。
ただ面白いのは、
映像越しになると立場が逆転するということ。
まぁこれは本題と逸れるので、またの機会に話すとする。
2、パフォーマーとしての信頼度
こちらは難易度が高い。
それでも最低限押さえておきたいポイント。
観客の行動には必ず理由がある。
ということは“バトル”になるのにも理由がある。
その理由とは、
・“バトル”にした方が盛り上がりそう
・見破ってマジシャンをいじめた方が面白そう
など様々ある。
共通して言えるのは、『完全に任せるほどマジシャンが信頼されてない』ということ。
つまりは「コイツに任せるより自分が手を加えた方が面白くなる」と思われている。
これを防ぐには……?
「現象でねじ伏せる」……?
それでは敵になって“バトル”が終わらない。
大事なのは、
・見切れた瞬間
・所作
・言葉遣い
・発声
など、人として&パフォーマーとして『信頼できる人間』の立ち振る舞いをすること。
わかりやすい例としては、
めちゃくちゃ強面のマジシャン がいたらどうだろう?
マジックの邪魔をするだろうか?
茶化すだろうか?
たぶんできない。
めちゃくちゃ高級感のある紳士的なマジシャンもそう。
めちゃくちゃミステリアスで、マジック自体に期待できるマジシャンもそう。
「邪魔すると損する」という思考を観客の中で作れるかもひとつの鍵になる。
3、観客の自由を制限するスキル
平たくいえば「支配力」だ。
これは勝手のものを触られたり、指示していない行動をしたりするのを防ぐことに使える。
先ほど説明した「信頼度」も一つの支配力。
ただそれ以外にもたくさんある。
具体的にいくつか例を挙げる。
・『目線』と『フォーカス』のコントロール
簡単にいえば、マジックにガチガチに集中させることで「いじわる」そのものに意識がいかないようにするということ。
またここが確実にできていれば、マジックが観客に深か刺さる。
つまりマジシャンとしての信頼度もあげることができて、演じるほどに支配力が強まっていく。
詳しくはこちらの記事で解説しているから見て欲しい↓
・テーブルを空けてもらう
テーブルに入った時にマジックするためのスペースを確保するのは誰しもがやることだろう。
ぼくはこれを観客にやってもらう。
その理由は二つ。
・マジシャンの手で食事を触ると言う衛生面の問題を避けるため
・観客が"自ら"マジシャンを受け入れたという事実を作るため
一つ目は言わずもがなわかると思う。
大事なのは二つ目。
人間は常に「一貫性」を保とうとする生き物。
観客に自らスペースを開けてもらうことで、「マジシャンがマジックをするためにスペースを空けるのを手伝った」という事実を作る。
すると観客の中に、「マジシャンに協力する自分」という自己イメージを形成することができる。
一貫性に従って動く観客が、マジシャンの邪魔をすることは基本的にない。
これでマジシャンの周囲(少なくとも左右)の観客は味方にすることができた。
しかし唯一マジシャン側が触るものがある。
それは「グラス」。
これを置く場所は、"遠くの観客から手が伸びてきたときに、手がグラスに当たって倒れそうな場所"。
これによって、「ギリては届くけどスペースを空ける手伝いはしていない観客」の自由もコントロールすることができた。
『衛生面は大丈夫なのか?』
→大丈夫。グラスは上の方しか口をつけない。底に近い部分を持つことに嫌悪感を抱く観客はまずいない。
・相手にしない
心が痛むが、それでも自由に振る舞ってしまう観客は相手にしないことだ。
そういう観客のほとんどはかまってちゃん。
それでもさすがに場の空気を悪くしたくて絡んでくる観客はいない。
相手にしないことで、かまってくれない人になると同時に「これ以上絡むと変な空気になるで」と暗にに伝えてみよう。
大概は大人しくなる。
さて、ここまでがテーブルホップで、
・観客が全力でタネを見破りにきてしまう
・マジシャンを困らせようとしてくる
・勝手に物を触ってくる
に対する有効的な対策でした。
よくこの“バトル問題”の解決策として「演出にこだわろう」みたいなものを聞くが、それ以前にたっぷりと改善点があることがほとんど。
演出や構成面はエンタメとしてのクオリティを上げるためには必要だが、“バトル問題”の解決には
・演者自身のマジックに対する解像度のアップ
・信頼されるための人間面の改善
・場の支配力を高める
この3つがダントツで大きい。
逆にここがちゃんとしていれば、演出や構成を考えずにそのまんまの状態でマジックを演じても、十分いい空気感のパフォーマンスが出来るようになる!
やってみそ。
「良い記事だった!」と感じましたら、Twitterの方で感想をシェア&僕のアカウントのタグ付けをして下さいませ。
ランダムにリツイートします!
↓ ↓ ↓
TAKKi@マジシャンの"裏"参考書
なお、他にもマジックを"演じること"に関する知識が知りたい方は、
他の記事もどうぞ!
✅オススメ記事 ↓↓
キッズショー経験300回以上、文化庁ワークショップ講師200件以上
の僕がたどり着いた、
・キッズショーの作り方
・マジック教室の作り方と教え方
の関する記事です!
無料部分だけでも十分役に立つ内容ですので、
「今のままでいいのだろうか・・・?」と思っている方は、
今後の活動の参考にしてみてください。
まとめてお得に購入できるマガジンもあります!
応援してくれる人は"あえて"別々に買ってください。笑
それではまたお会いしましょう!
TAKKi
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
