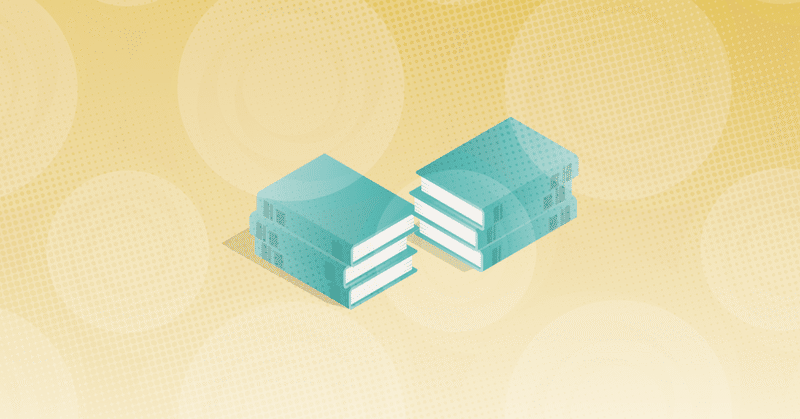
論文紹介 軍隊は次世代のリーダーに学ぶ時間を保証しなければならない
アメリカ陸軍の元軍人ロバート・スケール(Robert H. Sclae)は、アメリカ軍の将来に対して深い懸念を示す論説「学ぶには忙しすぎる(Too Busy to Learn)」(2010)を発表し、アメリカ軍の人事制度の問題を指摘したことがあります。
その問題とは士官の教育ですが、より根本的な問題は学習に割り当てることができる時間の乏しさです。2001年にアメリカはテロとの戦いを本格化させ、多数の兵士がアフガニスタンやイラクなどに派遣されましたが、派遣が長期化するにつれて、部隊の活動が忙しくなり、次世代を担う若手の士官を育てる余裕がなくなってきました。
Scales, Robert H. (2010). Too Busy to Learn, U.S. Naval
Institute Proceedings. Vol. 136/2/1284. https://www.usni.org/magazines/proceedings/2010/february/too-busy-learn
著者はますます多くの軍人が自らのキャリアを形成する上で実戦の経験を重視するようになっていることを指摘し、学業を蔑ろにするようになっていることに対して懸念を表明しました。
「不穏な証拠がある。すべての軍種の士官が学校に出席することを避けており、教育課程の期間は短縮されている。陸軍の幹部学校(staff college)のすべての教育課程に出席する士官はますます減っている。最も優秀な士官はイラク、アフガニスタンで勤務することを優先し、陸軍大学校を避けている。そのため、学生の平均年齢は41歳から45歳に上昇しており、そのため陸軍大学校は戦略的リーダーシップのための基礎を構築する機関というよりも、退職に向けた準備の機関になっている」
もともとアメリカ軍の人事制度では、士官、特に初級士官である尉官は、戦闘の経験を積むことが非常に重視されていました。この経験を獲得すると、軍人としてのキャリア形成、特に昇任と補職で有利な地位に立てるようになります。この傾向が近年ますます強まっており、各部隊の人事担当者は多数の尉官が学校に入れば、部隊の態勢を維持する上で有害だとして、教育課程に送り込むことに反対するようになっています。
著者はこの動きに歯止めをかけるため、尉官が戦術レベルの指揮能力を持つことを勤務で証明すれば、2年間の「兵士のサバティカル(soldier's sabbatical)」を与え、優れた大学院で軍事、行動科学、外国語を学ばせる機会を保証べきだと提案しています。このサバティカルは指揮官としての成功に対する報酬として位置づけ、追加の兵役を要求するべきではないとされています。もし博士号の取得に必要とされる条件を満たす場合があれば、その取得を後押しするべきだとされています。著者は、アメリカ軍の人事担当者はこのような制度に反対することを見越して、連邦議会は立法措置によって士官を増員し、かつ彼らの教育機会を保証するプログラムを制度化すべきとも主張しています。
これ以外にもさまざまな提案を出していますが、いずれも将来を担う世代の教育が後回しになっている状況を変えることを目的としたものです。著者は、イギリス軍が19世紀に第二次産業革命という大きな変化の時期に際して、新たな技術革新に対応して改革を行う必要があったにもかかわらず、世界各地に広がる植民地を防衛する活動で手一杯になっていたことから学ぶべきだと主張しています。当時のイギリス軍の人事評価でも、学校で過ごした時間が長い士官ではなく、前線で勤務した時間が長い士官に有利な設計になっていました。このことはイギリスの組織学習の効率を低下させる要因となり、第一次世界大戦で低いパフォーマンスを示す結果に繋がった可能性があると著者は考えています。
この議論は、軍隊の活動が増加し、業務に対する人員の余剰が減少するにつれて、人的資本が劣化していくことに注意を促すものであると思います。ここでは士官の人事が問題とされていますが、下士官以下の階級でも人的資本の形成と部隊運用の必要の間でバランスをとらなければならないことは同じだと思います。それぞれの部隊の人事担当者の立場で考えれば、任務遂行に必要なマンパワーが不足している中でそれを手放さないようにすることは理解できます。このような現場の事情が積み重なると、組織全体で若手の育成が滞るため、長期的に人的資本の劣化が起きます。これを予防するためには、著者が述べるような教育機会の保証が制度的に必要であり、それを有事の際にも可能な限り維持することが重要になるでしょう。
関連記事
調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。
