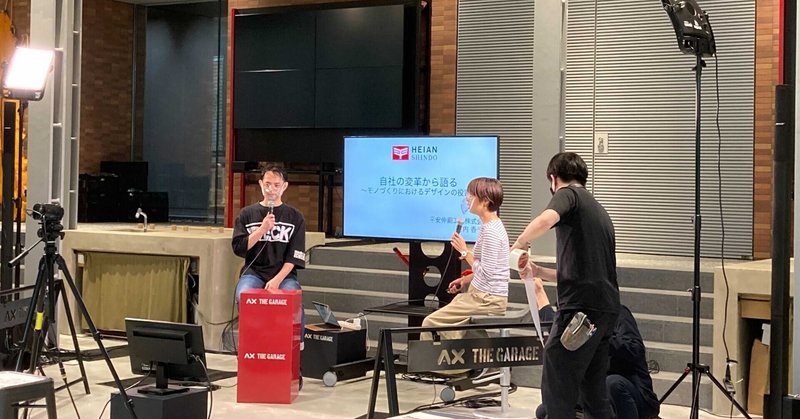
モノづくりにおけるデザインの役割①
こんにちは、つっぱり棒博士の竹内香予子です!
6月25日、近畿大学でセミナー担当させていただきました。タイトルは「自社の変革から語る~モノづくりにおけるデザインの役割~」。
デザインを語るのは1万年早いような気もして、大変恐縮なんですが、自分的には今までやってきたことを整理するのにとても良い機会になりました。
せっかくスライドも作ったので、今回近大で話したことを改めて文字にまとめてみました。解釈間違っていたら、コメント大歓迎!デザインに興味ある方、関わっている方と経験シェアできたらと思っています。
下にアーカイブ動画のリンクも貼りました。ですが、今回テキストではイベントの内容を再編集しているので、セミナーと同じ順序ではありませんのでご了承ください。(より分かりやすくということで変えてみました)
二回にわたって記事化しようと思っているのですが、今回は「デザインって何?」をまとめています。
デザインとはなんや?
デザインのいい商品サービスと聞いて何を思い浮かべますか?
「iPhone」「ダイソンの掃除機」「バルミューダのトースター」などなど。
これからの共有点から、デザインとは「外観を整えること」を指しているのでしょうか?
デザインを辞書で引くと
(1)建築・工業製品・服飾・商業美術などの分野で、実用面などを考慮して造形作品を意匠すること。「都市を―する」「制服を―する」「インテリア―」
(2)図案や模様を考案すること。また、そのもの。「家具に―を施す」「商標を―する」
(3)目的をもって具体的に立案・設計すること。「快適な生活を―する」 (大辞泉より引用)
辞書的に解釈すると「形を描き出すこと」であったり、「案を考える」ことだったりするのかなと思います。なので、デザインにおける「かっこいよさ」は、結果であって、目的ではありません。
私が今日お伝えするデザインとは、大辞泉の⑶の意味に近いような気がします。自分の言葉で整理してみると、こんな感じ。
商品やサービスの『らしさ』を描き出し、ブランド力を生み出す行為。
そして、『らしさ』とは、ユーザー中心にとらえ、あらゆる切り口で製品やサービスから得られる体験の質を高めることで生まれるプラスの影響であり、選ばれる源泉。
経営におけるデザインの重要性
このデザインという、なんともふわっとしたやつなんですが、今の時代、経営において無茶苦茶大切な存在になってると感じています。
その証拠に、経産省も「デザイン経営宣言」っての2018年発表してます。それくらい、重要度が増しているんですよね。
技術だけで差別化するのは難しい時代です。例えば家電なんかは、EMS(製造請負)に頼めば、誰だって作ることができる時代です。そんな技術が陳腐化しやすい時代だからこそ、「ユーザーとメーカーの関係」から、「ファンとブランドの関係」になることで、他社と差別化して競争優位を発揮できると考えられています。
「ファンとブランドの関係」になるためには、ブランドの一貫したコンセプトが必要で、買う前から買った後までそのコンセプトを体現した顧客体験を生む必要があります。
その顧客体験を設計する上で大切なのが「デザイン」です。「目的を持ってモノやコトを設計する=デザインすること」が、経営において重要性が高まっているように感じます。
デザインの構成要素の変化
さらに、経営においてデザインの重要性が高まっている背景に、産業構造の変化が存在します。前出のデザイン経営宣言の第三章「3. 産業とデザインの遷移」でも触れられています。
私が参考にさせていただいたのは、こちらのブログ。
「19世紀はデザインの第1世代、“ビジュアル”がデザインの対象だった。20世紀はデザインの第2世代、“オブジェクト”がデザインの対象だった。1980からはデザインの第3世代が始まった。“インターフェイス”がデザインの対象となり、2000年には“サービス”がデザインの対象となった。そして、今はデザインの第4世代。2010年からは、“ストラクチャー”がデザインの対象となっている。」
出典 Tomoki Hiranoさんのブログより
つまり、これまでモノづくりの世界で「デザイン」の対象としていたのは、「物体」そのものだけ。でも時代は変化して、「らしさ」を作り出すためにデザインが必要な要素は「物体」だけでなく、インターフェイスやサービス、更にはストラクチャーにまで範囲が広がり、それらも含めて一貫性を持ったデザインができていることではじめて「ブランド」として差別化できるのだと理解しました。
つまり、私たちがビジネスをしている時代において、ブランドまで商品やサービスを昇華しようとすると、デザインが求められる対象はかつてに比べ多岐にわたるということなんです。
平安伸銅でおきた変化
そんなデザイン回りの時代の変化。それを踏まえて、自分の仕事を振り返ってみました。私が入社した2010年の平安伸銅は、「価格」と「品質」が強みでした。会社としての一貫したコンセプトやそれを体現した顧客体験をデザインすることは全くなく、むしろコストになるので不要と考えられていました。
過去の実績から突っ張り棒の売り場を抑えていたので、一定数量の売り上げは維持していましたが、「平安伸銅の商品でないとダメ」という理由がなく、いつ競合にシェアを奪われてしまうか分からない状況でした。
この状況に危機感を抱いた私は、夫も巻き込み(2014年に会社に加わってもらう)、改革を進めていきました。
改革のゴールとしてイメージしていたのが「いかに選ばれる存在になるか」。
特に改革推進において夫の貢献はすさまじく、夫なくして今の平安伸銅工業は存在しないと思っています。
結果的にの話なんですが、夫は建築士でデザインが専門でした。建築家への弟子入りやホテルなどのインテリアデザインに携わったこともあり、デザインに対しの造詣が深かったのです。
経産省の「デザイン経営」では、経営の中枢にデザインを理解する人材を配置することを勧めています。振り返ってみると、夫が加わってくれたことにより、「デザイン」を判断できる体制ができたんだと感じています。こうして、何が起こったかというと、2016年にラブリコの発売、2017年にDRAW A LINEの発売、売上も私の入社時とくらべ、倍以上に伸びました。
デザインを取り入れて、どんなことをしたのか?
結構、何でもやったなあと思います。
一つは、「会社自体をデザインすること」。もう一つは、「新しい商品をデザインすること」。こちらに関しては、次回詳しく紹介したいと思います
デザインって何なのか?実は改革推進している渦中は、その重要性を理解していませんでした。でもがむしゃらに取り組んできたこと振り返ってみると、時代の変化と自分たちが取り組んできたことが「デザイン」という文脈で一致していることに気づかされました。
「デザイン」は、工場の設備のように形がありません。なので、予算の限られた中小企業では投資を渋りがちですが、今この時代だからこそ、トップ自らが重要性を認識して、社内に浸透させる行動をとることが必要だと感じています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
