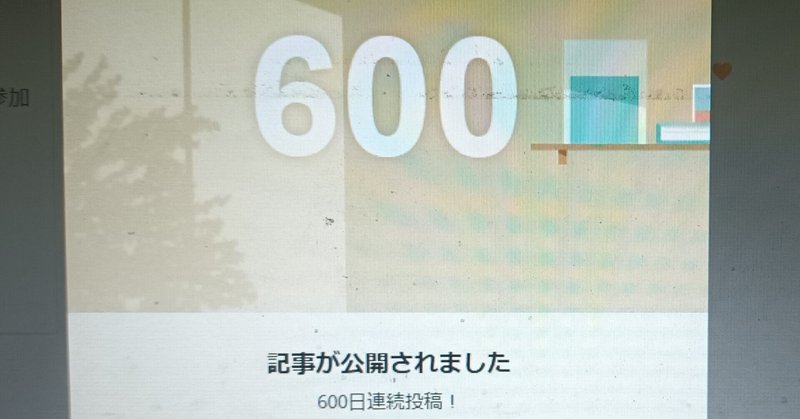
アンラーン💣リラーン📚ためらわん♫run45
⭐表現は相対的、それゆえ人はみな「知の『旅人』、知の『探究人』」さらにその姿に惹かれる「知の『耽美人』」⭐️
(これまでの虚栄を解きほぐす「unlearn」のため、頭の中を刷新する「relearn」を躊躇なく進めるための記録)
さきほど過去の旅を振り返るシリーズの投稿が「200回目」の節目となった
同時に、2021年9月からの連続投稿も「600日」という節目を迎えた
2021年9月からの投稿数は「1181」
1日最低1投稿としながら、実際には複数の記事を投稿する日がほとんどだった
その結果「1181」となっている
見た目でキリが良いわけではなく、節目とも思えない
しかし1181年とすれば日本史的には平清盛が没した年で或る意味で節目かも
さらに数学的には1181は素数なのでこれはこれでキリがいいかも
たくさん記事を書いたのは事実だとしても、それが何か特別なことを意味するわけではない
駄文をいくら集めたところで、それは巨大な無駄でしかないかもしれない
誤った方法で身につけた技術の反復練習は、誤りを肥大化させるだけ
間違ったスイングを繰り返しても、素晴らしいスイングに生まれ変わることはない
だから大切なことは「量」以上に「質」である
ありがたいことに、この「質」について鼻をへし折られる機会をここ数年いただけている
2021年は、オンライン学習サービスを提供する大手企業との業務委託契約で、探究講座のワークブック制作に参加させていただいた
そこでいろんな方から自分の表現物についてご指摘をいただくことができた
自分の思い描いているワークシートの説明のデコボコ具合がさらけ出された
主観で突っ走る表現をセンスという言葉の自己暗示によって正当化していた
客観の必要性から目を背けていた
客観が担保されなければ主観は裸の王様になってしまうことに気づかされた
2022年は、教員採用試験の問題集の原稿を書かせていただいた
限られた紙面の中に必要な情報・大切な情報をどのように収めるかに苦心した
多くの情報を詰め込むことができたという自己満足は、校正段階で打ち砕かれた
伝えたい情報と伝えなければならない情報との峻別に気づかされた
2023年は、探究学習に関するコラムの連載記事を書かせていただけている
記事の読み手がどんな人であるのかを考え、言葉の種類や粒度を判断せねばならない悩み
主観で突っ走り、客観をないがしろにする癖はなかなか抜けていない
コラムの存在意義は、読み手のニーズに基づくことも痛感している
これまでの投稿は責任が伴わないがゆえに自由であったこと
現在のコラムは責任と結びつけられた緊張感のあるもの
そんな厳しい現実に後ずさりしてしまいそうになる自分がいる
でもその荒波のおかげで自分の表現が鍛え直されている実感はある
この年齢になってようやく仕事の厳しさに向き合わせていただけている
表現の「量」に対する慢心の破壊
表現の「質」に対する改善の余地だらけ
表現はまさに生き物
固定されて安定した形はない
だから表現の正解というものもないだろう
表現は相対的
表現する側である自分という「主体」の頭の中も、心の中も、私を取り巻く状況・環境も一様ではない
だから、絶対性を持つ正解の表現に到達することはない
表現を受け取る側である他者という「客体」についても同様である
他者が表現を受け取る時点で求めているもの
他者が表現を受け取る時点で関心が高いもの
他者が表現を受け取る時点の心境
他者が表現を受け取る時点の状況
他者が表現を受け取る時点の環境
それらも一様ではない
そうして試行錯誤の旅は続く
ゴールはない
自分が何を表現したいのか
どのような他者に伝えたいのか
どのようなことを他者に伝えねばならないのか
そんな思考・表現の「方向性」に関わるのが【課題の設定】
そうして目線が決まったら、今度は実際に思考・表現を動かしていくための材料集めが始まる
先哲の教え、最新の動向、身近な話、専門的な知識
思考・表現を形にしていくための、ありとあらゆる材料を見て、選んでいく
そんな思考・表現の「具体性」に関わるのが【情報の収集】
テーブルに置かれた材料はそのままではバラバラである
それらを比べることで、見えにくかった価値が発見される
同時に組み合わせていくことによって新たな価値も誕生する
そんな思考・表現の「創造性」に関わるのが【整理・分析】
見つかった価値・生まれた価値は以前からあるものではない
だからそれをそのまま他者に示しても「価値の『価値』」は伝わらない
見つけた自分、生み出した自分の熱量だけでは主観の突っ走りになりかねない
だから他者に理解できるような言葉の種類と粒度を考える
そんな思考・表現の「客観性」に関わるのが【まとめ・表現】
ここまで色々と書いてはみた
しかしその長さからしても、これまでの経験が活かされているか怪しくなってきた
だがフランスの小説家アンドレ・ジッドはこう言ってくれている
「真実を探している者を信じよ、真実を見つけた者は疑え。」
人はみな真実の探究者であり、真実を探し続ける宿命である
それにも関わらず、既に真実を見つけたなどと
探究の歩みを止める者がいるとすれば、そこにいるのは人ではなく神だろう
そして神でないとすれば、その見つけたとする真実はまやかしだろう
だから固定的で安定した正解のようなものが見つかり、その旅が終わることはない
私たちは「知の『旅人』」かつ「知の『探究人』」である
そして謙虚に知と向き合い続ける自分の姿に酔いしれる「知の『耽美人』」でもある
また主観に突っ走ってしまったようだ
反省の日々は延々と続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
