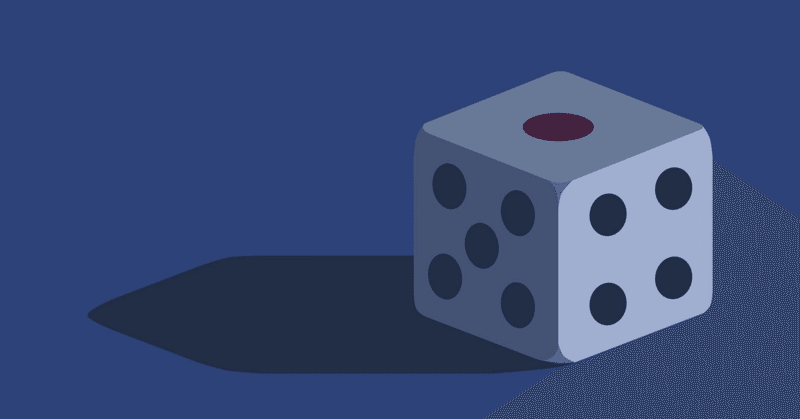
【小説】 六の目が出たら 【ショートショート】
今、僕は人生でぶっちぎりに最悪な日を過ごしている。
間違いなく、昨日まではバラ色だったのに。
出会いは二週間前。錦糸町のバーだった。その夜、さんざん盛り上がった僕らはそのままホテルへ雪崩れ込んで一夜を明かした。
まるで水のように透き通る肌。絹のような髪に、氷のようなまなざし。
完璧な女だった。それに、他愛もないような会話まで盛り上がった。
今はどうだろう? 原因は僕が散々調子に乗ったせいでもある。
僕は彼女を抱きながら、ベッドの上でこんなことを吹いたのだ。
「ねぇ、裕哉って強いの?」
「俺? まぁ、喧嘩は負けたことないかな」
「へぇー、強いんだ」
「まぁね」
僕は生まれて一度も喧嘩をしたことが無かった。だから、当然だけど負けた経験なんかない。だから、嘘じゃないと自分に言い聞かせた。
「私の旦那、超怖いヒトなんだよね……」
「ふーん。まぁ、勝てるかな」
「本当?」
「俺の方が断然若いんだし、力なら全然余裕っしょ」
「そんなこと言われたら、頼りたくなっちゃう」
「一人で抱えないで、誰かに頼るのも大事だぜ?」
幸穂に旦那がいることは初日に把握済みだった。それを分かっていて、禁断の果実を齧っているつもりだった。
その果実の実はあまりに甘く、そして多少の毒を含んでいるとは分かっていたけれど、致死性の猛毒だなんて気付きやしなかった。
僕の胸に顔に埋めた幸穂は、か細い声で言った。
「ねぇ、旦那に会ってみる?」
「え、俺が?」
「私のこと、欲しくないの?」
「幸穂を守れるなら、俺はオトコになるぜ」
「うん、頼ってる」
「俺に任せろっての」
そして、今日を迎えた。
「ここが私の家」
そう言って幸穂が指さした先には塀に囲われた豪邸が建っていて、門の両脇には強面の男が二人立っていた。
間違いなくヤクザの家だろうと思っていたが、悪戯そうに幸穂が笑った。
「引いた? うちの旦那、ヤクザなの。それも、組長」
ズバリヤクザの家だったのだ。僕は死を覚悟しながら幸穂に手を引かれ、門の中へと足を踏み入れた。
旦那の「組長」は六十前とはいえ戦場を潜り抜けて来たかのような屈強な身体付きで、顔面には「日本刀で斬られた」という傷跡を持っていた。
応接間に通された瞬間、旦那の姿を見た僕は小便をちびりそうになって声を震わせた。
「おう! おめぇがマメドロ野郎か」
「へっふ! はぁ……い!」
「座れやコラ。幸穂、おまえは出てろ」
「は~い。裕哉、またね〜」
「ええっ……あ、行っちゃう……」
組長と二人きり。僕はどのようにしてお詫び申し上げようか恐怖していると、組長は僕の顎を掴んでニヤついた笑みを浮かべた。
あまりの力に、顎が割れるかと思った。
「ほーう、確かにイイ男だわなぁ」
「しょ……しょんなことないれす……」
「どうだ。幸穂、良いカラダしてただろ?」
「ええっ!? しょの、あの……」
「俺がしこたま種付けて調教したカラダだからよぉ。ロハで横からぶんどられちゃあなぁ。金掛かってんだ、あのカラダはよ」
「しゅ……しゅいまへん……」
「おまえ、喧嘩強いんだってな?」
「いえ……よわい……れす」
「だろうなぁ。まぁ、いいや」
組長は僕の顎から手を離すと、テーブルの下からA四サイズほどの桐の箱を取り出した。
それを僕へ差し出してから、テーブルの上に片足を乗せたまましばらく黙り込んで僕を眺めていた。
正直、恐怖で気絶してしまいそうだった。
「じゃあ、ケジメつけようか」
「あのっ、本当に、この度は……」
「違ぇよ。ケジメつけろって言ってんだよ」
「ケジメ……ですか?」
「おまえなぁ、ヤクザの女に手ぇつけるってのがどういうことか分かってるよな? それも本妻だ」
「いけない、ことです」
「いけねぇよなぁ。でもな、世間で言う「いけない」よりも、もっともっと「いけない」ってこと、分かってんのか?」
「はい」
「じゃあ、ケジメつけろ」
恐怖で思考停止していた僕はもう「はい」しか言うことも出来なかったし、考えることも出来なかった。ケジメという単語は聞こえてはいたけれど、何をすれば良いのかも不明のまま時間だけが過ぎて行った。
すると、組長がサイコロをテーブルの上でコロコロと転がしながら何か言っていることに気が付いた。
いつの間にかそんな運びになっているとは知らず、知った瞬間に僕は絶望した。
「じゃあ、おまえの運に任せたわ。見せてもらおうじゃねぇか、な?」
「は……はい」
「おう、じゃあやれよ」
「はい」
「…………さっきからてめぇこの野郎! 俺が「さっさとやれ」って言ってんだろうが!」
組長がテーブルを蹴り上げた衝撃音で、僕は我に返った。
「すいません! あの、もう一度説明お願いします!」
「ナメてんのかテメェ!」
「すいません! 本当にすいません!」
「テメェが指詰めるのダラダラしてっから、サイコロ振って出た目の数だけ指落とせって言ったら「はい」って言ったんじゃねぇか!」
「そっ、そうなんですか?」
「その代わり「六」が出たら指は落とさないでやるって決めたんだろうがよ。まさかテメェ……俺があれこれ考えてやっていたのに、適当に「はいはい」返事こいてたんじゃねぇだろうなぁ!?」
「ち、違います!」
「だったら早くやれやコラァ!」
「はっ、はいいいいい!」
僕は、サイコロを、振る! 振って、出た目の数だけ、指を落とされる。
えっ! 指を、落とされるの!? なんで!? なんで!? えっ、訳分からない! なんで!?
「わかんない! なんで、わかんない!」
「さっさとやれやコラ」
「だって、お互い好きになってホテル行っただけで、なんで!?」
「……「だけで」だとテメェ、コラ。おい、こっち向け」
えっ。これって、僕は死ぬってこと?
なんで拳銃が僕の眉間に? これって、もうダメってこと?
やだ、やだやだやだやだ! 死にたくない!
「わ、わかりましたすぐ、やります!」
「おう。じゃあ今すぐサイコロ振れや」
「でも、六が出なかったら、指がなくなるのやだよぉぉぉおおお!」
「指なくなるのが嫌なんだろう? ええ? だったら「六」出しゃあイイじゃねぇか」
「怖い……怖いよぉ……お父さん……お母さん……」
「おいおいおい……なんだ、幸穂はこんな情けねぇ男に食われたってのかよ。あのオンナ、教育し直しだなぁこりゃ」
指がなくなったら、ごはんが上手に食べられなくなったり、スマホだって今まで通り使えなくなる。指がなくなったらどうやってLINEすればいいの? 音声認識? えっ。
「おまえダメだ。ラチあかねぇわ。じゃあな」
「ま、待って! 振ります! 今すぐ振ります!」
緊張と恐怖とパニックで僕は眩暈を起しながら、サイコロを掴んでテーブルの上に放り投げた。
頼むから! 頼むから「六」出て! お願い! 本当にお願い!
もう幸穂に二度と近付かないから!! 絶対に会いたいなんて言わないから!! だから、お願い!!
テーブルの上で跳ね返ったサイコロはそのままテーブルから転がり落ちた。
ふかふかのカーペットの上に零れたサイコロが、ピタリと止まって目を見せた。
嘘だろ……こんなことって、あるんだ。
「おい、おまえ……すげぇな」
「六……出た……」
「仕方ねぇな……もう、帰っていいぞ。あのオンナもついでに連れて行け。もう……用ねぇわ」
「えっ、帰っていいんですか?」
「いいよ、そういう約束だろ。おまえのツキが勝ったってことだ」
「やったぁ! すいませんでしたぁ! 失礼しましたぁ! あはははは! やったぁ!」
「ったく……こんな調子こいた野郎なんかに……さっさと出て行けよコラァ!」
「はい! さっさと出て行きます! お邪魔しましたぁ!」
「…………」
僕は有頂天になった。最悪な日が最高の日になった!
ヤクザに勝負事で勝った上に、幸穂まで手に入れた! これは武勇伝になるぞぉ〜!
浮かれ気分で門の外へ出ると、幸穂は愛車のベンツを停めて僕を待ってくれていた。
「裕哉、行こ?」
「うん、行こう!」
「ねぇ、運転してよ」
「もちろんさ」
生まれて初めて握る左ハンドルに若干緊張はしたけれど、さっきまでの死ぬほどの緊張に比べたら屁みたいなもんだった。
僕らは喜びを分かち合いながら、快適な車内でこれからの未来と希望についてたくさん話しまくっている。
信号待ちで停まっていると、幸穂がちょっとした(カワイイ)ワガママを言い出した。
「ねぇ、喉乾いちゃった」
「じゃあ、コンビニ寄ろっか」
「あ、すぐ目の前に自販機あるよ? ラッキ~」
「ラッキ~って、まさか降りるの?」
「信号が変わるのが早いか、私が買って戻るのが早いか、競争するの。楽しそうじゃない?」
「そういう変なトコも、好きだよ」
「ふふっ。じゃあダッシュしてくるねっ」
「よ~し。よーい……」
ドン!! っと衝撃を感じ、僕の頭は骨を通り越して脳まで激しく揺れた。
無事に車を降りていた幸穂が、笑いながらこっちを見ているのが確認出来た。
良かった、巻き込まれていない……だけど、なんで笑っているんだろう?
シートベルトはしているのに、前方に向かって僕の身体が激しく吹き飛んだ。これは、何かが爆発した? いや、大きな何かに猛スピードで追突されたみたいだ。乗用車じゃない。トラックか、ダンプカーだろうか。
車体がゆっくりと歪む音が、はっきりと鼓膜に届く。白い煙を上げながら、意味がなさそうなエアバッグが開いた。これって、多分助からないだろうな。だって、シートベルトが骨に減り込んで行ってるもの。
ヤクザって、暴力を職業にしてるから「暴力団」って言うんだぜ。見た目も怖いんだけど、関わると後々すっげー怖いんだって。
中学の頃、噂話が大好きな飯島ってやつが、楽しそうにそんなことを言っていた。
ダメだ。もう、意識が飛びそうだ。首の骨が抜けて行く感覚が、ある。
僕はやっぱり今日が人生で最悪な日だったんだと、ひしゃげたハンドルが胸に食い込んで行くのを感じながら、思い知らされていた。
サポート頂けると書く力がもっと湧きます! 頂いたサポート代金は資料の購入、読み物の購入に使わせて頂きます。
