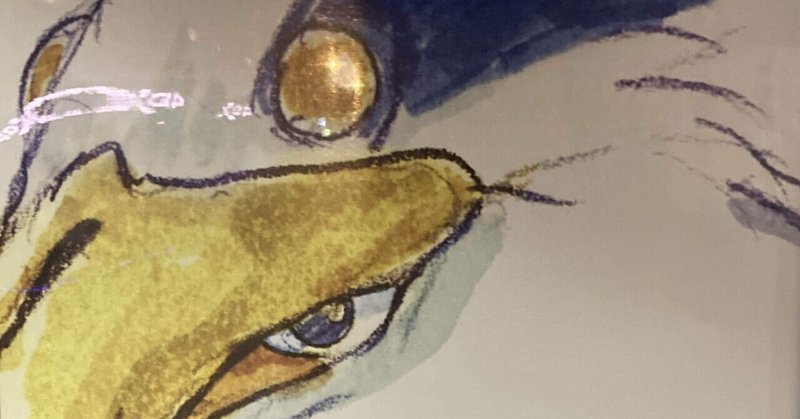
『君たちはどう生きるか』をどう誤解するか(2023.7.29改題・内容改訂)
2023.7.14初鑑賞
宮﨑駿さんの監督作品ともなれば、あらゆる分析ができるわけで、今回の『君たちはどう生きるか』にしても、たとえばあの空から降ってきた物語の主軸となる不思議な塔は、あれはスタジオジブリそのもの、あるいは宮﨑駿監督作品そのもの、あるいは日本のアニメ史ではないかという指摘もあります。
そして塔の内部の世界観、すなわち主人公眞人の冒険譚は、宮﨑さんが今作の作品制作に取り掛かるきっかけの一つとなったというジョン・コナリー氏の『失われたものたちの本』、そして宮﨑さんが愛読していた江戸川乱歩氏の『幽霊塔』、宮﨑さんが新人のアニメーター時代、および大塚康生さん小田部羊一などの宮﨑さんの先輩・同期の方々、そしてなにより高畑勲さんがアニメーションへの道を志すきっかけになったりと、日本にも多大な影響を与えたポール・グリモー監督の『やぶにらみの暴君』(1952年公開。後に『王と鳥』と改作)、そして宮﨑さんも場面設計・美術設計・原画として参加し、高畑さんが演出(監督)デビューをした『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968年公開)。これらが下敷きになっていると思われます。
まだこの作品のいわゆる「元ネタ」をあげようと思えばいくらでもあげられるでしょう。例えば宮沢賢治氏の作品へのオマージュが至る所に散りばめられています。わかりやすい点で言うとインコたちが眞人を食おうとする展開は『注文の多い料理店』だし、それに米津玄師さんが歌う主題歌『地球儀』にも『小岩井農場(パート九)』からの引用が見られます。
または、宮﨑さんが今までつくってきた、『風立ちぬ』、『ハウルの動く城』、『千と千尋の神隠し』、ラストは『ルパン三世 カリオストロの城』なども随所で連想させられます。
このいわゆる「元ネタ探し」という謎解きは非常に楽しいと思います。しかしそれはまさに作り手が観客=受け手を巻き込もうとするという意味において私たち受け手は術中に嵌められており、映画の大事な本質を見逃す可能性がある気もしなくもないと思います。
ただただあのシーンはあの映画からの影響でとか、あのシーンはあの絵画からの影響で、と謎解きに没頭しすぎて、そして謎を解いたと思い込み、ああわかったという気にすぐなってしまうのはちょっと危ういという気がするのです。
この『君たちはどう生きるか』は冒険パートが始まる前からして謎だらけです。
なぜ最初からアオサギが眞人のことをあんなによく知っていたのか?なぜナツコは塔の世界へ行ったのか?なぜアオサギの羽が最初は拾えなかったのにいつの間にか拾えるようになったのか?など。これらの答えは映画内でははっきり明示されません。
冒険パートが始まってからも謎は尽きません。
なぜキリコは若返って「あの世」で暮らしているのか?なぜヒミはそもそも火を操る力を持っているのか?そして大叔父様とは結局何者か?
大叔父様のモデルは、例えば高畑さんだとか、はたまた宮﨑さん自身ではないかとモデル探しが流行しています。他にも宮﨑さんが尊敬している堀田善衞さん、司馬遼太郎さん、中尾佐助さん、藤森栄一さんなどもモデルに入っていると思いますが、しかしたった数人だけではなく、私は全ての亡くなった先人たちの様があの大叔父様に込められていると思いました。私事で恐縮ですが、大叔父様には宮﨑さんが知る由もない先日亡くなった私の祖父の影すらも見ました。
さて、謎は誤解を生むものです。
しかし誤解は決して必ずしも悪いものではないと思うのです。映画というものは正しく理解をしようとすると逆にうまくいかないのではないでしょうか。誤解でもって映画を捉える。それでいいのではないでしょうか。そういう意味でこの謎だらけの『君たちはどう生きるか』を理解できない!と簡単に見捨ててしまうのは勿体ない気がします。むしろ映画として豊かな魅力にあふれた作品と言えるのではないでしょうか。
私がこの映画に祖父の影を勝手に見ることも完全な誤解ですが、それが映画を豊かにするということなのではないでしょうか。
そして宮﨑さんが監督した長編作品で初めて「おわり」や「おしまい」などのエンドマークが出ない、つまりこれは終わらない物語であり、現実と風が吹き通う映画なんだということに気づきこれには思わず感涙してしまいました。
あんなに映画というものは終わりのあるものであり現実とは違うものなんだとはっきり述べていた宮﨑監督がここでいよいよ「私はこう生きた。君たちはどう生きる?」と言わんばかりに終わらせなかったこと。私はそこにとても感銘を受けました。
と同時にあの宮﨑駿さんですら、今の時代、終わりのある、美しく閉じた物語を描けないということに強い危機感も感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

