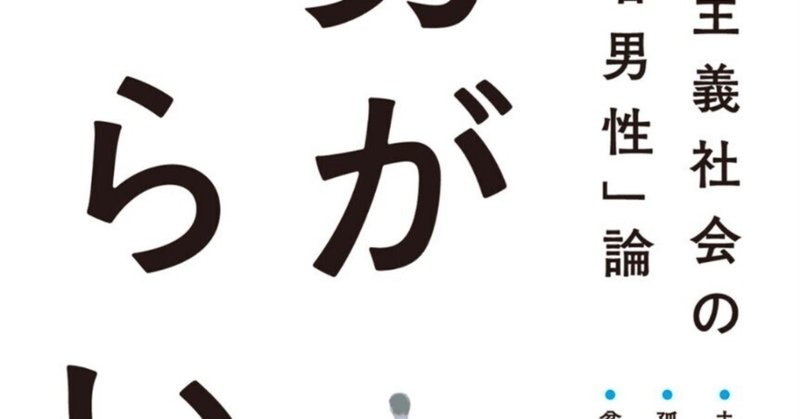
竹美書評 皆はこう呼んだ、エンツォとワーニャは弱者男性! 杉田俊介『男がつらい! 資本主義社会の「弱者男性」論』
「弱者男性」とはどんな人達か
弱者男性、インセル、きもいおじさん、ホモソ、ちんよし、チー牛、有害な男性性…2020年代は、男性の残念さを表現する単語が大量生産・大量流通した(もしくはし始めた)時代として記憶されるのではあるまいか。
MeToo時代を経た私には、本書は今読む必要がある本だと感じた。
杉田俊介は本書で以下のように書いている。
弱者男性たちは、社会的に差別されたり排除されたりしている、あるいは政治的な承認を得られない――というよりも、それらの二元論的な議論の枠組みそのものから取り残され、取りこぼされ、置き去りにされているのだ。
ーーーー
現代の弱者男性たちとは、まさにグローバル資本主義とリベラルな社会から「置き去りにされ」、「取り残され」た人々のことであると言えるだろう。
マイノリティでもないしマジョリティでもない、資本主義の勝ち組にもなれない男性。つまり何の意味もなくつまんない人生で、何で存在しているんだというレッテルを外から貼られ、それを内面化して鬱屈を深めていく男性たちは、今やその鬱屈を表明すれば、もっと強い非難を受ける。
概ね、Netflixの映画は弱者男性のやりきれなさを掬い取れてはいないように思う。『好きにならずにいられない』はややそこに触れている気もするが、北欧映画の『孤独』に対する我慢強さの所以という気もして、日本人にとっては参考になるのかどうか。
個人的な体験としては、男サン(この言い方w)はさァ、マジョリティなんだからちょっとくらい我慢しろよ、何ならちょっとくらい搾取されたくらいでがたがた言うなよ…MeToo時代の脈絡で、少なくとも私は様々なレベルでこれを感じていた。しかしそれに言い返すことは憚られた。だって私は、ゲイというマイノリティかもしれないが、「男」というマジョリティなんだから。
男性特権は存在する。ではそれを持っているんだから手放せ、と外から言われても、具体的に男性は何を手放したらいいのだろうか。
正直、異性愛者で、生活苦に追われ、異性から好かれることもなければ同性の友達も少なく、自分で自分が好きでもないという人にとっては何を手放せばいいのか分からないだろう。
何で生きているのだろう。生きてても何の意味もないのに。その鬱屈の結果が特定の人への攻撃に向かってしまうことは非常に痛ましい。が、その鬱屈こそが社会的に取り組まれるべき課題であるとする声はあまり強くない。
一方で、男の問題は男が自分で解決しろよ、抑制に耐えろよ、好かれる努力しろよ、男のくせに、という価値観をはっきり提示する社会で、男だって(本書の言葉で言うなら「正しく傷つく」ことを認め)、傷ついたんだと弱音を吐いていいんだ、男同士で支え合えばいいじゃないか…というアドバイスが大して当の男性の関心を引いていないのはなぜなのか、もうちょっと考える必要があるのだろう。
或いは、その「無意味」は宗教が埋めてくれるかもしれない。仕事が意味を与えてくれる日本文化に関する限り、多くの男性は、その静かになると襲ってくる「お前は無意味だ」という声を「会社」とか「仕事」が埋めてくれるわけだが、退職後がきついわけだし、仕事が無いとそれはとてもつらい。
問題は、その「つらさ」を「つらさ」として受け止めてくれる受け皿がどこにもないということだろうと思う。
弱者男性論としての『ワ―ニャ伯父さん』と『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』
大好きな映画だが、その映画評をうまく書けた気がしない作品に、イタリア映画『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』がある。
大好きなのに、何かが喉につっかえているような気がずっとしていたが、本書を読んで腑に落ちた。あれは弱者男性の物語だったのだ。
杉田俊介は、チェーホフの『ワ―ニャ伯父さん』のワ―ニャ伯父さんを弱者男性のモデルとして取り上げている。何の楽しみも意味もなくただ働き、親族に搾取され、うんざりしたまんま生きていくワ―ニャ。教養があることが却って本人を辛くさせる。
彼の親戚で、神を信じるソーニャはこの苦しい生活を続けて、「生きていきましょうよ」、いつか死ぬ時が来れば神の前ですべて報われるはずなんだから、と宥める。
実は私はこのくだりが『ワ―ニャ伯父さん』の中で一番好きだった。
しかし、ソーニャの方が女であることで人生において割を食っていることを勘案しつつも(偉いよ、杉田さん…)、神を信じる、つまり宗教という救いすらないワ―ニャはどうしたらいいのだと指摘しており、はっとさせられた。
その上でワ―ニャはすごい。杉田によれば、ワ―ニャは
誰も殺さず、女性を憎まず、自殺もしないという倫理
を生きたからだ。彼は憎い男を殺害しようとするが恐らく意図的に的を外し、自分を愛さなかったという理由で女性を憎むこともなく、彼は自殺も思いとどまる。
日本や他の国でも発生する男性による大量殺人事件に観察される「殺す」「ミソジニー」「自殺」。この三大要素は、男性において「男らしさ」と「有害な男性性」の間のごったまぜゾーンに属する行為ではないかと思うが(人巻き込んで殺すくらいなら自殺しろよって皆言うのはそういう意味では)、その上で
救済も解脱もない忍耐こそが弱者男性の尊厳である
と宣言している。壮絶だ。この覚悟は。怒りを特定の人に向けるのではなく、社会に対して怒れと。私は結構驚いた。修験道じゃないですか。フェミニズムだって、特定の人に怒ることに留まりがちで、本当には「社会」に対して怒りをぶつけきれていないというのに。どうしてそこまで自分に厳しく…。
これが、社会というものと個人の欲望が正面衝突した場合の弱者男性としてのカッコよさなのだろう。と同時にそれは「男」の意味付けからの解放とも思えず、苦い。内省的過ぎるのかもしれない。
『皆は…』に戻ると、主役エンツォは、社会的にも底辺にいて、元締めのギャングの親分にお目通りすら叶わないチンピラ。死んだ目をしてポルノビデオを見てオナニーする位しか楽しみがない。楽しみというかもはや排泄に近いのだろう。
彼は犯罪者であるし、悪人だ。おまけに知り合った少女と不同意性交をしてしまう。のみならず、彼女の死によって彼は自分の無意味な人生に意味を見出すのである。
『皆は…』がすっきりしているのは、このように扱いようのない弱者男性は、仮面をかぶり、名前を捨て、無名のヒーローとして孤独を友として生き、世の小さな不正を正していけ、という社会工学的な弱者男性の処分方法を示していることであろう。そして、私はこの映画が好きなのはそういうところに「男のかっこよさ」を見ているからだろうと思う。
しかしそれは、私が「弱者男性ではない」からなのかもしれないし、実際の所、弱者男性にとっての解放ではない。
非力なワ―ニャおじさんと、孤独に戦うことを決めたヒーローのエンツォは表裏一体であるし、本当にはどちらも救われていないように思う(映画も本も彼らの救済を検証していない)。
MeToo時代の黄昏
さて本書の言う意味で、エンツォはまさに弱者男性だ。しかし、でかい図体して何言うんだ、女は男がいるだけで怖いんだ、というのが、今、男性を批判する女性が寄ってたっている正義である。
私は本書を読むまではっきり言葉にする度胸がなかったが、この「正義」の物語と比較すると、男女平等という立場に立つなら、男の側には「怖いから抵抗するんだ、怒っているんだ」というエンパワーメントの物語すら無い。まして…女性と関わる部分がほとんどない男性が「男はいるだけで怖いんだ、有害な男性性を持っているんだ」という言葉についてどう考え、処分し、周りに迷惑をかけないよう軟着陸できるのか。
階級闘争物語の溢れた今、男性のこういう「どう思うか」なんか大事ではない。男は絶対的に自分を抑制し続けねばならないのだから。
『皆は…』は、2015年の映画なのでMeTooを知らない状態で作られているが、エンツォはMeToo時代においては即死すべきキャラであろう。私が内面化したMeTooの教科書がこう言う:女を男である自分のために犠牲にするなよ。
これは物語の構造に対する文句なのであるが、こういわれてしまうと、もう本作について掘り下げることすらできなくなってしまう。私はそうだった。
私は、まず相手の話を真面目に聞いてその中に落ちていかねばならないと考えるタイプである。
故に、MeTooをそれなりに真面目に内面化したので、「男が悪い」という意見が友達との会話の中にちょいちょい出て来ていたとき、うっすらそれへの疑念や反論を持った自分を恥じ、隠ぺいして抑圧してきた。
が結局それは私の「ホンネ」(これは本書では、ホモソ集団の中で共有される加害的な意識を形成するものだとされている)ではなかったため、状況が少々変化して来た今…特に私のある友達が「思想転向」してあんまりそういうことを言わなくなり、ようやく「何か変じゃないか?」と言えるようになった。
ただ、言われていたことや内面化したことに反発するだけでは、結局私もミソジニーに共鳴して一緒に揺れるミソジニーマラソンコンサート会場のファンの一人になってしまう。
杉田は、ここで集合的な怒りと加害に繋がりやすい、かりそめの「ホンネ」ではなく、「本心」という言葉を提示している。
私の言葉で言うなら、それは「私は、そういう物言いをされて心にかすり傷がついていたけど、それをずっと言えずに我慢していたのでそれが恨みに変わった」という心の動きを冷静に見ることだった。その先に、「恨みが溜まって行くのが幸せじゃなかった。でも、相手が女だからという理由で反論できなかった」という物語を描くことができる。
それを相手が聞いてくれるかどうかは別のことであるが、こうして、「恨み」を対象化してしばらく眺めてからガンジス川に流す(私の家はクリシュナ側の上流なのだが)しかあるまい。
私は弱者男性ではないが、「自分の傷つき」を傷つきだと認識しなかったり、MeTooの影響下で傷を否定した経緯があり、そこで本書と繋がりを持った。
本書は多分、弱者男性を救う方法を提示しているわけではない。でも、今可視化されにくい感情を、出来る限り社会に配慮した形で提示し、「恨んだり憎むことを終わりにしたい」という願いが伝わって来た。
短い本だがとてもよかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
