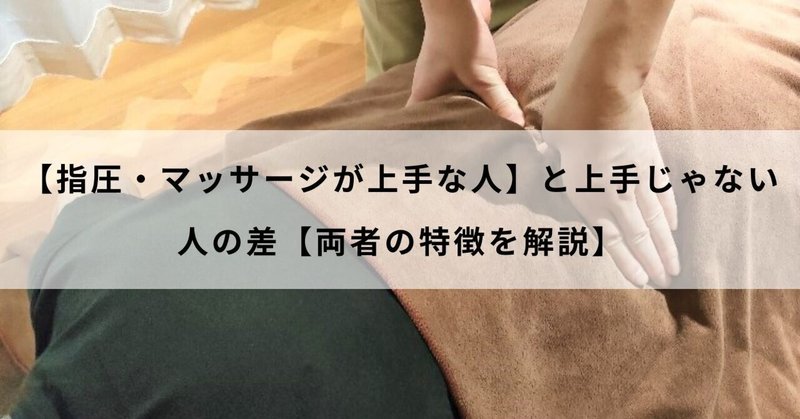
【指圧・マッサージが上手な人】と上手じゃない人の差【両者の特徴を解説】
先日、私がXで投稿したポストで、予想以上のリアクションを得ました。
指圧(マッサージ)が上手な人の特徴
— 【鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師】の上茶谷です (@taka0901ue) September 12, 2023
①手に迷いがない
②リズムを大事にしている
③理由なく骨を押さえることがない
④よけいな箇所を必要以上に押さない
それと、めっちゃ重要なのがコレ!
相手を不快にさせる言動がない!
これを受けて、今回は指圧(マッサージ)の上手な人と、そうでない人の違いを記事にすることにしました。
※以下、指圧(マッサージ)を「施術」という言葉で統一します。
あなたが患者から「施術が上手だ!」と思われるためのヒントになれば幸いです。
まず、施術を上手におこなうためには、施術者自身に求められる特徴があります。
上手な施術者とは、まとめると次の特性を備えています。
手に迷いがない
リズムを大事にしている
理由なく骨を押さえることがない
余計な箇所を必要以上に押さない
以上の特性を施術が上手な人と、そうでない人の違いとしてお伝えします。
本題へ入る前に簡単に自己紹介を。
上茶谷 貴之 (うえちゃや たかゆき)
・H21年 柔道整復師免許取得
・H31年 鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師免許取得
鍼灸接骨院、リラクゼーションサロン、フィットネスクラブ、介護施設、など10ヶ所以上の事業所で施術実績を積み、R3年3月に京都市内で開業。
(施術所のホームページ)
https://iyashimedical.com/
現在は1人で完全自費の施術所を営み、日々患者に向き合う。
では、本題へ入ります。
指圧(マッサージ)が上手な人の特徴
①手に迷いがない
施術が上手な人と、そうでない人の施術を比較すると、違いがはっきり分かります。
施術が上手な人は、特定の箇所に指を置いた後、しばらくの間、持続圧を加えます。
これによって、「この施術者は私の体の凝っている所を理解している」とい安心感が生まれます。
※安心感が生まれることで、プラセボ効果の向上が期待でき、結果的に患者の症状の改善につながる。
一方で、上手でない施術者は、圧力を持続させず、短時間で指を動かし、次々に異なる箇所に触れてしまいます。
その結果、施術を受ける側からすると、「ああ、ここが問題だと分かってくれたのに、なぜすぐに離れてしまうのか?」と、不満を感じてしまいます。
仮に凝っている箇所、問題のある所が分からないとしても、「ここだ!」と思った所を押さえ続けましょう。
その方が、施術を受けている側はストレスを感じません。
※保険施術中心の接骨院や整形外科のように、施術時間が短いところでは、瞬時に問題がある箇所に施術できる能力が求められます。
②リズムを大事にしている
上手な施術者は、施術のリズムを重視しています。
一部の施術者は、凝っている箇所にじんわりと持続圧をかけて緊張を緩める方法を選びます。
一方、別の施術者は一定の素早いリズムで瞬時に力を加えて、緊張をやえわらげます。
どちらのリズムの施術を受けても、正確な箇所に圧をかけてもらえるこ とで、心地よさを感じます。
この違いは、「補」と「瀉」をイメージしてもらうのが良いでしょう。
※前者が「補」後者が「瀉」。
しかし、上手でない施術者は一貫性がなく、施術のリズムが乱れがちです。例えば、肩背部の施術を考えてみましょう。
彼らは一部の箇所には持続圧をかけ、他の箇所では瞬間的な圧を加え、指をすぐに離すことがあります。
受けている立場からすると、「一体何をしようとしているのか?」と疑問に思うことがあり、集中して施術を受けられません。
ただし、施術の流れで肩背部は瀉の施術をして、腰下肢は補の施術をする場合があります。
その例が、上実下虚の患者です。
上実下虚に出やすい症状⇩
イライラしやすく、よく頭痛が出でる
肩や背中の疲れを感じやすく、呼吸が浅い
睡眠時間が短く、足腰に疲れ感やだるさを感じる
※肝実腎虚の方を、想像していただければと。
上実下虚は中間管理職、幼い子を育てるシングルマザーに多い印象です。
③理由なく骨を押さえることがない
施術中、骨に圧を加える場合、それには特定の理由が必要です。
通常、筋肉を対象に施術する際、骨の位置を確認する必要があります。
また、ぎっくり腰や急性の肩関節周囲炎などの症状に対処する場合、病変部位を探すために骨を指標とすることがあります。
施術の流れで意図的に骨に触れる、部位の例を挙げます。
外後頭隆起(僧帽筋)
肩甲骨上角(肩甲挙筋)
腰椎下部の棘突起(多裂筋)
中足・中手骨(骨間筋)
などです。
※1-3は刺激を与え過ぎると患者の状態が悪化する恐れがあるため、注意して施術する必要があります。



一方、施術が上手でない方は腹臥位での施術時に
肋骨
大転子
頚椎の棘突起
などの骨に押圧します。
おそらく、臀筋群や脊柱起立筋を対象にしているのでしょうが、指の当て方や圧をかける方向が不適切であると、施術後に痛みを引き起こすことがあります。
もちろん、私を含めて皆さんも施術時、骨をに触れる場合は慎重さが求められます。
患者の快適さと安全を最優先に考えましょう。
④ 必要以上に余計な箇所をおさない
「余計な箇所」とは、①で言及した手に迷いがないという点と連動します。つまり、施術を受ける側が特に施術して欲しい箇所を指定したにもかかわらず、それとは異なる部位ばかりの施術を受ける状況です。
具体的な例として、肩こりの患者が肩の重だるさを訴えているのに、下肢など他の部位に多くの時間を費やすことが挙げられます。
もちろん、下腿(膀胱経、胆経)、前腕(陽経)の施術が一部の肩こりに効果的であることは承知しています。
しかし、特に慢性的な症状の場合、患者さんは肩の痛みに焦点を当てた施術を望むことが多いでしょう。
※急性期の症状がある場合、患者の了承を得た上で、遠隔部位の施術を行うこともあります。
施術が上手でない者の例として、以前リラクゼーションサロンで施術を受けた経験を挙げましょう。
私は60分の施術をお願いし、「太ももとふくらはぎが特に疲れており、それに続いて肩がこっている」と伝えました。
しかし、施術が始まると、ほとんどの時間が肩背部の施術に費やされました。
おまけに、接遇のレベルもひどくて、ひどくて…
今はお金と時間が勿体ないからしないけど、若い頃は勉強のために、施術が上手でない所へ施術を受けにいった。
— 【鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師】の上茶谷です (@taka0901ue) September 13, 2023
特に激安リラクゼーション(外国人)は酷かった。
・肩背部の施術が肩甲骨を押圧し続ける
・施術中、急に手を離し、他の施術者と話す
・許可なく施術時間を延長しようとする
ひどかった。
リラクゼーションサロンで施術を受けた時のポストです。
60分2,800円のサービスのレベルを体験することができ、良い教訓になりました(笑)
技術の質を向上させるために、他人の施術を受けることも学びの一環

以上、上手な施術者とそうでない施術者の特徴を挙げてみました。
共感できる内容は、ございましたか?
技術の質を高めるためには、繰り返しの練習や多くの患者への施術経験が不可欠です。
同様に、他人の施術を受けることも非常に重要です。
良いと感じた施術方法を参考にして、自分の手技に取り入れることが学びの一環となります。
施術を受けに行くと、期待外れな結果や上手でない施術を経験することもあるかもしれません。
しかし、これらの経験も貴重な教訓となります。
良くないと感じた施術(接遇も含む)を、患者に提供しないように反面教師としましょう。
この記事があなたの施術の精度、向上の一助となることを願っています。
定期的にXでも情報を発信しています。
どうぞ、気軽にご覧いただけると幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
