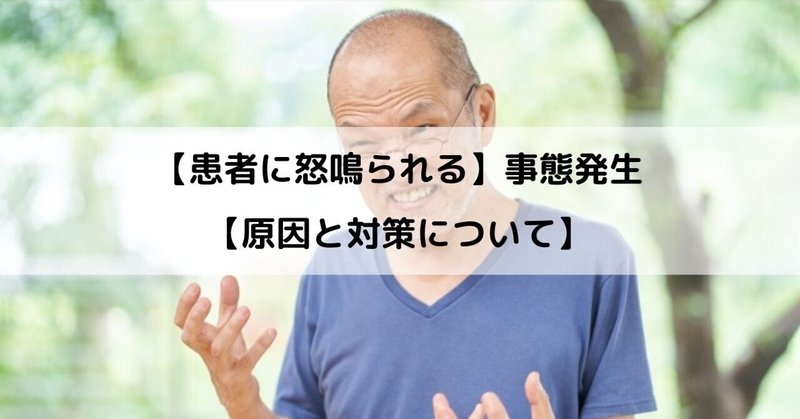
【患者に怒鳴られる】事態発生【原因と対策について】
京都で鍼灸マッサージ院を運営しながら週に1度、大阪の鍼灸整骨院へ働きに行ってます。
そこで私の施術に納得されなかった方と口論になりました。
※口論になった患者には私を含め3名の鍼灸師が施術しています
何故そのようなことが起きたのか、話を盛らずにお伝えします。
余談ですが、怒鳴れた経験のある人は意外に多いようです…
【全ての職業の方へ】
— 上茶谷貴之 【鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師】 (@taka0901ue) March 23, 2023
お客さんに怒鳴られたり一方的に文句を言われた経験はありますか?
※エピソードがあれば気軽にコメントいただけると幸いです。
なぜこのような事態が起こったのか?

患者が求める施術を行わなかったことがきっかけです。
患者について一部紹介。
ケガして来院。
当初は痛み、腫れ、熱感などが診られたため、患部への施術を控えてました。
柔道整復師の院長が施術を終え、鍼灸師である私に変わります。
院長から引き継ぎ中、患者から
「どこに鍼するん!?」と質問され「症状によります」と回答。
すると
「なんやそれ、どこにするか聞いてるんや!」と言われました。
院長から
腫れがひいている
痛みが落ち着いている
痛い側と反対の筋肉が張っている
などの情報を聞き施術開始。
患部の周辺に鍼をして、患部は灸をするつもりでした。
鍼を打ち終えツボに灸を置いていると、
患者「おい、なんで痛い所に鍼せへんのん!?」
私「鍼でなくお灸をします。」
患者「いや、ちょっと待てよ!他の先生は鍼してるで!あんたはなんでせえへんの!?」
私「する必要性を感じないからです」
※患部に鍼をしなかったのは痛みが出やすい部位であり、他の施術者が担当したさい、痛がっていたから。
くわえて、足の冷えが顕著のため。
※痛みを感じやすい部位についてはホムンクルスが参考になります。
https://koto-orthopaedics.com/no-painful-injection/
くどくなるのでこの後のやり取りは割愛しますが、最終的には私が
「違う日に他の鍼灸師に施術をしてもらえばどうですか?」
と提案。
すると、「ほんならええわ!帰るわ!」
と患者が怒りを表し終了。
私が他の鍼灸師の施術を勧めたことに腹が立ったようで、
「あんたが言うのは逃げ口上や。他の業界でそんなこと言うとったら腕落とされるぞ」
と言われ、院長が仲裁にはいり終了。
ここまで読まれた方は
「上茶谷のコミュニケーション不足が原因じゃない?」と思う方もいらっしゃるかもしれません…
そう!その通りなんです!
とどの詰まり原因はコミュニケーション不足

患者が冷静になり、私に言ったことは
あなたと他の先生のすることは何故違うのか聞きたい
患部に鍼をしない理由を納得できるように説明してほしい
あなたの考えがあるなら伝えてほしい
ということです。
以上のコミュニケーションが欠けていたのが、事件の発端になったのは間違いないでしょう。
インフォームドコンセントを思い出しました。
インフォームドコンセント:十分な説明を受けたうえで患者さまご自身が同意の上、最終的な治療方法を選択していただくということ。
コミュニケーションをしなかったのは理由があって、
10分以内で問診と施術を行うというルールがある
違う日に「話を短くして早く施術してください」と院長から指示を受けた
患者にとって症状を毎回細かく聞かれるのはストレスになると考えた
以前同様の患者の施術にはいったとき「任せます」と言われた
などです。
お給料をいただいている立場なので、事業所の方針に従おうとするのは当然です。
また、患者の立場になったとき質問ばかりされたら「ここは施術者のあいだで情報が共有できていないのか?前も同じこと言ったぞ」と不安になります。
最後に、施術前にエラそうなモノの言い方をされて、
「どうして誠心誠意の対応をする必要がある?」
って思ったのは本音です。
こちらは施術者でもあり、感情を持った1人の人間です。
器が小さくてすいません…
私の想いに共感してくださった方がおられて嬉しかったです。
施術者は患者(お客)さんの不調を取り除いたり、要望に応えるのが仕事だと考えてます。
— 上茶谷貴之 【鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師】 (@taka0901ue) March 22, 2023
ただ、聖人君子でいる必要はないと考えています。
・口調があらい
・施術の協力をえられない
・要望が過剰
な人などはこちらから断っても良いと思うんですが、どうですか?
今後の対策

カルテに情報を残す
カルテの記入に統一性はなく、基本的には症状、施術部位、施術内容だけが記載されています。
時間に追われていても
Subjective(主観的状態):患者が自分の症状や感覚について説明する部分。
Objective(客観的状態):施術者が患者から聞いたり、患者の状態を確認して得られる情報
Assessment(評価):主観的状態、客観的状態から得られた情報から導いた患者の病態。
Plan(施術計画):どのような施術を行なったか。今後の施術方針について
は記入が必要と考えます。
引継ぎを具体的にする
院長が施術をした後、鍼灸をおこなうケースが多いのですが
「肩・腰に鍼をお願いします」
「〇〇筋が張ってます」
といったかたちで患者を引き継がれます。
さすがに情報は少ないので
「体を前に曲げると腰の下の方が痛いそうです」
「左を振りむこうとすると〇〇筋に痛みが出るそうです」
くらいの具体性が必要です。
しかし院長に求めるだけでなく、こちらからも確認する必要があります。
最後に
つね日頃から、スタッフ間で話し合う必要があります。
例えば、
患者の症状の経過
どのような考えでどのような施術をしたか
症状が出ることで患者はどのようなことに困っているか
など。
週1回の勤務で院長以外の施術者とは顔を合わせないので、難しいのが現実ではありますが…
今回の記事が組織で働く人にとって、なにかの参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
引き続きTwitterでもよろしくお願いします。
私が運営する癒しマッサージ鍼灸院(京都市南区)はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
