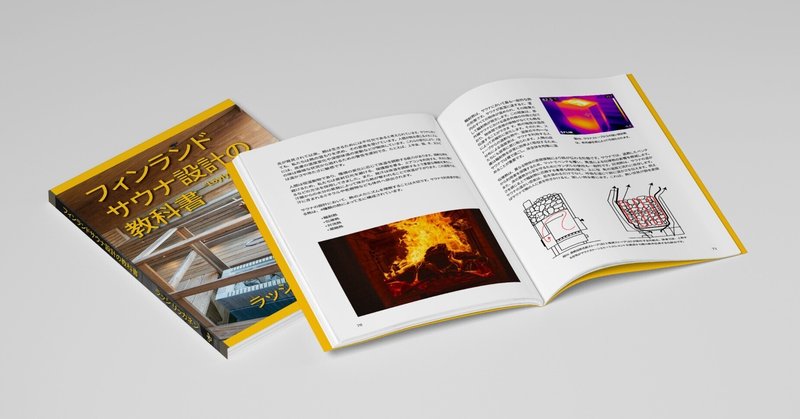
『フィンランドサウナ設計の教科書』出版のお知らせ
突然ですが『フィンランドサウナ設計の教科書』という書籍をリリースしましたのでお知らせとなります。2024年5月9日よりAmazonにて発売開始され、国際サウナ協会会長によるご推薦のもと、日本サウナ・スパ協会様の会報誌においてもアナウンスをいただきました。この場を借りまして、書籍出版にあたりご支援いただきました皆様へ心から感謝と御礼を申し上げます。
本書籍は『The Secrets of Finnish Sauna Design』の日本語訳版であり、著者であるラッシ・リッカネン氏は、フィンランドサウナの専門家兼デザイナーとして国際的に活動されている第一人者であられます。私は日本語訳版の編集・翻訳担当として、Keiichi Kitagawa氏とともにプロジェクトへ参画しました。また、日本の専門家の皆様に多大なるご協力をいただきました。

本書籍の内容ですが、端的に申し上げると「フィンランドサウナのつくり方がわかる本」となっております。なにを扱っているのか、各章の概要をご紹介しながら、どのように、だれが、いつ、どこで本書籍を活用いただくことを想定しているのか、なぜ、日本語版を出版するに至ったのかを、翻訳・編集者の目線で解説し、本書籍を手に取るきっかけとなりましたら幸いです。
「フィンランドサウナ設計の教科書」の概要
はじめに、本書籍の冒頭には以下のようなくだりがあります。これはフィンランドとその他の国との捉え方の違いを端的に表しており、たとえサウナの専門家でなくとも、そのサウナがフィンランドサウナに該当するかそうでないかは容易に判別されてしまうという事実があります。
海外で「サウナ」や「フィンランドサウナ」と名付けられた施設に対し、フィンランド人は違和感を敏感に感じ取ります。彼らはサウナ建築の専門家ではありませんが、サウナの本質を直感的に理解しています。フィンランドにはプライベートサウナが多く、その形態や作法はさまざまです。しかし、彼らにとってのサウナの馴染み深い概念は直感的に養われます。
この直感的感覚は老若男女関係なく、現代フィンランド人の多くが備え持っており、日本のサウナ文化との決定的な違いの一つであると推測されます。本書籍の出版に合わせて、著者のリッカネン氏が来日されましたが、日本のサウナをご案内し、ともにサウナ室で汗を流してもなお、日本人として、フィンランド人との直感的感覚の違いを認識せずにはいられませんでした。
そのような違いがあるなか、本書籍を含む原著の存在意義は「世界中でより良質なサウナを普及させるため」とされています。楽しく、リフレッシュでき、健康によいロウリュとサウナを提供するため、たとえフィンランドとは異なる環境であっても、いかにフィンランドの本質を踏まえたサウナをつくることができるのか、その具体的方法と再現手法が詳細に書かれています。

リッカネン氏は、最高のサウナを実現するためには4つの条件が備わる必要があると明示しています。第1章ではサウナの「文化」、第3章ではサウナの「熱」、第4章ではサウナの「空気」、第5章ではサウナの「内装」について詳細に掘り下げており、サウナの外観だけでなく、ロウリュを基軸としたサウナ体験の創出を論理性を持って示しているのが本書籍の特徴になります。

サウナの「熱」を扱う第3章は、熱のメカニズムからサウナストーブとストーンの仕組み、メンテナンス方法などについて詳細に解説されています。たとえ日本のすぐれた建築士であっても、熱を発するストーブを扱った経験がないという事例は珍しくありません。このようにサウナの「熱」の特殊性を知り、最高の熱の体験を設計するためのヒントが本章では書かれています。

第4章は、サウナでもきわめて重要な「空気」の設計について解説されています。著者が来日した際、日本とフィンランドサウナの違いと印象をたずねた時に真っ先にコメントしておられたのは「空気」の違いでした。さらに本章では、昨今言及される機会が増えてきた「フレッシュエアーのつくり方」について詳細に解説されており、日本初公開の内容になるかと思われます。

最高のサウナを実現するための最後の条件、サウナの「内装」については第5章で解説されています。ここで言う内装とは、ベンチやガラスなど人間が直接目に見えるものにとどまらず、目には見えないロウリュを含めた包括的な空間設計手法にも触れている点が特徴です。さらに「ロウリュの法則」と呼ばれる考え方に基づき、内装設計の優先順位を論理的に提示しています。
このように論理性によって再現性を高め、どんな地域や場所でも、フィンランドの本質をとらえたサウナのつくり方が、本書籍では解説されています。
「なぜ」日本語版が出版されるに至ったのか
ここまでが本書籍の概要となりますが、なぜ日本語版が出版されるに至ったのか?編集・翻訳担当としての立場で説明してほしいというお声を多く頂戴しました。ここからは個人的に、出版の背景について書きますので、著者・出版社・協会・大使館など、特定の企業や組織によるものではなく、わたくし個人の見解として、話半分のお気持ちでお読みいただけますと幸いです。

まず私とフィンランドサウナとの関係性は7年にわたります。フィンランドをはじめて訪れたのは2017年。フィンランド政府観光局よりフィンランドサウナアンバサダーを公認いただいたのは2018年。フィンランドを再訪したのは2019年。コロナを挟んでふたたびフィンランドを訪れたのは2022年と2023年。そして昨今はフィンランド人の来日対応も珍しくなくなりました。

しかしどれほど月日が経過しても、はじめてフィンランドのサウナに初めて足を踏み入れた2017年、日本とのサウナの違いに衝撃を受けたあの体験が色褪せることはありませんでした。その原体験が確信に変わったのは2022年の再訪時。この違いをより言語化しなければならない… もっと多くの人に日本との違いを伝えなければならない… いても立ってもいられない思いでした。

そんな折、2022年の夏に国際サウナ協会のリスト・エロマー会長から手渡された1冊の本。それこそが原著である『The Secrets of Finnish Sauna Design』でした。当時、まだ英語のコミュニケーションさえおぼつかなかった私ですが、翻訳ツールなどを用いて、不器用ながら書籍の内容と格闘を開始します。そして、本書籍に書かれた内容を国内で実践することを考えました。

当時、サウナのプロデュースでお手伝いしていたのが、サウナシュラン2023入賞の『ぬかとゆげ』。こちらではバリアフリーサウナとウィスキングサウナ、さらにフレッシュエアーの仕組みを導入するべく、原著の内容を反映しつつ、フィンランド人も視察に訪れるような素晴らしいサウナが完成しました。ただし原著の読み込みは一部に留まり、書籍全体の理解が必要でした。

このように日本語化の構想は2022年からあり、私自身の英語力やサウナ建築知識の底上げに努めつつ、然るべきタイミングを私個人は思い描いてきました。転機となったのは2023年、著者であるリッカネン氏との対面が実現し、時を同じくして、建築と言語に長けたKeiichi Kitagawaとの思いが一致したことがきっかけで、著者同意のもと、日本語版での書籍化が決定しました。
書籍化が決定してからの制作期間は半年ほどを要し、2024年の5月に発売開始となりました。以上が日本語版が出版されるに至った背景となります。
「いつ」「どこで」この本を活用したらよいか
こちらでも、私個人の見解を続けていきます。フィンランドには日本のように、サウナのことをさまざまな角度で取り上げた書籍そのものが多くは存在しません。情報が包括的にまとまったサウナ本自体が少なく、それゆえに原著の情報は目から鱗でした。複数回フィンランドを訪れましたが、私個人で数百万円はかけたであろう渡航費以上に値する情報が書かれていました…

少々大仰かもしれませんが、この本のたった数千円によって、フィンランドサウナ旅で得られる気付きが、大きく変わることでしょう。はじめてフィンランドを訪れた時、もしも本書籍を片手に旅をしたならば、きっと私のサウナ活動は大きく違ったのではないでしょうか。さらに、本書籍は読み込めば読み込むほど、新しい気付きと示唆を提供してくれることに驚くはずです。
「だれが」この本を読むことを想定しているか
サウナをつくりたい、サウナをつくる予定のあるすべての読者を想定しています。サウナをつくってもつくらなくても、本を説明書のように広げながら、フィンランドサウナのつくり方を議論し、妄想してみてください。仮に日本独自のサウナをつくることになったとしても「フィンランド人ならきっとこう考える」という目線の獲得だけでも、成果は大きく異なるでしょう。
次に、サウナをつくることを計画している事業者や建築事務所、工務店などの読者も想定しています。私もかつて、サウナをつくる際に本書の内容を翻訳し実戦に活用しましたが、実際の打ち合わせの場などで、ぜひ本書籍にメモ書きや赤入れなどをしながら、プレゼンに活用いただけましたら幸いです。事業者と支援者同士の目線合わせにもお役立ちできるかと存じます。
また、アウフグースやウィスキングなど、サウナでのサービスを何かしら提供している読者も想定しています。私個人はどちらのサービスにもそこそこ触れてきましたが、その道を突き詰めれば突き詰めるほど、サウナの仕組みへの理解やサウナづくりの次元に到達すると考えています。題名にフィンランドと入っていますが、それでも手に取っていただけると嬉しく思います。
最後に、サウナをつくる予定はないものの、サウナファンであるという読者も想定しています。前項でお伝えしましたように、本書籍を片手にフィンランドを旅するだけでも、得られる気付きは大きく異なることでしょう。発売開始してからまだ間もないものの、すでにサウナファンから購入いただいた声を聞き、大変嬉しく思っております。ぜひお手に取られてみてください。
「どのように」この本を活用したらよいか
本書籍の内容を実践しようと思うと、日本の法規や建築基準など、ハードルが出てくることは間違いありません。しかしながら、実際にフィンランドを訪れた日本人たちは、サウナの本質に触れ、創意工夫を凝らしながら最高のサウナを実現させており、私個人もそのような例を数多く知っています。本書籍のすぐれた点は、どんな地域や環境でも実現できる再現性にあります。

なるべく多くの方に本書籍が届いたら理想と考えておりますが、本の実売以上に、本書籍を参考にサウナをつくられる100、1,000の事例にお力添えできたなら、これ以上に嬉しいことはありません。日本は公共のサウナ施設数が10,000以上もある、世界的にも稀有な国です。そのうちの1,000事例、読者に手に取られるような書籍であってほしいと心から願っております。
最後に
以上、繰り返しになりますが、編集・翻訳担当の一人として本書籍に携わってきた私個人の見解を記載してまいりました。最後に、以前執筆しましたnoteでも触れておりましたが、日本は歴史柄、フィンランドよりもドイツのエッセンスを取り入れてきた国であり、昨今はドイツ由来のアウフグースの地位を確固たるものにしているのが、日本のサウナトレンドになります。
それでもなぜ、いま、『フィンランドサウナ設計の教科書』の日本語版が必要とされ、世に出ることになったのか。著者のリッカネン氏や私たちも、未だ全貌を掴めているようで道半ばであるかもしれません。最終的な評価は読者の皆さんと後世に委ねつつ、そこでようやく完成を迎えるのでしょう。その意義と真の目的は、読者の皆さんとともに作っていけましたら幸いです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
