
浅く広く学ぶことの意味
かの有名な物理学者、アインシュタインは言いました。
「いかなる問題も、それが発生したのと同じ次元で解決することはできない。」

これはどういう意味でしょうか?少し考えてみましょう。
この記事を読んでいる方の多くは、スポーツトレーナーや理学療法士、それに類する職業の方々だと思います。そこで、私たちの専門分野である理学療法から考えてみます。
理学療法とは
理学療法とは、病気やけが、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態の人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に運動、温熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いて行われる治療法です。「理学療法士及び作業療法士法」第2条には、「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えること」と定義されています。
つまり、運動やマッサージ、物理療法を主とした治療法であり、その専門家である理学療法士は人の身体の専門家と言えます。主な専門分野には、解剖学、運動学、物理学、生理学などがあります。
理学療法士は専門学校や大学でこれらの学問を基礎から学びます。
細かな部分は今回の主題から逸れるので、今回の話における理学療法士の専門分野とはこのあたりということにして次に進みたいと思います。
アインシュタインの言葉を考える

この前提でアインシュタインの言葉に戻って考えてみましょう。
「いかなる問題も、それが発生したのと同じ次元で解決することはできない。」
解剖学の範囲で発生した問題、たとえば膝の靭帯が切れた場合、それを解剖学の次元では解決できないということになります。
「膝の靭帯が切れたら手術で再建するじゃないか。それは解剖学で発生した問題を解剖学で解決しているのでは?」という反論もあるでしょう。しかし、この議論において重要なのは「解決する」という現象の定義です。
つまり、「問題」は靭帯が切れたことではなく「切れてしまった原因」であり、「解決する」とは「その原因が分かり、それがなくなること」と定義しなければなりません。
靭帯を再建することは「解決」ではなく「応急処置」に過ぎません。靭帯断裂の原因を無視して手術だけで競技復帰しても、再断裂のリスクは高いままです。
そこで私たち理学療法士は、手術後のリハビリで「患部外トレーニング」と呼ばれる膝以外のトレーニングを行い、再発を防ごうとします。体幹を鍛えたり、足首や股関節の動きを良くしたり、ジャンプや着地、走り方の問題点を探して改善を図るのです。
専門分野だけで解決は難しい

特に前十字靭帯の再断裂に関する研究は多く、さまざまな観点から再発予防の研究が行われています。しかし、現在でも再発率は8~25%で、特に若く活動性の高い選手ほど再受傷率が高いと報告されています(Wigginsら, 2016, 参考文献②)。
(システマティックレビューからの引用ですが、今回は個々の数字を厳密に議論したいわけではないのでご容赦ください)
昔と比べて再発率は下がってきているとも解釈できますが、一方で、0%にはできないと感じるかもしれません。
ここで、「0%は無理」と決めてしまうと、「問題を解決する」というアインシュタインの言葉の意味を深く考えることができません。なぜなら、「10%まで再発率が下がったなら解決した」と思い込んでしまうからです。
重要なのは、「まだ見逃している視点があるのでは?」と考えることです。しかも、それが解剖学や運動学など「理学療法」の領域以外にヒントがあるかもしれない、と考えられるかどうかです。
多くの専門家は、「自分の専門領域を深めることで解決しよう」としますが、それだけでは解決できない問題にも多く出会うでしょう。そのとき、「もっと専門領域を深める」だけでなく、「他分野の知識を取り入れてみよう」と考える姿勢も必要です。
現在はかなり心因性の問題と再発率を取り上げた研究も増えてきていますが、本当の意味で心因性の因果関係を統計的に証明することは難しいと考えています。(個別性が強すぎるため)
研究と現実の違い
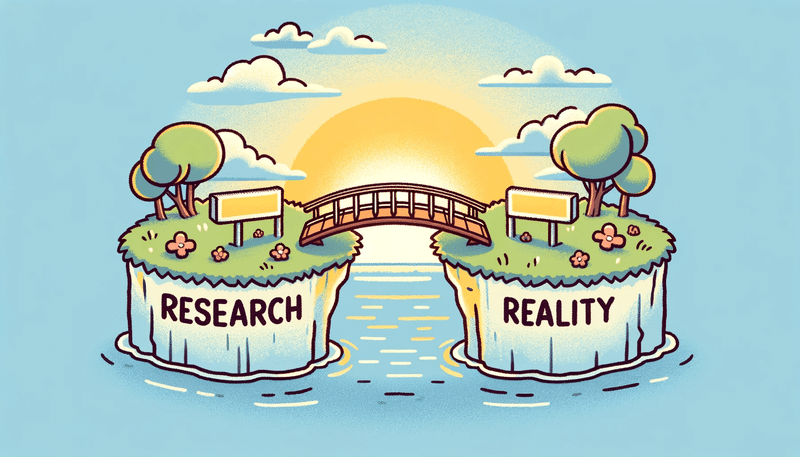
専門領域は研究によって発展しますが、現代の研究は「可能な限りバイアスを排除する」ことが前提です。つまり、あらゆる要素が関係しあっているという前提を排除することと同義です。
しかし、私たちのクライアントは複雑な要素が絡み合った一人の人間です。専門知識だけでは解決できない問題も多いはずです。クライアントの周囲には無数の環境要因が存在しているからです。
「いかなる問題も、それが発生したのと同じ次元で解決することはできない。」
この言葉の意味を深く理解するためには、あらゆる学びをやめないこと、そして実践して体験することが必要です。さらに半永久的にその定義を広げ続けます。
解剖学や運動学を別の領域として捉えるところから始まり、それらすべてを「理学療法」と捉える。
そして理学療法を含む医学全般を西洋医学と捉え、
さらに他の医学も合わせて医学と捉えます。
こうして、解剖学、運動学、生理学、物理学などを深めたら、
理学療法以外の西洋医学(内臓、循環器、呼吸器など)、
さらには東洋医学やキネシオロジー、他の民間療法なども視野に入れ、他の領域へと広げます。
この広げた領域に目の前のクライアントの問題に対する解決策があるかもしれません。
民間療法や代替療法を怪しい、詐欺だとすぐに切り捨てることは理学療法だけが絶対的に正しいと言っていることと同じなのですから。
まずは知ってみる、体験してみる、学んでみる、判断はその後からでも遅くないと思います。
専門分野だけに知識が偏ることの弊害

少し視点を変えて、専門分野については誰よりも知識があり、技術研鑽もし続けているけど、その範囲が狭いことの弊害を考えてみます。
実際にあった例を紹介します(紙面の都合上、かなり簡単に記載します)。
あるプロ選手が、両股関節のつまりを訴えていました。
最初は定石通り股関節後方のストレッチや前方のリリースなどでその場で変化はあるものの、いつも1週間程度でつまりが戻ってしまいました。
そこで少し丁寧に評価をしてみると、お腹の硬さ(腹直筋)が著明で恥骨の動きを制限しているようでした。
そこで徒手的にゆるめると即時効果は非常に高く、つまりは0になりました。
しかしまた1週間ほどすると戻ってしまいます。
これでは、「問題を解決した」とはとても言えませんよね。
そこで別の視点から「お腹の硬さ」の原因を考えてみました。
一番は「食事」の問題。
食事はどうしているのか、と話を聞いてみると
時間がなくてコンビニ食が多い、とのこと。
そこで作り置きでもいいから1週間だけでもコンビニ食をやめてみよう、という話になりました。
するとわかりやすくお腹の硬さが消え、股関節のつまりもなくなりました。本人が一番納得できないようでしたが(笑)
もちろん、実際には栄養学だけではない要素が多分に関わっているのですべての場合でこれが当てはまるわけではありませんが、専門分野だけでは解決できないというわかりやすい例ではないかと思います。
今回の例で解剖と運動学、生理学、物理療法だけの知識をいくら深めても、「1週間後に症状が戻る」という現象を解決することはできなかったと思います。
結論

専門家ほど、浅く広く学ぶことに意味がある。
専門分野は誰よりも詳しくて当たり前です。この記事は理学療法士として、トレーナーとして論文を読むことや学術書を読み漁ること、専門スキルを磨き続けることを否定するものではありません。
むしろその逆で、それらを十分にしているのに目の前の現象で困っているときこそ、他のあらゆることに興味を持ち、偏見なく事実を観察し、学び続けてほしいという願いです。
この繰り返しこそ、あなたの目の前のクライアントを助けるヒントをくれるはずです。
「自分は理学療法士だから」「柔道整復師だから」「鍼灸師だから」と学ぶ範囲を狭めることがクライアントに不利益をもたらし得ると思います。
私もその重要性に気付き、今まさに学びの範囲を広げ始めたところです。
同意していただける方は、ぜひ一緒に学びを深めていきましょう。
次回は「初めての領域の学び方」について書きたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考文献
①理学療法とは|理学療法士を知る|公益社団法人 日本理学療法士協会 (japanpt.or.jp)
②A J Wiggins et al. Risk of Secondary Injury in Younger Athletes After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Sports Med. 2016
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
