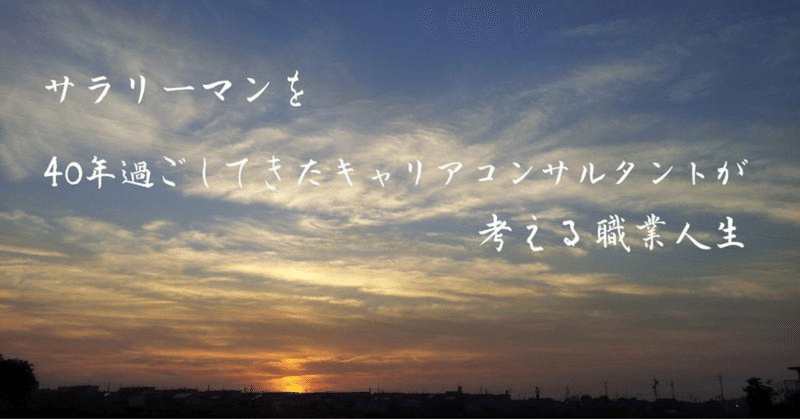
安定志向 と 変わり続けること
しばらくカウンセリングに関する話題を書いていたので、今日はキャリアコンサルタントとして普段から感じていることを語りたいと思います
今も昔も新卒事情を振り返ると、「安定志向」を求めて就活されておられる学生たちが非常に多いと感じます
そもそも学生が就職活動する際の指標となっている「安定」とは、一体どういったイメージなのでしょうか
私が新卒者への面談で直接聞くと、志望で多いのは「大企業」や「公務員」、理由は「安定」です
そして、その学生の親も「安定したところの方が安心だ」とアドバイスしていたようです
でもこれって、おかしなことだと思うのです
今の50歳代以上の方にとっては、大企業=安定した良い企業 というイメージは現実でした
しかしそれも、バブルが弾け、リーマンショックを経て、今では完全に夢物語です
私自身この40年間に、雇用の仕組みや働き方、男女格差や年金制度や成人年齢等、目まぐるしい変化に振り回されてきましたし、銀行や証券会社、建設業や重工業、家電メーカーと、世に大企業と言われていた会社の経営破綻をいくつも目にしてきました
だから今の世に「安定」なんてどこにあるの?と思っています
その証拠に、激しい競争の末新卒で「安定」した企業に入社できても、入社後3割を超える人が3年以内に離職してしまうのです
このことを考えても、今、就活されている学生の親御さんが抱いている「安定」は勘違いだとは思いませんか?
もっともこれは新卒だけの問題ではなくて、全ての方に考えていただきたい問題です
少々説教臭いのですが、「流れる水は腐らず」なのです
またこれを言い換えるなら、「世の中で変わらない真理とは、どんなものでも常に変わり続けること」だと思うのです
なので、パッと見「安定」した企業とは、「自力で試行錯誤を繰り返し能力向上に努めて、いつでも変化に対応する」人の集団で、だからこそ環境が変化しても業容が変わらず「安定」しているのだ、という実態を理解してほしいのです
また逆に、自らは変わろうとせず今の自分で満足してしまったら、周りから腐っているように見えるかもしれないのです
確かに常に向上心を持って努力し続けるなんて、考えただけでもうんざりするでしょう
無理して変わろうとしなくてもいいじゃないか、と思うかもしれません
でも、自分は変わりたくとも環境は変化し続けるので、環境に応じて自分も変化して行かざるを得ないのです
それでも頑なに変化を拒めば「腐って」しまいます もったいないです
では、どうするか
そんなに大仰に構える必要はありません
例えば「挨拶の声を少し大きくする」とか、「すれ違いざまに挨拶していたのを、ちょっとだけ立ち止まって挨拶するようにする」とか
まずは普段の行動を少し変化させてみましょう
自分が意識的に行動を変化させることで、変化することに耐性が付き前向きになってきます
なので、「最近毎日が代わり映えしないな」とか、「毎日同じことの繰り返しでつまらないな」 とか、そんなふうに感じている時は、「周りの環境が腐ってきたか」、「自分自身の認知や感覚が鈍感になっていて、周りの変化に自分が気づいていないか」をよーく点検してください
そして、もし前者なら「転職を考える」「転居を検討する」、後者なら、「通勤経路や通勤時間帯を変えてみる」「自分の生活習慣を変えてみる」「人との接し方を変えてみる」等、まずは自分で変化を起こしてみてください
自分や環境が変化することで新たな刺激が生まれ、その刺激によって新たな発見や気づきが生まれ、貴方を大きく向上させてくれるでしょう
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
