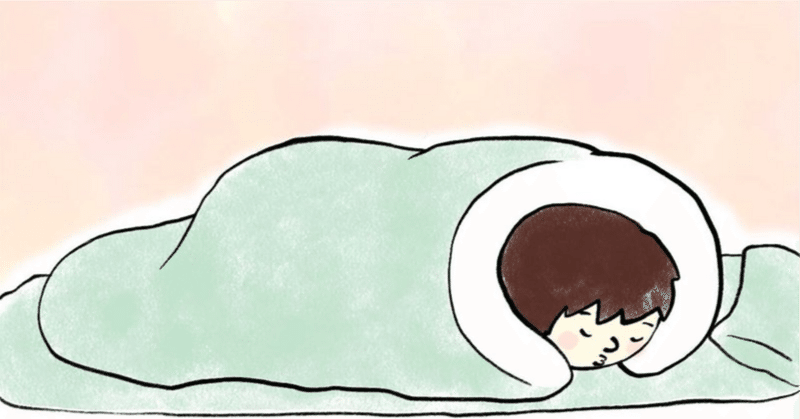
ママとパパの休む技術(1)我々は休めているようで全然休んでいない #248
先週は連休明けの疲れもあるなか、仕事を再開した矢先に、子どもの入院、妻の体調不良による医療機関との連携等と、少々ハードな日々となりました。
30代の初めまでは、こうした時に、睡眠時間を削り、ハードモードで対応して乗り越えようとしていました(いま思うと愚かすぎました、、、技術と知識が足りてませんでしたね。。)
しかし、双子が産まれてからは、短期的に無理して私自身が体調を崩すと、家庭も仕事もすべてが崩壊していくリスクがあると身を持って体感したため、
最近はハードな状態になったときには、まず自分自身のコンディションを整えることに意識を向けるようになりました。
介護、育児、仕事は長期戦です。長期間走れるための心身のコンディションを整える技術は、若いときの自分のテリトリーの仕事だけ無理して乗り切るのとは別のスキル体系です。
双子育児は親も共にぶっ倒れていきやすいハードプロジェクトですので、3年間続けていくなかで、工夫してきた健康管理について、何回かに分けて書いていきたいと思います。
今回は休むということについて最近学んだことと、工夫していることを書きたいと思います。
数々の親子共倒れ経験からの学び
休むことの大切さを学んだのは、これまでの3年間で、数々の痛みを伴う経験から学んできました。
双子と一緒にコロナに感染し、15日間のステイホームをしたこと、
双子と妻と4人でノロウイルスに感染し、バイオハザード状態の10日間を生きたこと、
双子と長男3人が順番に肺炎で入院し、自身もゲホゲホ絶不調になりながら入院対応をしたこと、
妻がぎっくり腰、ノロウイルス感染で衰弱し、体力が限界を迎えて心にもダメージが及び、産後うつを発症したこと、、
等々、数々の痛みを伴う経験をしてきました。
(もちろんそれ以上に子供や家族からら喜びと幸せをいただき、育児は楽しいと思っています!)
これらの経験を通して、ママとパパが無理をして乗り越えていくにはハード過ぎるので、親の健康管理は育児の最重要事項だと学び、
妻の主治医の産婦人科医、精神科医、看護師さんとの議論や、手当たり次第に本や論文を読みながら、健康管理についての理解を深めていきました。
精神科医から言われた「休む」の定義が凄かった
最近は特に、精神科専門医と会話する機会が多く、休みにくい環境でいかに休むかというのは、技術力がいると学びました。
本当に休むというのは、静かな環境で、まったく何もせずに、ただただ横になって楽な姿勢を取り、なーんにもせずにひたすらぐっすり眠ることだと教えていただきました。
実際に精神病院の急性期入院では、完全休養をするために、スマホも預けて、静寂な環境で快適に眠れるようにすることがもっとも大切になっています。
赤ちゃんの鳴き声などが耳から入ってしまうだけでも、睡眠の質は下がってしまいます。
あまりにも疲れている場合には、静かな環境で何も邪魔されずに寝れるように環境を整えて回復を図ることが本当に大切だと思います。
こうした休息の取り方についての知識をアップデートするなかで、寝室のカーテンを遮光カーテンにし、内窓で騒音と室内温度を快適にするなど、寝室の睡眠環境の改善と睡眠時間の確保を7時間程度確保するようにしています。
子どもを寝かしつけて一緒に寝てしまい、朝早く起きて学びや運動をするリズムを整えるようにしています。
※いろいろ試して、遮光カーテン1級を2枚重ねることで断熱と昼寝と朝の睡眠が変わります
自分のモニタリングスキルをつける見える化(コーピング)
睡眠の確保に加えて、自分の状況をモニタリングしていくことも大切にしています。
その際は、外側に出していく見える化を意識しています。
デジタルウォッチで歩数や睡眠データ、体重などを見える化することに加えて、自分の感情や困ってることを外に出していくコーピングを日常的に行うようにしています。
GoogleKeepメモに妻の看護の状況をメモしておいて主治医と看護師さんに伝えることも、自身のメンタルの健康にはとても大切な要素になっています。
また、先週であれば子どもの体調不良や病院で困ったことなども、外側に書き出すことで、精神の安定にもつながっています。
身体反応というアラート機能に耳を傾ける
外側に書き出すコーピングができていると、身体の変化にもアンテナが立つようになります。
人間は動物なので、身の危険を感じると固まったり、心臓や内臓を守るために猫背、前傾姿勢になります。
つまり防衛本能として身体にいろんな変化を生じさせて、休みなさーい!危険ですよー!とアラートを出しています。
自分にはつかれたときやストレスが溜まるとどんな身体反応が出てくるのかを理解しておき、それらが出たら早めに多めに休むようにするなど、身体反応に対して素直に対応するようにしています。
私の場合は分かりやすく口内炎ができますので、口内炎が出てきたら休みを取らないとヤバい!というアラートを基準にしています。
休むのが苦手な方は、以下のような読みやすい本や動画も活用しつつ、自分の休む技術を点検していくと良いと思います。
休むことを学ぶ動画と本
身体反応を受け入れて休むための技術を解説しておられます
書籍でも良く理解できます。
小林先生の自律神経の論理はシンプルですが強力です。
寝ることの大切さと技術はこちら
https://youtu.be/vZryxbDmPdE?si=9Mrp4HCUhesIMii9
寝不足は睡眠障害という立派な病気だと知れます。
ママとパパは毎日大変ですので、我々が倒れないように、自分のことも大切にして、長い育児プロジェクトを楽しんでいきましょう!
よろしければサポートお願いいたします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費、双子育児の挑戦に使わせていただきます!
