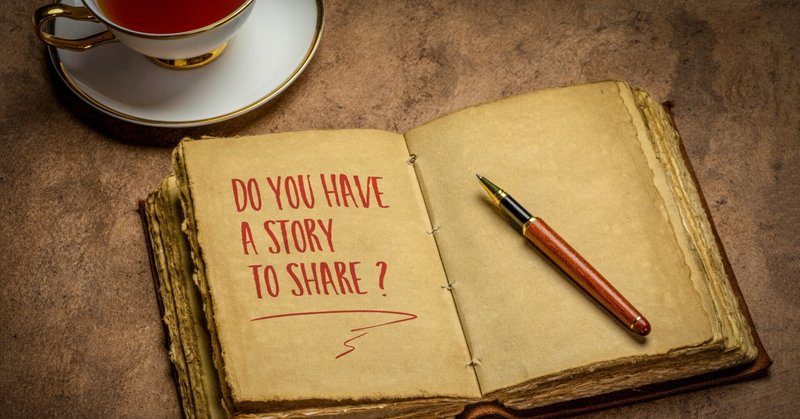
【徹底解説】キャリア構築理論とは何か?(5)3つの社会的役割:Savickas(2013)
まだまだキャリア構築理論を読み込んでいきます。もはや自己満足以外の何ものでもありません。「【徹底解説】キャリア構築理論とは何か?(2)」では、自分自身を形作ることとは人生を通じたプロジェクトであるとサビカス先生が述べていることを指摘しました。このようなプロジェクトにおいて、私たちは社会との接点を持ち続けるわけですが、(1)アクター、(2)エージェント、(3)オーサー、という三つの社会的役割を持つとサビカス先生は捉えています。
Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. Career development and counseling- Putting theory and research to work, 2, 147-183.
(1)アクター
アクターとは行動する個人であり、物語の輪郭を描くものであるとサビカス先生はしています。学校から企業を退職するまで続くものとして想定されています。行動を扱いますので、他者から見て観察可能なものであるとしています。
(2)エージェント
アクターが客観的に観察可能な行動を対象としていたのに対して、エージェントは主観的な個人による内面を含めた努力や適応を行う存在として描かれています。働いたり生活をしていれば、様々な機会が私たちには訪れます。そうした機会的な筋(occupational plot)によって探求される努力や適応に焦点が当たっています。
(3)オーサー
主観と客観の相違はありながら、アクターもエージェントもある時点における行動や適応という社会との接点を描き出すものでした。それに対してオーサーは、投影的な観点という難しい言葉をサビカス先生は用いながら、自伝的な再帰性を考察する存在であるとしています。
この再帰性(reflexivity)という言葉はちょっと難しいですね。社会学系の辞書がわりに用いている『社会学の力』で少し見てみたところ、社会学者アンソニー・ギデンズが近代化論の文脈でよく使っている概念のようです。ギデンズの原著を読む気力はないので、『社会学の力』をお借りします。
とりわけ近代に特徴的なのは、そうした再帰性が徹底的に作用し、それゆえ社会活動全般が再起的なとらえかえしの対象となってくる点にほかならない。ここでは社会的な営みがそれに関して新たに得られた情報や知識によって絶えず検討・改善され、その結果として当の営みがそれ自体、大きな変貌を遂げることになる。
サビカス先生がここまで何度か繰り返し説明されている人生の意味を構築し続けるという文脈と合わせれば、再帰性という言葉を用いた背景にも内省的にとらえかえしをしながらダイナミックに変化するという意味合いで用いていると解釈されます。
こうして物語を構築し再構築し続けることによって、私たちの経験は意味あるキャリアの物語へとパターンづけることができるとサビカス先生は述べていらっしゃるわけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
