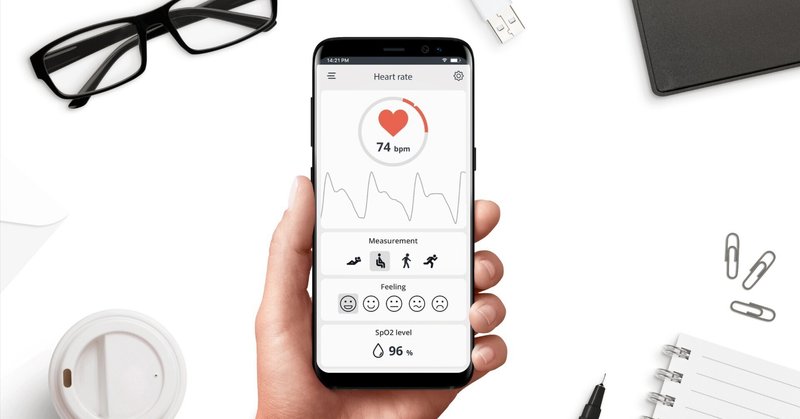
【読書メモ】ランニングエコノミーを心拍数で科学する!?:『ダニエルズのランニング・フォーミュラ 第4版』(ジャック・ダニエルズ著)
『ダニエルズのランニング・フォーミュラ』の第3章は心拍数に焦点が当たっています。なんとなくおぼろげながらの理解だったものが、解像度を上げてクリアに理解できる素晴らしい内容です。ぎっくり腰のせいでずっと走れていないため、知識だけ増えてきていてアンバランスな状況です。早く走りたいなー。
ランニングエコノミー
市民ランナーの方であれば、ランニングエコノミーという言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。ただ、その意味合いの理解があやふやなことも多く、少なくとも私は知りませんでした。
本書では、ランニングエコミーが優れているという状態を「同じスピードでも消費する酸素量が少ない」(p.71)と端的に述べています。酸素量がカギになるのですね。そのためVO2MAX(最大酸素摂取量)がランナーにとって重要な指標になるわけです。
最高心拍数を把握する
酸素摂取量と関連する指標には心拍数も含まれます。心拍数はランニング中にリアルタイムで把握しやすい指標ですので、モニターする上では有効なものです。
その上で重要なことは最高心拍数を把握することだと著者はしています。というのも、ランニング中の速度と血中乳酸濃度とは相関するのですが、それらの値と最高心拍数に対するパーセンテージとも関連するからです。
たとえば、最高心拍数が180だったとしたら、走り始めの血中乳酸濃度が少ない状態では心拍数が140で、その後に負荷をかけてきて血中乳酸濃度が高くなると心拍数が160になる、といった具合で捉えられるからです。要は、血中乳酸濃度という私たちがリアルタイムで把握できない数値を、心拍数というリアルタイムで把握できる数値によって類推できる、というわけです。
最高心拍数はアシックスのランニングラボ等で把握することができます。私の場合は173回/分と診断されました。
こうした施設で測定するのが大変な方向けに、著者は最高心拍数を測定するう具体的な方法についても教えてくれています。
ランナーが自分で最高心拍数を測定するとしたら、2分間のハードな坂道走を何本か繰り返すのが、いちばん簡単だろう。まず1本目、坂を上りきったところで心拍数を測る。2本目も同様に心拍数を測り、1本目よりも高ければ3本目を走り、さらに心拍数が上がるかどうか確認する。3本目が2本目を上回らなければ、その値を最高心拍数とみなしていい。反対に、3本目が2本目を上回ったら、4本目を走る。とにかく、前の1本よりも心拍数が上がらなくなるまで繰り返す。もし坂道がなければ、800m走を速いペースで何回か繰り返すだけでもいい。そして坂道走と同じように、前の1本と心拍数を比べる。
このような現実的なtipsを載せてくれているのも本書のありがたい点です。
心拍数を取り巻く注意点
心拍数の把握は大事ですが、注意点もいくつかあります。第一に、気温が高い状況では、通常と同じ速度で走っていても心拍数は高くなります。
第二に、安静時心拍数もコンディションを把握する上での重要な指標になります。トレーニングで心肺機能が強化されると朝目が覚めた直後などの安静時の心拍数が徐々に低下します。つまり、安静時心拍数が低下していくことは心肺機能が強化されているということを意味していると考えられるのです。
他方で、安静時心拍数が通常よりも高い時は、オーバートレーニングの兆候であるなどなんらかの身体の不調の可能性があるので要注意だとしています。健康的に走るためには意識したい点です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
