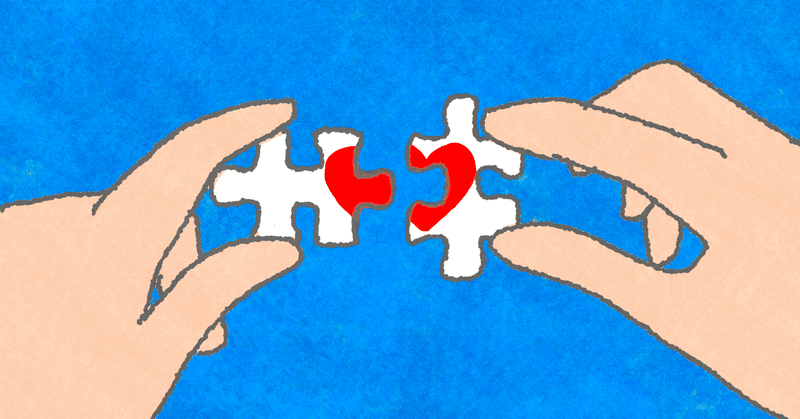
旅先の食で迷うとき:旅先の食との相性について
「食物アレルギーの回避」は全てに優先される
旅先で何を食べようか?と考えた時に、まっさきに除外しなければならないのは食物アレルギーの出るものです。
食物アレルギーを持つ人、あるいは若い人ほどこれは常識となっていると思いますが、高齢になるほど食物アレルギーを好き嫌いと混同する人が増えると感じます。旅行の同行者が暮らしをともにする相手ではない場合は特に、理解度を確認しておくと無難でしょう。
その他、牛乳に含まれる乳糖でお腹を壊す人(乳糖不耐症)、熱を通していない山芋が苦手な人(肌につくとかゆくなるシュウ酸カルシウムや、アレルギー風の症状を出す成分も含まれるとのこと)も、注意が必要でしょう。
初めて食べるものに対しては、その料理の食材を確認しておくと安心です。
好き嫌いの中で、もし「これを食べるとなんとなく具合が悪くなるから好きではない」というものがある場合、体質が受け付けていないので無理はしないでください。
嫌いなものを無理して食べる必要はない
旅行において、食というのは手っ取り早く「現地」を感じられる手段です。
ですが、それが旅行の楽しみの全てでもありません。
街並みがまとう空気感、展望台からの美しい眺望、大都会でしか手に取って買えない本、祭りの熱気など、体験できるものはその他にもあるからです。
例えば、かまぼこが苦手な人が、かまぼこで有名な神奈川県小田原市でわざわざかまぼこを食べる必要はありません。
ただ一方で、「小田原のかまぼこの歯ざわりなら食べられた」というようなケースもあります。完全に避けてしまうとこういうものは逃してしまう可能性が出てきます。
これをどう考えるかはあなた次第ですし、もしこの「食べられた」ケースを逃したくないなら、自分の好き嫌いを細かく分析する必要があります。
自分の「嫌い」の姿を把握しておく
「嫌いな食べ物」とひとことで言っても、人によって、または食べ物によって、相当に細かな違いがあります。
五感のどこかで引っかかりを覚えるケースであれば、そのどこにひっかかっているかが重要です。聴覚の影響はあまりないでしょうから、残りの4つで例を挙げます。
・味覚:特定の味が駄目(苦い、辛い、酸味など)、味付けの濃さが合わない
・嗅覚:食材の香りが駄目(磯臭い、青臭いなど)、料理の匂いが混ざると駄目
・視覚:色合いが悪い、気味悪さを感じる形
・触覚:口の中で触れた感触が気持ち悪い、歯ざわりが苦手、喉を通る感覚が嫌
また、好き嫌いには「トラウマ」という軸もあります。
特定の食材を強要されたり、具合が悪くなって(「貝にあたった」など)以来食べていないなどです。
数日の旅であれば、これらを我慢してまで、地元のものにチャレンジする必要はありません。下手にチャレンジして結局拒絶する方が、地元の方に失礼ですらあります。
そのうえで、地元の味に敢えてチャレンジしたい場合については、この料理(または類似した料理)が嫌いな理由を踏まえて検討しましょう。
例えば北国住まいで「塩味が濃すぎて嫌」なら、塩味が薄く出汁を効かせた関西の味付けなら食べられるかもしれません。
子供の頃食べたピーマンの苦味が駄目だった、という人は(これは味覚が鋭敏な子供時代によくあることです)、苦味が少ないピーマンの産地でなら肉詰めを美味しく食べられるかもしれません。
反対に、セロリのようなどう調理しても独特な芳香と味が残る食べ物が駄目な人は、食べることを諦めた方が良いでしょう。(食べられる者からすると「そういうところが美味しい」のですが…。)
このような見極めをしておくことは、旅行先はもちろん、普段の食生活を充実させることに役立つでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
