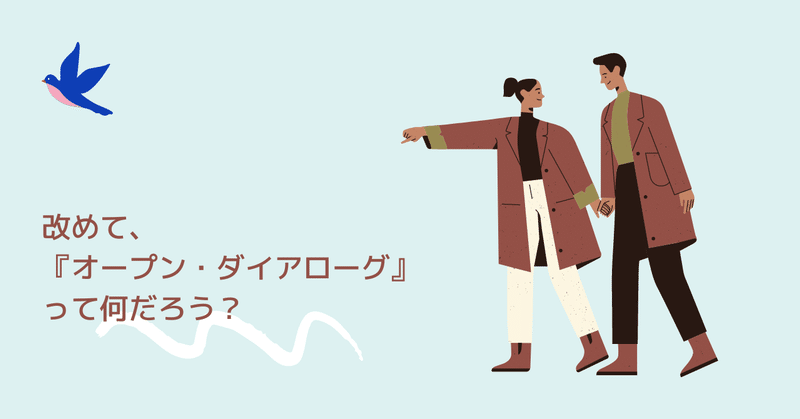
改めて『オープン・ダイアローグ』って何だろう?
こんにちは、対話スペースけやきのきよこです!
『オープン・ダイアローグって何ですか?』
と尋ねられたとき、皆さんはどう答えますか?
一般には『開かれた対話』と訳されますね。
開かれた、というのは、『医師と患者』というような限定された関係でする会話ではない、という意味があります。
しかし、その他にも、『オープン・ダイアローグってこういう物』というような概念を表す文章って、色々あるなあと感じます。
ちょっと一言で説明するのは難しいかもと思いました。
今日は『オープン・ダイアローグとは何か』について、良く取り上げられるコンセプトや、私の学び・経験などから改めて考えてみようと思います。
7つの原則
オープン・ダイアローグについて理解しようとする際に良く取り上げられるのが、次の「7つの原則」です。
(出典:ODNJP『OD対話実践のガイドライン』)
1.即時対応:必要に応じてただちに対応する
2.社会的ネットワークの視点:クライアント、家族、つながりのある人々を 皆、治療ミーティングに招く
3.柔軟性と機動性:その時々のニーズに合わせて、どこででも、 何にでも、柔軟に対応する
4.責任を持つ:治療チームは必要な支援全体に責任を持っ て関わる
5.心理的連続性:クライアントをよく知っている同じ治療チ ームが、最初からずっと続けて対応する
6.不確実性に耐える:答えのない不確かな状況に耐える
7.対話主義:対話を続けることを目的とし、多様な声に耳 を傾け続ける
いかがでしょうか?
どれも、オープン・ダイアローグを実践する際に大切な事のように思えます。
しかし、対話スペースけやきではこれら全てを守っての対話実践を行うことはしていません。
例えば、ご参加頂く方の可能な日時で行っているため『即時対応』は『可能な範囲でなるべく早く』になっています。
『社会的ネットワークの視点』についても、ご家族や知人の方、治療に携わる方などをいきなり連れて来て頂くという事は難しく、そのため相談者さんお一人からお話をうかがっていく事が多いです。
オープン・ダイアローグは、生まれた当初、フィンランドの公立病院で急性期の精神疾患の治療に用いられていました。
しかし、その後日本でのオープン・ダイアローグの展開としては、斎藤環さんが行っておられる『引きこもりダイアローグ』などを代表として、医療ではない所でも価値を認められるようになってきています。
引きこもりや不登校などの中にある社会と個人のずれの解消や、疾患には至っていない場合の予防的なメンタルヘルスケア、家族・職場などでの対人関係の悩みの解決、教育や福祉の場面など、さまざまな問題解決に応用されています。
それら応用的なオープン・ダイアローグでは、精神医療の場で用いられるときと同じような原則が必ずしも重要ではない場合もあると私は考えます。
もしかすると、もうすでに他の原則がある実践グループもあるかもしれません。
また、オープン・ダイアローグの開発者の一人であるヤーコ・セイックラ氏は、こう述べています。
『オープン・ダイアローグというのは対話なんだ。オープン・ダイアローグを学ぶとなったときに、7つの原則から説明がなされることがあるが、それはオープン・ダイアローグの本質ではない。』
7番目の原則にも『対話が続く事が目的』とあります。
オープン・ダイアローグでは対話が続く事が最も大切な価値です。
7つの原則は重要な共通の理解としつつ、各対話の場では可能な範囲で取り入れていく、という現場的な実践が必要なのではないでしょうか。
対話が続くために必要なもの
では、対話が続いていくためには何が必要なのでしょうか?
私はこれまで色んな場でオープン・ダイアローグについて学んだり、対話実践で感じた事から、次の2つが大切だと考えています。
平等で安全・安心な対話を目指すこと
社会心理学者のエドガー・シャインは1965年の著作で『個人が安心して変われると感じるためには、心理的安全性を作り出す必要がある』と記述しています。(Schein&Bennis,1965)
その後も複数の研究者が、心理的安全性は個人の進歩や組織の協同に重要であると述べています。
(例:ウェイリアム・カーン、エイミー・C・エドモンドソン)
オープン・ダイアローグの対話の場では、初対面の人と一緒である事も多くあります。
そのような場所で自分の気持ちを表現したり、個人性の高い話をするためには、心理的安全性の担保は不可欠です。
地位や立場を超えて自由に発言し合うことができる雰囲気がそこにある、と感じる事で自分を自然に表現したり、また心の奥から深く聴く事ができます。
オープン・ダイアローグに参加するようになって間もない方は、最初は心理的安全性を感じる事が難しい場合もあるでしょう。
オープン・ダイアローグを行う前に、
・批判や否定、説得はしない
・対話の内容は外部へは持ち出されない
と言ったコンセプトを確認し合う作業が必要です。
お互いの存在・発言への尊重
オープン・ダイアローグでは『お互いは別個の人間であり、分かり合う事はない』と考えます。
冷たい感じもしますが、分かる部分もあれど自分とは違う心を持つ相手だととらえ、興味を持って話を聴き続けたり問いかけていく事が、話す人・聞く人それぞれの心の自由を担保するためには必要です。
また、オープン・ダイアローグではそれぞれの発言全てに平等な価値があるとします。
そして、沈黙にも同様に価値があり、尊重されるべき物です。
沈黙は、話している方の考えが大きく動いている途中に起こったり、あるいは感情の表現だったりもします。
参加者全員でその間を大事に待つ事で、対話をより豊かに育てる事ができます。
しかし、時には対話がいつの間にか心理的安全性が脅かされるような危機にあったり、心の傷に触れて非常に辛くなっている、などのネガティブな理由で沈黙が起こっている場合もあります。
そのような良くない沈黙を防ぐためには、ファシリテーターなどが対話全体を把握し、確認しつつ対話を進める必要があります。
実践してこそ分かる部分も
今日は、オープン・ダイアローグって何なのか、7つの原則やその他必要なコンセプトを並べて考えてみました。
対話は人間の活動であるため、スポーツや自動車の運転などと同じで、一通りやり方を学んだ後は実践してみる必要があります。
対話実践に参加する事で、オープン・ダイアローグについてより深く理解したり、新しい発見があったりです。
現在、全国各地に色んな個性のあるオープン・ダイアローグ実践グループができて来ています。
対話スペースけやきとしても、全国に仲間が増えるのが嬉しいです。
SNSなどで発信されているグループも多いです。
良かったら参加してみてください。
〈オープン・ダイアローグについて〉
フィンランドで考案された対話メソッドです。
対等な立場でお互いに敬意を持ちながら「聴く」「話す」を続けていくと、本人の中から自然と改善や回復が湧いてきます。
元は精神疾患の治療法として生まれましたが、
現在では福祉や教育、会社組織など色々な場所に広まりを見せています。
★対話で話された内容は外部へは持ち出されません
★対等な立場で行う、安心・安全な対話の場です
★対話中のどんな一言にも、沈黙にも価値があります。
対話スペースけやきは広島県福山市を中心に、オンライン・オフラインで対話実践やオープンダイアローグに役立つ勉強会を行っています。
下記公式LINEにコミュニティの概要や開催予定などを掲載しています。
ご興味のある方、ご質問のある方は、どうかお気軽にお問い合わせください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
