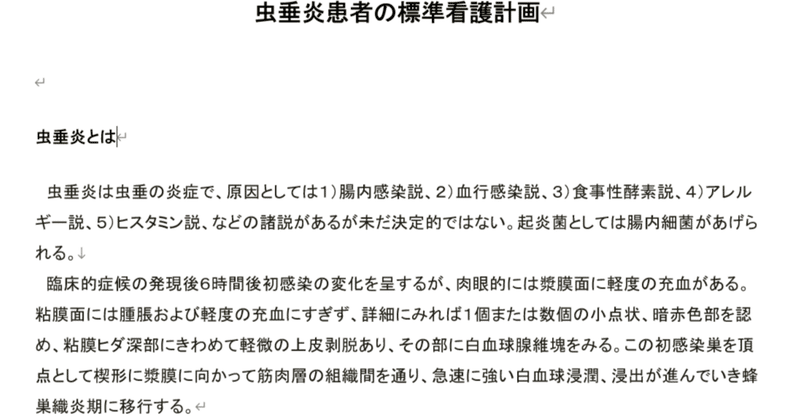
看護計画テーマ「虫垂炎患者の標準看護計画」
いつもお疲れ様です。
実習中、挨拶しても無視されることはないですか?
あるあるネタなので、実習後は笑い話になります。辛いと思いますが気にせず乗り切りましょう。
今回は虫垂炎についてです。
早速まとめていきましょう。
虫垂炎患者の標準看護計画
虫垂炎とは
虫垂炎は虫垂の炎症で、原因としては1)腸内感染説、2)血行感染説、3)食事性酵素説、4)アレルギー説、5)ヒスタミン説、などの諸説があるが未だ決定的ではない。起炎菌としては腸内細菌があげられる。
臨床的症候の発現後6時間後初感染の変化を呈するが、肉眼的には漿膜面に軽度の充血がある。粘膜面には腫脹および軽度の充血にすぎず、詳細にみれば1個または数個の小点状、暗赤色部を認め、粘膜ヒダ深部にきわめて軽微の上皮剥脱あり、その部に白血球腺維塊をみる。この初感染巣を頂点として楔形に漿膜に向かって筋肉層の組織間を通り、急速に強い白血球浸潤、浸出が進んでいき蜂巣織炎期に移行する。
アセスメントの視点
合併症として、穿孔性腹膜炎が最も多く、その他イレウス、肝膿瘍、腎孟炎などが起こり安いため、穿孔や腹膜炎の症状を注意深く観察する必要がある。
症状
腹部痛
上腹部及び臍周囲の腹痛を訴え漸次回盲部に限局し、またときには最初から回盲部に腹痛を訴える。
消化機能
嘔吐、食欲不振、便秘と排ガスの欠如
身体所見
微熱
39度を越えない
腹部
回盲部における圧痛点にはマックバーネ点、ランツ点、キュンメル点などがあり、疼痛特殊症状としてはブルンベルグ徴候(回盲部を少しづつ深く圧し手を急に離す時に疼痛がある)、ロプシング症状(下行結腸を圧し、大腸ガスを盲腸に逆行せしめる時回盲部に疼痛を発する)、ローゼシュタイン症状(左足でマックバーネ点を圧すれば疼痛著明となる)などがある
体位
腹壁の緊張を除くために膝を曲げている。
検査
腹部レントゲン写真
尿検査
白血球(10,000 〜16,000 )
治療
1.保存的療法
薬物療法(ファロスポリン系、アミノベンジルペニシリン系など広範囲の菌に効く
抗生剤の投与
2.観血的療法
虫垂切除術
術後経過と管理
1.疼痛管理
鎮痛剤の筋注で管理
2.食事
手術第1病日より開始
3.安静
手術第1病日より歩行可
術後合併症
出血
腰椎麻酔で手術した場合、悪心、嘔吐、頭痛の有無に注意する
ドレーン挿入の場合は排泄量性状の観察をする
看護計画(術前)
.アセスメントの視点(術前)
突然の入院のことが多いため、不安の除去を図り、手術を受け入れられるように援助する。激しい腹痛時は、下肢を屈曲させ側臥位とする。下剤の投与、潅腸は原則としておこなってはいけない。
.問題リスト(術前)
♯1.安楽の変調:腹痛
〔要因〕・虫垂の炎症による腹膜刺激症状(単純、急性、化膿性、壊死性)
♯2.術前不安
〔要因〕・疼痛
・緊急入院
・診断のための検査や各種処置に対する情報不足
・手術への不安
.看護目標(術前)
疾患や手術に対する不安が軽減され、手術に向けて精神的準備がてきる
全身状態を整え、手術に対する身体的準備ができる
.看護問題(術前)
♯1.腹痛
・痛みが緩和したことをことばで表す。
穏やかな表情になる。
>手術前日
O−1.痛みの部位と強さの変化
2.痛みの特徴と経時的変化
3.血液データ
4.ショック状態の前駆症状(全身の脱力感、疲労感、皮膚蒼白、冷汗血圧低下
T−1.安楽な体位
2.体温、血圧、呼吸数、脈拍の測定
3.指示された輸液量を滴下し、水分出納・電解質バランスをチェックする。
4.症状の推移によっては、緊急手術となるため、その準備をする。
E−1.腹痛が強くなった時には我慢せず、訴えることを指導する。
2.ショック症状について説明し、その兆候の出現時にはただちに医師や看護婦に伝えるよう指導する。
3.安楽な体位について指導する。
#2.術前不安
・不安がなくなったことをことばで言える。診断のための検査の必要性がわかり納得できたことを表現できる。
術前から術後の自分の状態がイメージでき、対処方法を言葉で表現できる。
普段通りの言葉や態度での日常生活行動をとることができる。
>手術前日
O−1.疾病、術前検査、手術、術後の経過に関する患者の情報量とその理解度
2.言葉による表現、表情、態度の表出状況と不安の程度との関係
T−1.術前検査の説明や術前オリエンテーションを落ち着いた状況で説明
2.心配や不安に対し誠意をもって対応する。
3.睡眠が障害されている場合は、医師と相談の上睡眠剤を使用するとともにその効果を確認する。
E−1.術前検査や術前・術後の処置について、タイムスケジュールも含めてわかりやすく説明する。
2.検査や手術に対する心配や不安について、それらを訴えてよいこと、また受けとめる用意があることを伝える。
3.必要時、鎮痛剤や眠剤が使用できることを伝える。
看護計画(術後)
.アセスメントの視点(術後)
腰椎麻酔のため、随伴症状に注意する。
.問題リスト(術後)
♯1.安楽の変調:創痛
〔要因〕・手術による皮膚組織の損傷
・麻酔の覚醒
・創部の炎症
#2.安楽の変調:頭痛
〔要因〕・腰椎麻酔による脳脊髄圧の低下
#3.セルフケアの不足:清潔、排泄、移動動作
〔要因〕・鎮痛剤使用による活動性の低下
・術後の疲労
・治療、処置による行動制限
.看護目標(術後)
創部の癒合が良好となる。
.看護問題(術後)
♯1.安楽の変調:創痛
・疼痛がない、または、緩和されたことを、言葉で表現することができる
・穏やかな表情になる
・活動範囲が広がる
>術後3—4日
O−1.疼痛の有無と程度
2.痛みに対する言葉の表現
3.バイタルサインの変化
T−1.医師の指示に基づき鎮痛剤を与薬する。
2.気分転換の活動
3.背中をさする
4.疼痛による苦痛や不安を表出できる雰囲気をつくる
E−1.回復の一過程であることを伝える
2.疼痛時あるいは前駆症状のある場合、医師や看護婦にすぐ伝えるように説明する
#2.安楽の変調:頭痛
・頭痛が消失したことを言葉で表す
>術後4—5日
O−1.頭痛、吐き気、悪心の有無と程度
2.言葉による頭痛の表現
3.活動の範囲
4.頭痛に対する非言語的表現(苦痛様顔ぼう)
5.鎮痛剤、補液が行なわれていればその効果
T−1.頭痛を予防するため、以下の非薬物的な方法を実施する。
2.頭部をやや低くした体位の保持
3.頭部の冷罨法
4.症状出現時は医師の指示に基づき鎮痛剤、補液を行なうとともに、その効果を確認する。
E−1.症状出現時には安心させるために以下のことを説明する。
・麻酔の影響であること
・症状の程度や持続期間には、個人差があること、等
2.症状出現時は、臥位で静かに休み、症状が軽減してから行動するよう指導する
#3.セルフケアの不足:清潔、排泄、移動動作
・セルフケアの必要性について認識できたことを言葉で表す
・活動を広げることへの恐怖心が消失したことを言葉で表す
O−1.以下のことをアセスメントする。
・日常生活における活動可能な範囲と規制に関する認識度
・性格傾向
・サポートシステム
T−1.患者に代わってセルフケア満たす行為をある程度行なう
2.患者のセルフケア能力を活用する
3.患者が質問しやすい雰囲気をつくるとともに質問には丁寧に対応する
E−1.術後経過に合わせて活動の範囲を広げていくことが機能回復に役立つことを話し、セルフケアをすすめる。
2.日常生活に自信がもてるように指導する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
