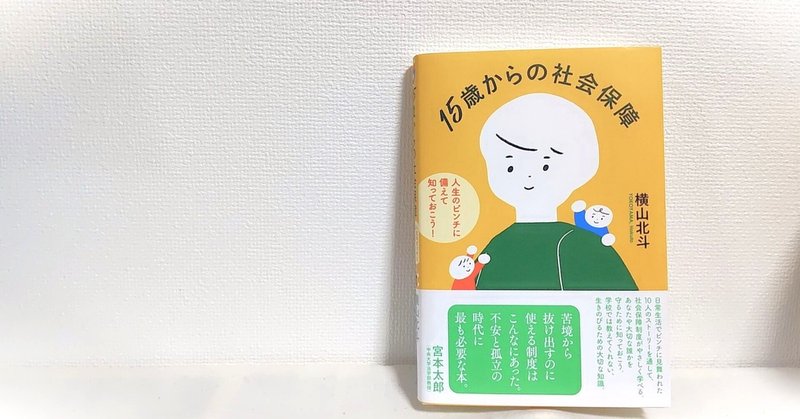
「わたし」で居続けることを支えるために必要なもの
私はこの本を、子どもの習い事の待ち時間に、カフェで読んで大泣きした。なんてことないふりをしながら読めないくらいには十分に泣いてしまいそうだったので、途中で本を閉じ、途中からは家で読んだ。
同じソーシャルワーカーの方が書いた本で、この本が出ることになった、という時から知っていたので、ぜひ読みたいと思い、予約をしていて家に届いた本だった。

いろいろな社会保障制度があるけれど、日本では、その制度を知っていないとなかなか使えない。
病気で休まないといけなくなった時に、傷病手当金をもらえるとか、家族に介護が必要になった時にサポートしてもらえるとか、そういう社会保障の制度があることをそもそも、教えてもらえないから、使い方も知らない。
福祉、とか制度、とか言葉はなんとなく知っていても、それが自分とどう繋がるのか、必要な状況になるまではピンとこない。
そしていよいよ必要になった時にも、自分とは遠い存在だったはずの福祉制度に触れることに躊躇したり、人からの見られ方が気になったり、制度自体が書類の提出など複雑な手続きが必要だったりと、ハードルがいくつも存在する。
私は、この本が、中学生が読んでもわかるくらい、読みやすく書かれた制度紹介の本だと思っていた。そう思って読み始めた。
が、大きな間違いだった。この本は、単に社会保障というものを広めるための本ではなく、「なぜ社会保障が大切なのか」を伝える本だと私は思った。
いつの間にかやってきて、自分でもわからない。
この本では、いくつもの「困りごと」に出会った人たちが登場する。会社でハラスメントに遭い、適応障害と診断される20代の女性。持病があり、学費に悩む大学生。事故に遭い、働き方を変えざる得なくなった男性などだ。
それぞれ、元は平穏な日常を送っていて、事態はいつの間にか変わっていく。身体や心の不調や、お金のこと、人間関係、日々の暮らしにまで影響を与えはじめ、平穏な日常と違ってしまった「今」に気づく。そして、その過程で、その人自身の何かもいつのまにか変わっていく。その人の存在自身が、何かに削られ、傷ついてしまうのだ。
そんな時、さまざまな場でソーシャルワーカーは、声をかけ、話を聞きねぎらい、「こんな制度がありますよ」「頼ってみてはどうですか」「もし~だったら、こんなことも知っておくと役に立つかもしれません」と情報提供をする。
最初は躊躇する人も、そんな制度があるならちょっと相談してみようかな、と申請の手続きをしはじめる。
そうした制度を知り利用していく過程で、その人自身の削られ、傷つけられていた何かにも、傷薬が塗られ、絆創膏で守られ、徐々に癒されていく変化があることが伝わってきた。
それは、「その人がその人でいること」の回復の過程だった。その人が生きていくために、最低限必要な、削られてはいけないとても大切なもの。
それは目には見えないし、普段は意識していないから自分でも分からない。
だけど、ひとたび傷つくと、とても痛いしひりひりする。痛みを自覚するレベルの傷になってしまうと、治るのにも時間がかかる。
そうした状態を、その人がその人でいられる状態になるまでの回復をサポートしたり、その人らしく居続けるためにあるのが「社会保障制度」なのだ。
時には安心して家に住めるように、時には適切な医療が受けられるように、時には学校に行き、自らが思い描く将来を歩めるように、さまざまな社会保障制度がある。
そうした制度を利用して、いつの間にか自分自身でいられなくなってしまった、ひりひりする今から脱し、自分の人生の主導権を自分に取り戻し、また自分の人生を歩んでいく。それは、最低限、誰にでも「保障」される生き方なのだ。少なくとも、この国はそれを一番大切なものとして位置付けている。
そのこと自体は、みんな義務教育で習う。日本国憲法、とか基本的人権の尊重、とか、テストの穴埋めで暗記したことば。
ただ、その言葉の意味を、守り方を、教えてはもらえない。基本的人権が傷ついたとき、その人がその人であるために必要なものが何らかの形で零れ落ちたり、奪われたり、なくなったりしたとき。
その人が生きていくために、最低限必要な、削られてはいけないとても大切なもの。それは「尊厳」と呼ばれるものだ。かけがえのなさ、大切な存在であること、それが誰からも何からも否定されないこと。
職場でハラスメントを受けたとか、配偶者から暴力を受けたとか、何かのアクシデントで心身に大きな傷を負ったとか、家族のケアのために子どもが学ぶ時間を持てないといったことは、全部、この尊厳が傷つけられた状況なのだ。
社会保障は、生きる、暮らすという現実を支えるだけではなく、外からは見えにくい個人が抱えた傷ー尊厳の回復を強く後押しするものだ。
本にある後半のケースに、家族のケアを担っていた中学生が、学習支援を受け塾に行けることを「やった!」と喜ぶ場面があった。
その人がその人らしくあれる基盤が整えば、おのずと人は自分の力を発揮できるようになり、自分の人生を希望を持って歩きだすことができる。
社会保障は、「わたし」で居続けることを支えるためにある、一人残らずみんなが使える制度であり、権利だ。
***
このnoteには、ハッシュタグに、この社会保障が使える可能性がある、この本にも事例として載っているキーワードの一部をつけました。
もしかすると、自分にも使える社会保障制度があるかもしれない、と感じられた方は、この本の著者である横山さんが代表のNPO法人 Social Change Agencyで、制度を探せるチャットボットが作成されています。こういった情報提供も、本にあるようなサポートも、ソーシャルワーカーなどの福祉支援者が行っています。
必要な人に、必要な時に、必要なサポートが届いていく社会になりますように。私も、いちソーシャルワーカーとして、このnoteに綴ります。
読んでいただきありがとうございます* 役になったなと感じたnoteがあればおススメやシェアで応援していただけると嬉しいです。 自分らしい、体温のある生き方が広がりますように。
