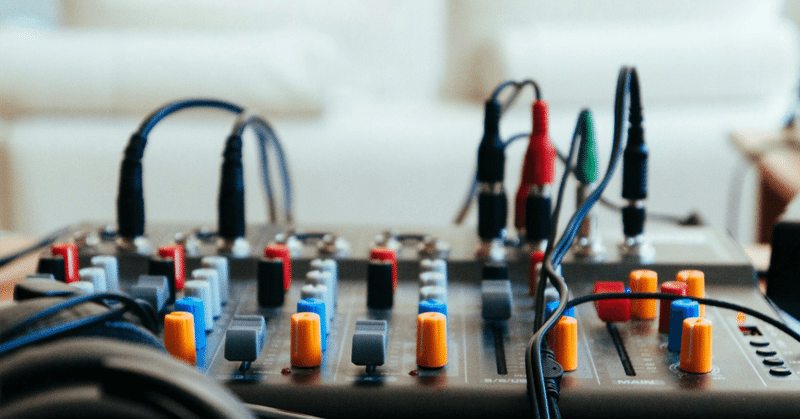
ミックスの下準備 サンプルレートの設定・ゲインステージングなど
ミックスの手順を紹介
特にこれといった実績や自慢できることはありませんが、自分好みのポップロック・オルタナティブロックなサウンドを自由にカッコよく操れるようになったので是非参考にしてほしい!
使用ソフトはCubase12 ジャンルはポップロック
エンジニアにミックスをお願いすることもありましたが、素材感のコントロールが時間内に出来なかったり、後から参考にしたいサウンドが出てきたりして自分が求めている要素・やりたいことを柔軟に取り入れることができなかったり、修正のための費用がかさばったりした経験から、自分でミックス・マスタリングまで行うことに決めた。各パートの素材感を最大限引き出すにはどうしたらいいのか。。今回は自身のミックスのマニュアル化と、使っていただけることを目的に書いていく。参考にしていただけると、とても嬉しいです。
曲は全て完成している状態、後はミックスのみという状態からの手順です。

サンプルレート・ビット深度の設定
通常は44.1kHzや48kHz
ビット深度は、通常は16ビットまたは24ビット以上であればギターロックなサウンドなら問題なしの印象。写真やイラストの編集と同様に、高解像度は低解像度に落とせることができるが、低解像度は高解像度にできないという意識があればいいと思います。なので、48kHz 32bit float形式を使うことが多い。
仮のギターでもそれが本ちゃんの音源になる可能性があるので、ラフ段階でもその形式を使う。
ソフト音源のオーディオファイル化
ソフト音源はオーディオファイルに書き換え無音部分はカットもしくはフリーズにする。シンセ動かしながらのミックスは負荷がすごく、Cubaseが落ちないようにするための対策
この段階では、midiのオートメーションやクオンタイズ、ベロシティの調整は終わっている状態
クオンタイズ・ベロシティの調整忘れをこの段階で気づかないように完璧に仕上げておきたい
トラックの整理
作業しやすいようにフォルダ名をパートごとの名前にして、Busトラック・各トラックの順に整理しまくる。音量バランス・センド量を一括でコントロール



僕は
Drums オレンジ
Bass amp DI sub bass青
guitar 水色
guitar クリーントーン エメラルドグリーン
ヴォーカル・コーラス 黄色
FX(AUX) 空間系 パラレル処理 赤
のようにしている。初めてシーケンサーを見る人にも説明しやすくして、曲作り・アレンジをすぐに始められるようにしている。
ゲインステージング
【DTM】ミキシング時のマスト処理!?「ゲイン・ステージング」とは?
プラグインにかかる適切な音量(スウィートスポット)がよくなる。
アナログをシミュレートしたプラグインとかに効果がすごい。
VUメーターを使うので、ゲインステージングをした後も、プラグインを指す前・後の音量調整としても使用できる。
ゲインステージングはミックス前に波形を整えること。基本的にはVUメーターが、0db になるようにする。はみ出てもいいから、0db 中心として振れるくらいがちょうどいい。動画を参考に!

プラグインインサートで「supervision」検索
▼
signal のところのVUを選択
▼
歯車アイコンをクリックしてscaleのVUdbFSを選択
インサートの最後の方に入れることで、コンプやEQを入れた後も音量の振れ幅を確認しやすくなるのもコツ
各楽器の参考レベル ギター・ベース アンプシミュレータを入れた後にVUメーターで確認 0db 中心として振れるくらい。 アンシミュ前の音が割れてたりしても、意図的なことが多いので、あまり気にせずアンシミュの最後のマスターでゲインステージングを行う
固いピアノやクラップなどのトラック ピークが0dbになるように合わせる
ドラム🥁などアタックが強いトラック VUメーター -6dbくらいに。Cubaseのノーマライズ機能を使うのも早いですね
クリックトラック・コードトラック・リファレンストラックの用意
ミックスを行う際にリズムやテンポを維持するために、クリックトラックを用意
ミックスの参考として、似たような音楽やアーティストのトラックをリファレンスとして用意することも一般的 2、3個あれば音量感や素材感、目指す完成像に迷わず、近付くことができる気がします。曲作りの際は、全くジャンルの違う大好きな曲を入れておくと、閃きが増える気がします
本格的にミックスに入る前に、プリミックスで各楽器のバランスを取っておく
リファレンストラック3つほど作成し、聴き比べながら各パートの音量を調整
好きな曲・目指したい音楽の正解と聴き比べながらやるため、迷いが少なくなる。
個人的には、バスドラ・ベース・ボーカルのトラックを同じくらいにして、最近流行りの低域に重心があるクリアで現代的なサウンドを目指したい。
以下にいくつか最高な曲を載せておきます!僕が今風だと感じている音量感だけ参考にしてみてください。
バンドサウンドを作っているのですが、EDMやダンスミュージックの音量感が参考になる時があります。ぜひいろんな曲の音量感と比べながら制作してみてください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
