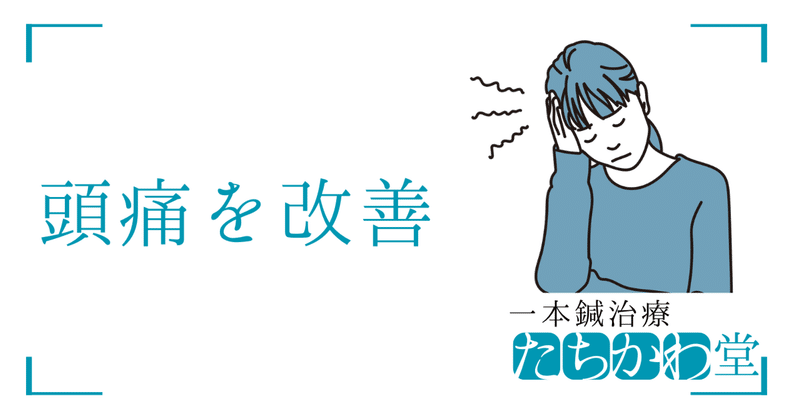
頭痛を改善したい!原因と種類、予防と治療方法を解説
ズキズキ痛んで仕事に集中できない…痛くなったら薬を飲んでの繰り返し…など、頭痛に悩む方は多いのではないでしょうか。
ここでは頭痛の原因と種類について整理して解説するほか、症状別の予防方法、治療方法を紹介します。
頭痛の原因と種類

頭痛の原因と種類は大きく慢性か急性かに分けられます。
慢性頭痛(一次性頭痛)
急性頭痛(二次性頭痛)
原因がはっきりせず、他に原因となる病気のない頭痛を「慢性頭痛」や「一次性頭痛」と呼んでいます。一方、病気などの原因によって引き起こされる頭痛は「急性頭痛」や「二次性頭痛」といい、見逃すと大変なことになってしまうケースも。
順番に解説していきます。
1.慢性頭痛(一次性頭痛)

繰り返し起こる慢性的な頭痛のことで、はっきりした原因や疾患が見当たらないものを「慢性頭痛」や「一次性頭痛」と呼んでいます。
A.筋緊張性頭痛
もっとも多くみられる頭痛。その名の通り、首、肩、背中の筋肉のコリや緊張が原因で起こる頭痛です。
頭全体に痛みが出たり、後頭部と首の付け根部分が締め付けられるように痛んだり、眼の奥に痛みが出るなど、痛みの出方は様々です。
主な原因
パソコンを使用したデスクワークやスマホの見過ぎ、またはストレスによって首、肩、背中の筋肉のコリや緊張によって引き起こされると考えられます。特にデスクワークの方は、長時間同じ姿勢で仕事を続けるので、筋緊張性頭痛に悩まされる方が多いとされています。
予防方法
人間の頭の重さは約5kgと言われています。うつむき姿勢が続くと首、肩、背中の筋肉に負担をかけるため疲労が蓄積し頭痛が起きやすくなります。
極力、うつむき姿勢を控えると頭痛予防に効果的です。
パソコンやスマートフォンを操作する際は、なるべく目線の高さに合わせて操作することをおすすめします。
また、ストレッチや湯船に浸かって入浴することで、首や肩、背中の血流を良くすることも効果的です。
B.片頭痛
頭の左右どちらかに現れる頭痛のため、「片」頭痛と呼ばれます。ズキンズキンと脈打つような痛みが現れ、体を動かしたり入浴したりすると悪化するのが特徴です。
頭痛が起こる前兆で視界がキラキラ、ギザギザした模様に見える「閃輝暗点(せんきあんてん)」という現象が起こることや、吐き気、嘔吐を伴うことがあります。
主な原因
脳の血管が急激に拡大し、脳の血流が多くなりすぎるために頭痛を起こすと言われていますが、正確なメカニズムは分かっていません。
何らかの変化が起きた脳の視床下部で、顔の皮膚の感覚を司る「三叉神経(さんさしんけい)」が刺激されて炎症物質が発生し、脳の血管が急激に拡張することが原因と考えられています。
予防方法
食べ物の中には、片頭痛を誘発させると言われているものがありますので、注意してみると良いかもしれません。
・赤ワイン
・チーズや納豆など(チラミン含有食品)
・ハム、ソーセージなど(亜硝酸ナトリウムを含む加工肉)
・スナック菓子、インスタントラーメンなど(グルタミン酸ナトリウムを含む食品)
※いずれも何らかの形で血流増加を促したり、血管を広げたり縮めたりする作用があるため、片頭痛を誘発させる可能性がある食品です。
C.群発頭痛
片方の目の奥がえぐられるようにとても激しい痛みが発作的に現れる頭痛で、睡眠中に起こることが多く、激痛で目が覚めることもあります。
痛み発作は1日に2~8回繰り返され、数日~3ヵ月ほどの間、集中して続きます。これを群発期と呼びます。頭痛が起こらない時期を経て、また群発期がやってくる場合や、群発期が年中続く場合もあります。
主な原因
目の奥にある「内頚動脈(ないけいどうみゃく)」が何らかの原因で拡張し、周囲に炎症が起こり、神経を刺激して起こると考えられていますが、正確なメカニズムはわかっていません。
予防方法
群発頭痛はアルコールやタバコが引き金になることがありますので、特に痛みが発生した群発期には避けた方が無難です。
2.急性頭痛(二次性頭痛)
脳に異常があって起きる頭痛で、二次性頭痛とも言われます。
その名の通り急激に起こる頭痛で、とても激しい痛みを伴います。症状がでた場合は一刻も早く病院を受診しましょう。
D.脳血管障害・髄膜炎、脳腫瘍
脳の血管に障害が起こる脳出血や、脳表面の膜と脳の空間にある血管が切れて起こるくも膜下出血、髄膜炎や脳腫瘍などが挙げられます。
脳出血の場合は、とても強い頭痛と共にめまい、吐き気、嘔吐の症状が起こります。いずれも一刻も早い病院での受診が必要となります。
E.薬物乱用頭痛
頭痛薬を飲む回数が増えたことで頭痛の症状が悪化し、慢性化してしまった状態を薬物乱用頭痛と呼びます。
頭痛薬を常用すると脳が痛みに過敏になり、わずかな刺激でも痛みを感じやすくなってしまいます。何度も頭痛薬の服用を続けるとさらに悪化してしまい、薬の効果も薄れていきます。
主な原因
頭痛薬の過剰摂取が原因です。
頭痛薬を毎月10回以上服用する方は薬物乱用頭痛が疑われます。
慢性頭痛と急性頭痛の見分け方

「お酒を飲み過ぎてしまった」「よく眠れなかった」などといった原因が特に思い当たらない時は、まずは病院で診察を受けることをおすすめします。
特に、今まで感じたことのない痛みがある場合や、頭痛とともに目の見えにくさや手足の動きにくさなど、何らかの体の異変を感じた場合は、急性頭痛(二次性頭痛)の可能性があります。
頭部のCT検査や、MRI検査などで特に異常が見られなければ、急性頭痛ではなく慢性頭痛です。
慢性頭痛の服薬治療は、対症療法?

慢性頭痛の原因の大半は、筋肉の緊張やコリが原因。
慢性頭痛を改善するためには、緊張している筋肉を緩め、コリをほぐすことが効果的です。
痛み止めや安定剤、抗うつ剤などを服用すればその場は楽になりますが、痛みの根本原因を無くす治療ではありませんので、時間が経てばまた痛みが出てしまうケースが多いです。
結果的に服薬治療は対症療法となってしまい、痛みを繰り返し、また薬で抑えるといったループに陥ってしまい、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
一本鍼治療で慢性頭痛を改善

慢性頭痛(一次性頭痛)の原因の大半は、筋肉の緊張(コリ)によるもの。
マッサージでは届かない身体の深いところにあるコリにアプローチする一本鍼治療なら、慢性頭痛の原因となるコリを効率的にほぐすことができます。
ぜひ一度、「たちかわ堂治療院」の一本鍼治療をお試しください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
