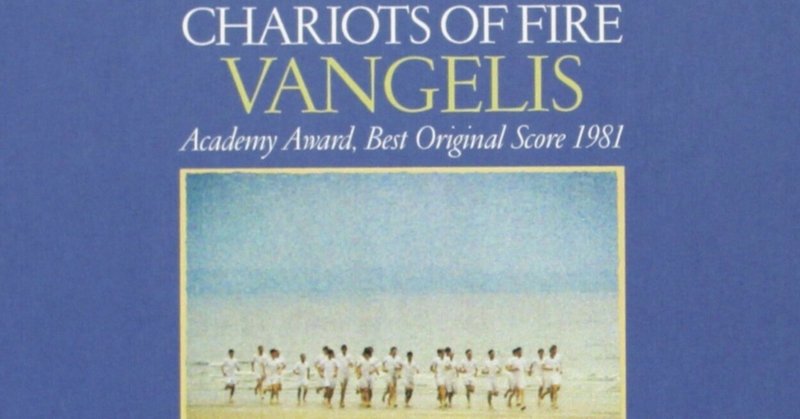
読むナビDJ 9:オリンピック音楽 - 過去記事アーカイブ
この文章はDrillSpin(現在公開停止中)というウェブサイトの企画連載「読むナビDJ」に書いた原稿(2013年10月3日公開)を転載したものです。掲載される前の生原稿をもとにしているため、実際の記事と少し違っている可能性があることはご了承ください。また、著作権等の問題があるようでしたらご連絡ください。
去る9月7日、2020年開催の東京五輪が決定しました。今の日本の状況で五輪開催をやることの是非の議論もありますが、オリンピックというスポーツの祭典そのものに関しては、みなさん心ワクワクする人が大半ではないでしょうか。
そんなオリンピックは、スポーツだけでなく音楽も注目されるイベントになってきています。とくに1984年のロサンゼルス五輪以降はエンターテインメント性も高くなり、開会式や閉会式はまるでコンサートのような演出を行い、テーマソングも大々的にフィーチャーされるようになりました。それにともない、オフィシャルだけでなくアンオフィシャルなものも含めて、オリンピックと音楽は密接な関係を築きつつあります。
今回はオリンピックにちなんだ多種多様な楽曲を10曲セレクト。大会開催の順を追って、スポーツの祭典の歴史を紐解くように、音楽も楽しんでみてください。
ヴァンゲリス「炎のランナー~タイトルズ / Chariots Of Fire - Titles」
オリンピックと聞くと、この曲を思い出す人も多いのではないでしょうか。1924年のパリ五輪を舞台に、若きアスリートの栄光と苦悩を描いた1981年の映画『炎のランナー』。アカデミー賞を受賞した作品自体のクオリティはもちろん、ギリシャのシンセサイザー奏者ヴァンゲリスによるサントラも大ヒットし、いまだにスポーツ関連の番組やイベントで使われる頻度の高い名曲です。プログレ出身のヴァンゲリスは本作含め、サントラの世界で売れっ子となり、『ブレードランナー』(1982年)や『南極物語』(1983年)でも成功を収めました。
古関裕而「オリンピック・マーチ」
今から半世紀前の1964年に行われた東京オリンピック。まだ戦後を引きずっていた日本に大きな経済効果をもたらし、新幹線や首都高をはじめインフラ整備のきっかけにもなりました。そんな復興ムードを掻き立てるように、勇壮な「オリンピック・マーチ」が高らかに鳴り響くことになります。作者の古関裕而は、日本の近代音楽を代表する作曲家。クラシック音楽はもちろん、映画や舞台の音楽、歌謡曲、軍歌に至るまで様々な分野で活躍。スポーツ関連でいえば、全国高校野球大会のテーマ「栄冠は君に輝く」も彼の手によるものです。
三波春夫「東京五輪音頭」
同じく、1964年の東京五輪関連。「オリンピック・マーチ」よりも、こちらの方が有名でしょう。いわゆるノヴェルティ・ソング的なイメージもあり、三波春夫にとっては万博のテーマソング「世界の国からこんにちは」と並ぶ代表曲です。でも実は、作曲者の古賀政男は三橋三智也のために書いたそうです。他にも橋幸夫や坂本九など多くの歌手が競作しており、関連レコードは当時400万枚以上も売れたというから驚き。近年では氷川きよしも歌っていますが、2020年に向けてさらにこの曲をカヴァーする人が増えそうです。
ヘンリー・マンシーニ「時よとまれ、君は美しい ミュンヘンの17日~リュドミラのテーマ / Visions of Eight - Ludmilla's Theme」
1972年のミュンヘン五輪は、8人の映画監督によって撮影され、オムニバスのドキュメンタリー映画『時よとまれ、君は美しい ミュンヘンの17日』として公開されました。『東京オリンピック』を撮った市川崑や、『男と女』や『白い恋人たち』で知られるクロード・ルルーシュなども参加しています。印象的な音楽は巨匠ヘンリー・マンシーニが担当。なかでも、ソ連の体操選手リュドミラ・ツリシチェワのシーンに流れる美しいメロディが傑作。武装組織によってイスラエル人選手が殺害されるという悲惨な大会だっただけに、ちょっと複雑ではありますが。
ルネ・シマール「モントリオール讃歌 / Bienvenue à Montréal」
70年代の歌謡アイドル・マニアならきっとご存じのルネことルネ・シマール。1974年の東京音楽祭世界大会で「ミドリ色の屋根」を歌い、13歳という若さでグランプリを受賞しました。ルネはカナダのケベック州出身ということもあり、1976年のモントリオール五輪では公式テーマを歌う歌手に抜擢されました。70年代らしい躍動感のあるソフト・ロック・チューンは今聴いても新鮮。しかし、モントリオール五輪は増税などの施策ミスで地元の反対が大きく、この曲までもがバッシングされ、結局ヒットせずに終わったという不遇の名曲です。
ジンギスカン「めざせモスクワ / Moskau」
1980年といえば、アメリカとソ連が対立する冷戦のまっただ中。前年にソ連がアフガニスタンに侵攻したことにより、モスクワ五輪はアメリカや日本をはじめ50カ国近くがボイコットするという前代未聞の大会でした。不参加国の中には西ドイツも混じっていたのですが、なぜかその国からデビューしたジンギスカンが「めざせモスクワ」という曲を発表し世界的に大ブレイク。特別にモスクワ五輪に招待されるという栄誉を得ました。この曲は日本でもヒットし、ダーク・ダックスやバオバブ・シンガーズによってカヴァーされています。
ジョン・ウィリアムズ「オリンピック・ファンファーレとテーマ / Olympic Fanfare And Theme」
前回のモスクワの反動で、1984年のロサンゼルス五輪は当時の東側諸国がボイコットする大会となりました。しかし前述の通り、このあたりからエンタメ性の高いイベントになっていきます。その象徴ともいえるのが、当時発売された『L.A.オリンピック公式アルバム』。このアルバムは、競技別のテーマ曲が収められており、TOTOやハービー・ハンコック、そしてフィリップ・グラスまでジャンルを超えたビッグ・ネームが大集結。なかでも映画音楽の巨匠ジョン・ウィリアムズによるファンファーレは、大会の華やかさを象徴していました。
フレディ・マーキュリー&モンセラート・カバリエ「バルセロナ / Barcelona」
1992年のバルセロナ五輪あたりになると、すっかり冷戦の雰囲気はなくなり、さらに音楽との密接なコラボレートが行われるようになります。我が国からは坂本龍一にも声がかかり、マスゲームの音楽を作曲したことも話題になりました。メインのテーマ曲は、音楽監督を務めたテノール歌手のホセ・カレーラスとサラ・ブライトマンのデュエットでしたが、それ以上に話題になったのがクイーンのフレディ・マーキュリーとオペラ歌手モンセラート・カバリエのデュエット。しかし、残念ながらフレディはオリンピックの前年にエイズで急死。彼の代役はホセが務めました。
ミューズ「サヴァイヴァル / Survival」
昨年2012年のロンドン五輪になると、みなさんも記憶に新しいことでしょう。音楽や演劇のさかんな英国らしく、開会式と閉会式のゴージャスな演出及び出演者も話題になりました。とくに閉会式は、クイーンとロンドン交響楽団を核に、ジョージ・マイケルの復活、スパイス・ガールズの再結成、ザ・フーのメドレーなど山場が満載。そして、公式テーマソングとなったミューズのアグレッシヴな「サヴァイヴァル」もクライマックスのひとつに数えられます。なお、ミューズのメンバーは聖火リレーにも参加したことでもニュースになりました。
アルリンド・クルス、エヂ・モッタ、マルチナーリア、他「Os Deuses Do Olimpo Visitam O Rio De Janeiro」
次回2016年の舞台は、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ。ロンドン五輪の閉会式では、マリーザ・モンチやセウ・ジョルジが登場してブラジル音楽ファンを驚喜させましたが、なんとその直後には公式テーマソングが発表されるという気合いの入りよう。日本では一般的ではありませんが、サンバの大スターであるアルリンド・クルスやゼカ・パゴヂーニョ、そして新作『AOR』が話題のエヂ・モッタなど多数のミュージシャンが参加。カシンがサウンド・プロデュースを担当し、期待を煽るようなスケール感に満ちたナンバーに仕上がっています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
