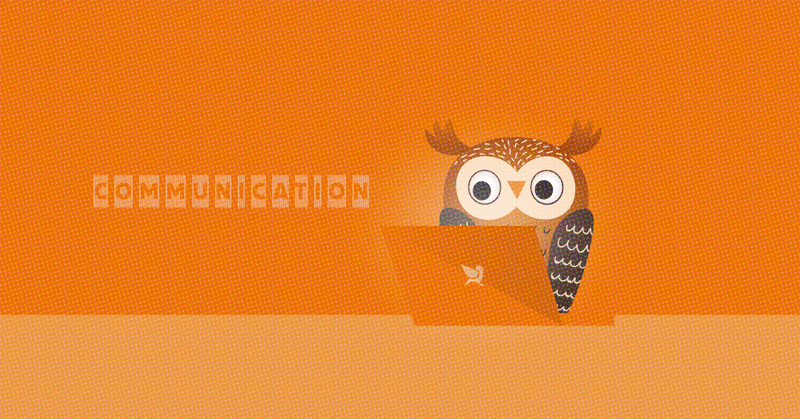
フクロウのように大きく開いて
すっかり、本を読まなくなってしまった。私は継続力が中途半端なのかもしれない。毎日毎日、一年間ずっと、あるいはそれ以上の期間本の世界に触れていた自分が、別人みたいだった。
これはただの日記。一つ変わった所があるとすれば、バカみたいに本を読んでいたのに最近は本に触れることさえしなくなったことである。昨年も、一昨年も、その去年も、私に周りには常に本がいてくれたのだが、今はその限りじゃない。何度目かのCtrl+Z。本を読むかわりに覚えたキーボードのコマンドを何度も行使して、慣れない(ようになった)文章を何度も打ち直す。
携帯を忘れた。硬くて、薄くて、手におさまりのいいスマートフォンが、ショルダーバッグにも無い今週の一日だった。焦り、といらだち。スマホが使えないことの不安より、普段持ち合わせているものを忘れる自分の愚鈍さに怒髪冠を衝きそうになった。いつだって怒るのは、自分にだけ。それは、スマホの一件でも火を見るよりも明らかだそうだ。
人は手のあたりに何かないと不安なんですよ。と、どこかの本で読んだ気がする。スマホが無いから不安なのか、元々手に何か無いと不安なのか…どちらにせよ何かこう手持ち無沙汰になるのが、気持ち悪い。けど、それは偶然ショルダーバッグに入れていた一つの本で緩和される。「大衆の反逆」という本の、「フランス人のためのエピローグ」という章をまず読んでいた。「大衆の反逆」という本って何?という問いは一旦おいておき、読むのが初めてでないその本にそもそも興味を持った理由を、過去の自分に問いたくもあった。なあ~んでこんな本買ったんだろう…とあまり面白くない章の上を、目線がなでていくだけ。そんなもんである。幾ら本を読もうとも、すべての文章をスラスラ理解できるわけじゃないのだなぁと。
でも、本というものからどうしても抜け出せない。その理由を、私は知っている。それは、いつどこでも、教訓や学びを与えてくれるから。雷が落ちるほどでもないし、神から天啓を受けたッ!程のものじゃないけど、「あっ」と気づかされる。ありきたりで、慣れたものばかりに埋め尽くされそうになる日常に投じられる一石は、微かではあるが嬉しい。
「大衆の反逆」の第一章「密集の事実」という章に、書いてあったこと。それは、「知性人のしるしは、この驚く眼にある。それゆえ古代人たちは、いつも大きく眼を見開いた鳥、すなわちフクロウをミネルヴァ[ローマ神話の技術・工芸の女神。のちギリシャ神話の知恵・工芸の女神アテナと同一視される]に供したのだ。」(オルテガ・イ・ガセット、2020,65-66)というもので、ちょっとした雑学でも面白なぁと感じた。
ハリーポッターでもホグワーツ城に持ち込んでいい三種類の動物の一匹(残りは猫、とヒキガエル)くらいだなぁ…という知識しか持ち合わせていなかった…(笑) これから好きな動物、好きな鳥は何かを問われたら、「フクロウです」と答えたくなった。特に意味はない…ビジュアル重視ならコンドルかハシビロコウに二強。異論は認める。と、おふざけはここまでで、先ほどの引用した文章を目にした時に考えていたことは、大学一年生の時に受けた、哲学の講義で勉強したこと。哲学者の特徴というか、哲学を学ぶ時に大事なことは、「驚く」ことであるってね。驚きから、学びが始まるんだって。へぇ…知識と知識がつながる所はなんとも面白い。私も大きく眼をかっぴらいていようか。そう思った一幕は、帰りの電車の異状も特にない座席でのこと。
参考
2020、オルテガ・イ・ガセット、『大衆の反逆』(佐々木孝訳)、岩波文庫。
あ、わたしは文献書くタイプです…( 一一)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
