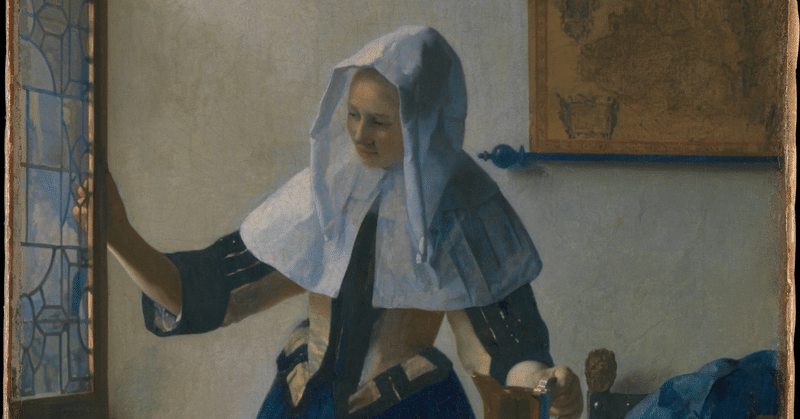
小雪 * 巫女の卒論
「今、谷崎潤一郎の卍っていう小説で卒論書いているんですけど」
大学四回生の巫女が紙垂を作る内職をしながら言う。彼女は日本文学の専攻である。
「こないだ二千字書いて教授に見せたんです」
「二千字、少ないよ」
「その二千字も、教授に、一旦置いとこうか。って言われてしまって」
「それボツってことだよね」
「そうなんです、また一から書き直しです」
北欧の人のように色が白く、瞳も茶色い彼女が、はぁ、とため息をつく。白いきれいな手で折られた紙垂が、彼女の横にふわっと山積みになっている。
私たちは手作業のことを内職と呼んでいる。たとえば半紙に切り込みを入れて折り、紙垂を作る。結婚式用に昆布を結ぶ。白い紙を細かく切り、お祓い用の切麻を作る。切麻は塩と同様に撒いて空間を清めるためのものである。
巫女たちと内職をしながら卒論や就活の話を聞くのが私は好きだ。卍の中身を知らない私に、巫女があらすじを説明してくれた。
「園子さんていうお金持ちの奥さんがいて、彼女は美術学校に通っているんです。そこで光子さんていう魅力的な女性に出会って好きになってしまって、愛し合うんですね。でも光子さんの方にも婚約者がいて、彼も結構、濃いキャラクターで、けっきょく四人の恋愛模様が卍になってる、みたいな話です」
そっか。園子さんは光子さんのことを、たまたま好きになっちゃったんでしょ? じゃあ仕方ないよね、好きになっちゃうのは。神が作った落とし穴に落ちるようなものだから。私は熨斗袋の紅白の紐を外しながら言う。外がだんだん嵐になってきた。渡り廊下の簀子、上げようかどうしようか、頭の隅で考えている。渡り廊下は雨漏りするので、木製の簀子が雨に濡れ、そこを歩くと足袋にも染み込んでしまう。濡れた足袋の冷たさは耐えられない。
***
「儀式で、巫女さんとかが、神がかったようになったりするじゃない? あれって、本当にそうなってるの? 演技してるの?」
学生時代の女の先輩が、久しぶりに会った私に聞いた。相変わらずこの先輩は直球だなあと思いながら、「うちの神社ではそういう儀式はしませんけど、演技ではありませんよ、本当にそうなってるんですよ」と答える。
儀式でなくても、唐突に何かを思いついたり、急にどこかへ行きたくなったり、誰かや何かを好きになったりすることを、私は神の采配と呼んでいる。神がかりとはニュアンスが違うかもしれない。でも、自分ではない何かの作用という意味では同じだ。
調子乗りで涙もろいスサノオが、外でさんざん遊んで帰ってきて、リラックスタイムにコーヒーでも飲みながら、箱庭をいじっている。箱庭の中には人間たちが暮らしている。スサノオは上から眺めて、これはぁ、こっちにやってぇ、こことここにぃ、落とし穴を作ってぇ、こいつとこいつはくっつけちゃえ。とやっている。スサノオは、その人間たちが男か女か、未婚か既婚かなど、まったく気にしていない。だって神だから。
スサノオだけではなく、八百万の神たちが、あちこちで采配しているから、采配される側の私たちはとても忙しい。
新人の巫女が、「これ、どうするのが正解ですか?」と聞いてくる。
右に置くのか、左に置くのか、紐は垂らすのか、お餅は山盛りにするのか、水器の蓋は開けるのか、閉めておくのか、きまりがあるものもあるし、無いものもある。西と東で、あるいは京都と大阪で、きまりが違うこともある。新人はわからないから、とりあえず全部聞いてくる。私は、きまりがある時は正解を言う。無い時には、「面白い方が正解。」と言う。すると、はてな?という顔をされるので、さらに「センス。」と言う。そうすると巫女たちは「私センス無いから・・どうしよ」と悩む。そして不思議な形のお供物が三宝に乗せられる。
**
卍の巫女は京都の大学に通っていて、神社の助勤が無い日には塾の講師とコンビニでのアルバイトをしている。卍の説明がひと段落すると、コンビニのお給料についての話になった。コンビニではお給料が系列のネット銀行に作った口座へ入るのだという。
「私は5月生まれだから、銀行口座の支店名は、おにぎり支店なんですけどね」
「ふざけた名前だなあ」
「他におもち支店とかチョコ支店とか、からあげ支店もあります」
ネット銀行は建物を必要としないので、支店名も地名である必要がない。支店名は誕生月で決まり、おすし支店やスープ支店もあるのだという。
自分が銀行のおにぎり支店長になって、おもち支店長と熾烈な出世争いを展開しているところを想像してみる。が、どうも広がらない。マニラ支店長やニューデリー支店長なら、めくるめく日々を妄想できるのに。
ネット銀行には建物が必要ないように、支店長もたぶんいらない。お金が実態のない数字であるように、支店も支店長も実態がない。
幽霊支店の幽霊支店長。概念を貸し出して、妄想を回収する。
**
学生の巫女たちは、たいてい複数のアルバイトを掛け持ちしている。
私は、巫女たちがコンビニやパン屋さんやケーキ屋さんでアルバイトしているところに、眼鏡とマスクを着用し、極力凡庸な服装で、お客としてこっそり買いにゆく。存在感を消すのには慣れている。神職は、神と人との間に立つ者として、透明な存在でなくてはならないから、日々そのように心がけ、訓練をしているのだ。透明になった私は、働く彼女たちを見て、「ここの制服もかわいいけど、やっぱり巫女の装束の時のほうが百倍良いな」と満足する。ついでに甘い物や新製品を買って帰ってくる。
来てはったでしょう、バレてますよ。変装しててもすぐわかりますよ、たたずまいで。
と巫女たちは笑いながら言う。
やっぱりオーラが出ちゃうんだごめんねごめんねー。と冗談を言いながら、私は自分の素人っぷりに少し落ち込む。まだ完全には透明になれていないのだ。存在感を消すのはむずかしく、幽霊支店長への道は長い。
絵の達者な巫女が、干支の絵馬に可愛らしい顔を書いている。
歳神様がもうすぐやって来る。
二十四節気 小雪 新暦11月22日頃
*亥の子餅(いのこもち)
亥の月の初めの亥の日の亥の刻に、七種の新穀で作った亥の子餅を食べると病気にならないという言い伝えが西日本にある。茶道では11月に炉開きをするが、その際のお菓子も亥の子餅である。火鉢や炬燵を出すのもこの日が良いとされている。六月の晦日に食べる水無月と言い、亥の月の亥の日に食べる亥の子餅と言い、日にち限定で食べるお菓子は限定であるがために三倍美味しく感じられるううえ、邪気を祓い、繁栄を願うという大義名分があるのでギルティフリーなお菓子でもある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
