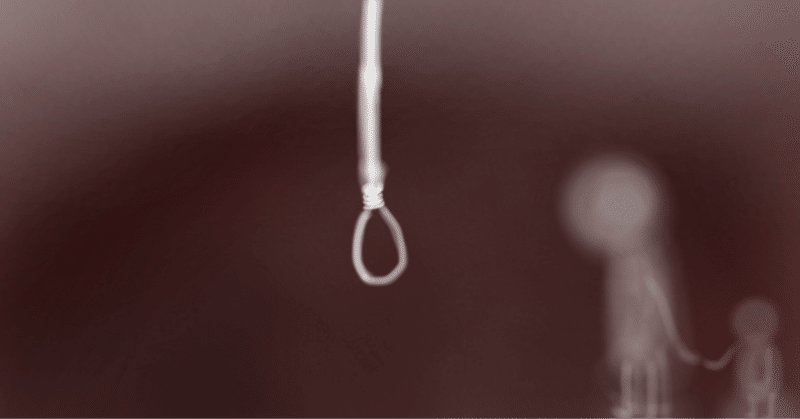
Photo by
nemuinda_1
江戸時代の「希死念慮」
上記の話の続き。
希死念慮とは死を願う感情、はっきり言ってしまえば「自殺願望」のことだが、「自殺」というのは謎が多い。遺書にはっきり原因を書いている人もいればそうでない人もいるからだ。だからこそ「本当に自殺だったのか」「闇の権力に殺されたのでは」などという陰謀論が巻き起こる。古くはマリリン・モンローがそうだし、最近だと俳優の三浦春馬の自殺が「謎が多い」と言われた。
死にそうもない人が突然死を選ぶ、この現象は江戸時代でも不思議がられていたらしく、江戸時代後期の儒学者・鈴木桃野が「反古のうらがき」に書いている。いろんなところで引用される有名な話であるが、鈴木はこれを「縊鬼」と題し、妖怪や悪霊の類とした。物語自体は下記のリンクを参照のこと。
「不意に死にたくなる」という怖さがなんともいえないが、こういう人間のよくわからない感情というか、心理を「妖怪の仕業」としたのだろう。
希死念慮とはちょっと違うが「通りもの」というのがあって、これも妖怪の一種とされている。通り悪魔などとも呼ばれているが、これに取り憑かれると心を乱されるという。ある屋敷にこの「通りもの」が現れ、それを見た者はとっさに「この世のものではない」と思い心を鎮めた。運良く彼は助かったが、堀の向こうに住む別の者がこれに取り憑かれて乱心し、刀を振り回して人に傷を負わせた挙げ句、自ら命を絶ったという。
この「通りもの」「通り悪魔」という言葉、なぜか姿を少し変えて今でも残っている。意味合いはまったく同じ。
「通り魔」である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
