
酒屋八兵衛×村山健太郎〜酒器編〜
昨日は第三回オンライン酒屋八兵衛酒の会!!
今回は佐賀の唐津焼作家、村山健太郎さんをお招きしての座談会でした🍵
予め、健太郎さんの酒器と元坂さんの八兵衛のお酒を双方送り合って頂き、同じ酒を同じ酒器で呑みながら語り合ってもらいましたよ〜👏
酒器による味の違い

今回元坂さんの元に届けて頂いた酒器がこちら!!
右側、白い方は旬蕾で実際に使わせて貰っている酒器と一緒ですね☺️
元坂さんが健太郎さんのこの2つの酒器を手にした時の印象、
まずシンクに置いた時の音が今まで使っていた酒器(市販の陶器)とは全然違う!!カーンと高い音が抜ける感じ!!
そして次に驚かされたのは同じお酒を飲んでいても2つの酒器で飲み比べた時のその違い!!
*右側、白い酒器とだとシャープな感じの飲み心地。八兵衛の純米酒吟醸、大吟醸はこちらが合う!
*左側、茶色い酒器だと味が増幅される様な広がりのある飲み心地。八兵衛の山廃、純米酒が合う!
といった風にその違いにびっくりされていました!!
本当にそんなに違うの?と思われる方もいらっしゃるでしょうが、本当に全然違います!!
私達旬蕾でも飲み比べていましたが全然印象が変わります!!お酒を呑む時に如何に酒器の影響があるかが改めて分かりましたね🧐
何故こんなに違いが?
勿論、原料によっても変わりますが形、釜や燃料によっても変わってきます。
例えば、白い酒器は灯油を燃料とした灯油窯で焼いていて、茶色い酒器は薪を燃料として登り窯で焼いています。
特徴として…
灯油:コントロールが効きやすく狙った方向に持って行きやすい。あまり存在感の主張したくない普段の日常使いの料理とかに持ってこい!
薪:存在感が出る。薪を燃やした時の灰の影響も受ける。晴れの日の器など、存在感の出したい時に向いている!
と燃料1つとってもこんな特徴が出やすくなるんですね〜!!
実際に使用している釜も見せて頂きました👀✨

左:灯油窯 右:薪の登り窯
土と釉薬
酒造りにおいて重要な発酵やできたお酒を熟成させること、それは陶器の原料でもある土や釉薬でも同じ。土も発酵させたり熟成させたりして良い素材に精製されます!!
村山さんのこだわりの一つとして原材料は自らで採取、作っています!!
通常は土屋や釉薬屋さんから買ってくるもの。
しかし、村山さんは自ら土を掘ってきて釉薬もご自身で作られています。
全国でも作家自ら土を堀り、釉薬を作って作品にしているのは30人もいません。全体のほんの数%とといったところです!
そういう土から掘ってきて精製するという昔ながらの技術が残っているところが唐津の魅力の一つだったそうです✨

村山さんの掘ってきた土↑
一方の元坂さんも自ら伊勢錦という酒米を作り、それを用いて酒造りをしている面もあり、村山さんと通ずるものがありますね!!👍
業種を超えたコラボ✨
釉薬とは…焼き物の表面に掛ける薬品で、これを掛けて焼くことでガラス質のツヤっとした光沢や色付け、耐水性を得られる等の特徴があります。
釉薬では主に松、杉、雑木、稲藁等の灰や石を原料に作っています。
普段村山さんが使用している稲藁の灰はもち米の藁を主に使っていますが、元坂さんの育てている酒米、伊勢錦の稲藁ならどんな発色をするのか?
是非元坂さんの育てた伊勢錦の稲藁の灰の釉薬で酒器を作ってみたい!!
そしてその酒器で伊勢錦の八兵衛のお酒を飲みたい!!
なんて素敵な伊勢錦のコラボレーション!!
ワクワクしかしませんね🤣
お酒と酒器の楽しみ方がより一層増します☺️絶対にいつか実現させて欲しいものです!!
大事なのは肌感!!
原料にこだわるお二方、双方の共通点にはこんな所でも…。
村山さんの場合、土は触った時の感じが全然違います!
土屋で変にブレンドされたものだと油粘土みたいな気持ち悪さを感じてしまう。逆に天然のもの(自分で掘ってきた唐津の土)は扱いにくいけれど触り心地が自分にとってとてもいい!!
釉薬にしたって農薬を使っている稲藁の灰はドロドロして臭い。とてもではないが使えないので無農薬のものを使っています。
一方の元坂さんも生米に手を突っ込んだ時の感触が全然違うんです!!例えば同じ伊勢錦でも自営田と他で育ったものとでは温かみが違うのです。
元坂さんは米洗いをする時も下記のような違いを感じています。
山田錦:ギシギシと黒板を引っ掻いた時の感じ
五百万石:サラサラと手の通りのいい感じ
伊勢錦:粒が大きいがスッと入ってきて温かみのある感じ
※お酒の味等は関係なくあくまで米洗いの感覚です。
職人の自分に合う肌感というものがやはりそれぞれあるんですね〜🤔
村山健太郎の思ういい器
村山さんは経年変化が好き!!器は育つもの。
例えば革製品やジーンズのように使えば使うほどモノが馴染んで良い味が出てきますよね?
器もそれと同じで使えば使うほどその器の味が出てきて良い物へと成長していきます!!
そして原料が良ければ良い育ち方をするのです!!
村山さんが苦労して自ら土を掘りに行って原料を確保するのも全てはこの器の成長を楽しめるものを作りたいからなのです!😎
国宝になっている器とかも殆どが使い込まれてきたもの。
村山さんは
"自分が真っ当な作りをして先の人が使い込まれたものを見て欲しい"
という想いで作られているのです!!!
そして元坂さんの伊勢錦で造られたお酒も年、3年と置いてどんどん良くなるお酒!!🍶
器と同じ様に長い目で付き合って欲しいお酒なのです!!
成長を楽しむ器とお酒。手に入れた私達消費者にとっても長年楽しめるものですね。
最後の方にご参加頂いた唐津で日本料理店"あるところ"を営む平河さん!
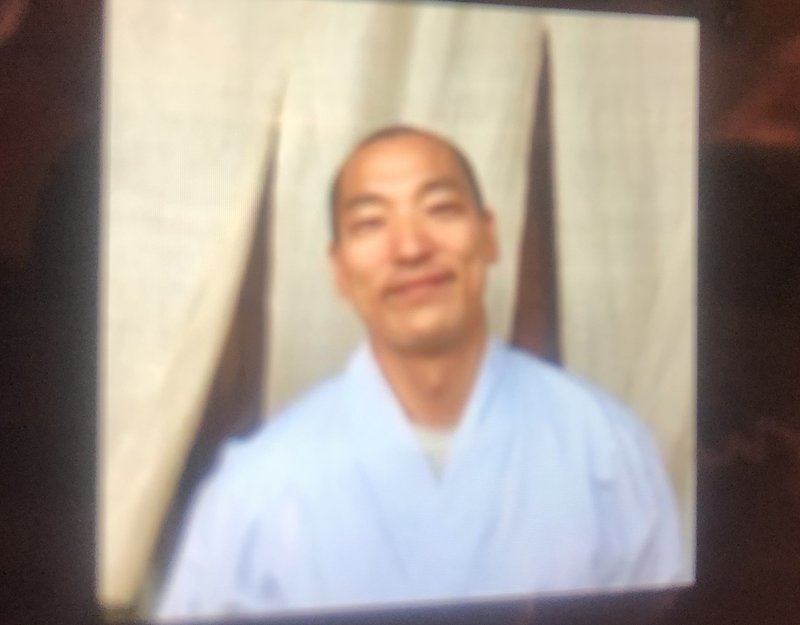
あるところhttp://arutokoro.com/category/gaoisatu/
日本料理の原型ともいえるお店。
締めの塩むすびがめちゃくちゃ絶品とのこと!!🤤
あるところでも村山さんの器を使っており、無理な注文も村山さんだからこそ叶えてくれる技術の高さも教えてくれました👌
あるところにも是非行ってみたい…締めの握り飯が食べたい…
皆さん是非!村山健太郎さんの窯場から10分程なので両方行けちゃいます🖖
今回、元坂さんの焼き物に興味あるけど全然知識ないからなーの一言から実現したこの会。
酒造りと陶器作りという、一見違うものだけれどもこんなにも多くの共通点や同じ考え方を持っているという事に双方驚きながらも凄く嬉しそうでかなり意気投合していました!!
聞いている私達も楽しくなってしまうお話でしたね🤗
今回も酒の会中にpaypayやnote のサポートによる投げ銭を頂いた皆様本当にありがとうございます😭引き続き宜しくお願い致します!!
記事を読んでイイネ!と思われた方、オンライン酒の会に参加して頂いた方、是非サポートとpaypayよる投げ銭を宜しくお願い致します。
↓↓↓↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
