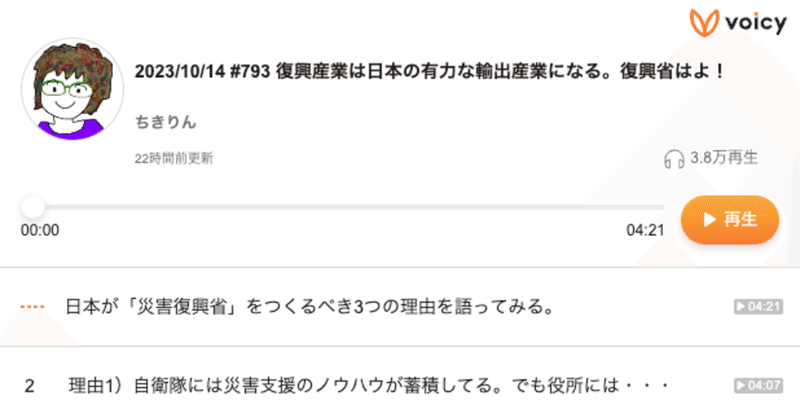
飛騨市の過去の災害について調べてみた
動画クリエイターのシュウジです。
岐阜県飛騨市と株式会社Another Worksが行う、複業人材を登用する実証実験において、「関係人口創出パートナー」として選出いただきました。
ちきりんさんのVoicyを聞いていたら、日本は復興省をつくるべきだ!というお話がありました。とても勉強になったので、内容のまとめと、飛騨市に近年起きた自然災害について書いていきたいと思います。
日本は復興省をつくるべき?
ちきりんさんが日本に復興省をつくるべきといっている理由は以下の3つです。
ノウハウが蓄積される
蓄積したノウハウを他国へ輸出できる
日本メーカーが不得意な産業を克服できる
日本は自然災害の多い国です。しかし、狭い地域で見ると「50年ぶりの大雨」「100年ぶりの大洪水」など、災害に見舞われる機会は多くはないです。ですので、自治体に災害復興に対するノウハウが蓄積されておらず、毎回初めての対応に追われてしまいます。これが理由の1つ目です。
2つ目の理由は、蓄積したノウハウを他国に売ることができる、というものです。世界でも地震や津波、ハリケーンなどの自然災害は猛威を振るっています。そうした国々へ、災害復興のノウハウを提供することができるとおっしゃっています。
最後の理由は日本が不得意な産業を克服できることです。日本メーカーは多機能・高価格の商品を販売することばかりに力をいれています。ガラケーで1gを争っていた当時、iPhoneのシンプルな機能に市場を奪われたことが証明しているように、1つのシンプルな機能を開発するということが苦手です。しかし、災害時に必要とされる支援物資、インフラなどに求められている機能はとてもシンプルです。こここに特化した産業を興していくことができれば、国際競争間でも優位に立てることになります。
ざっと触りだけ紹介しました。詳しい内容はちきりんさんのVoicyをぜひ聞いてみてください。
飛騨市の災害の歴史は
自然災害というと、どうしても自分には関係ないものと思ってしまいがちです。そこで、飛騨市に過去に起きた災害について調べてみました。近年だと、以下の災害が発生しています。
どれも台風や大雨による浸水、土砂流失などが起こっています。平成11年の豪雨災害では死者もでるほど大きい災害だったようで、当時の映像が市役所のHPに掲載されています。
当時からまもなく25年が経とうとしています。当時の自治体の担当者の方は40歳前半〜退職間近という年齢でしょう。実際に復興に関わる世代はもう少し若くなることを考えれば、やはりノウハウを蓄積しておくことは大切といえます。
飛騨市の雪は災害じゃないの?
市役所のHPに面白い記載がありました。昔から伝わる防災に対する言い伝えだそうです。
【古川町】
・宮川河川にあるドンビキ岩(鷹狩橋上流にある大きな一枚岩)が沈むと大水(水害)になると昔から言われる
・雪虫が多いと大雪になる
・ミヤマフジの咲く年は災いごとが起こる
・カマキリの卵が高いところに産み付けてある年は大雪になる
・オサムシの多い年は大雪になる
【河合町】
・小無雁地内の弁天橋から上流左岸※1の道が冠水すると、小無雁地区の避難を準備、開始する ※1上流から下流に向かって眺めた左側の岸
・ススキにあるカマキリの卵の位置まで雪が積もる
・雪が降る前に椿がつぼみを付けると雪が少ない
【神岡町】
・農業をやっていて感じることとして、マイマイガ等の蝶目類が大量発生した地域は大雨になりやすいと感じます【経験則】
・ネズミの異常行動(普段食べないほうれん草を食べ散らかす等)が見られた数週間後に大きな台風が来る事があります【経験則】
・鮎釣りに行く時は、キュウリを持って行くと河童にひっぱられる
・川に入って釣りするので流されないように注意って意味だったように思います
・数河方面から来る夕立は大雨、柏原方面からの夕立は止まる【伏方地域】
昔の人の経験則は馬鹿にならないと思う一方で、経験則だけでないデータの蓄積も必要だと思う次第です。
市役所のHPに豪雪による災害の記載はありませんでしたが、都会出身の僕から見れば、飛騨市の雪は災害レベルです。大学の頃、豪雪地帯出身の友達が都心の電車が3mmの積雪で運転停止になるニュースを見て驚いていましたが、そりゃそうですよね。雪の降るレベルも、それに対する備えも違いすぎます。
雪国の人なら慣れていると思いがちですが、必ずしもそうではありません。誰も冬の雪かきを進んでやりたがる人なんていません。都会出身の人ははしゃいで雪かきを楽しい!と言いますが、3日で嫌になります(←昨年の僕です)
特に屋根の雪下ろしは大変で、市が雪下ろしの講習会を開くほど。
これまでは雪下ろしをやれていた人も、高齢化によってどんどんしんどくなっていきます。飛騨市でも2022年に82歳の男性が雪下ろし作業後に転落して死亡したというニュースがありました。

飛騨市では雪下ろしサポート事業として、対象者に補助金を出して除雪を依頼できる制度を設けていますが、除雪を行う人員も補助金額も十分ではないのが現状です。
雪下ろしは何も生産されない作業です。補助金による支援ももちろんですが、除雪を行う人員が今後ますます少なくなることを考えると、根本的な解決にはならないでしょう。
雪を何かに活用できないのか、と調べていたところ「冷熱エネルギー」として活用する取り組みがあるそうです。
記事をすべて理解できたわけではないですが、こういった解決策を模索していくのが、住む人にも必要なのではないでしょうか。なんでもお上に頼っていてはダメで、自分たちの住む土地は自分たちでよくしていくという気持ちを持っていきたいです。
僕が関わらせていただく「関係人口創出」プロジェクトは「未来のコミュニティ研究室(FCL)」が主体となって活動されています。
12月9日には研究発表会があるので、多くの飛騨地域の方に足を運んでもらえるよう活動していきます。
このnoteでは活動の記録を発信していきますので、ぜひいいねやフォローをしていただけると嬉しいです!よろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
