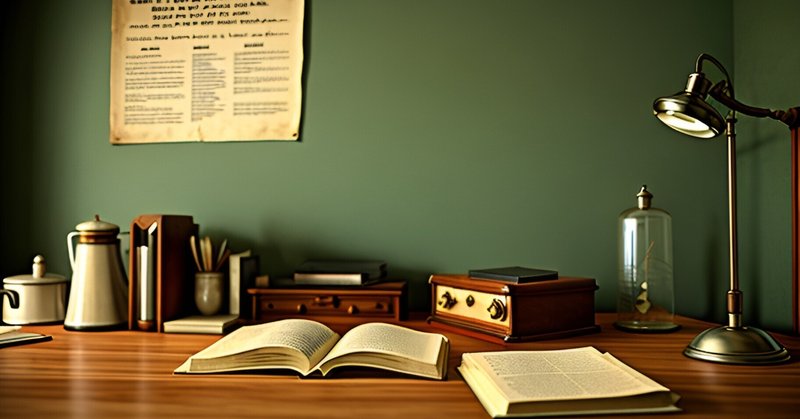
高齢者薬物療法における倫理的な問題
※地域医療ジャーナル2018年10月号 vol.4(10)より転載です。情報の鮮度にご注意ください。
高齢者における多剤併用、いわゆるポリファーマシーをめぐる問題が注目される中で、潜在的に有害事象リスクの高い薬剤、あるいは医学的に無益な薬剤を、いつ、どのように減らしていくかという議論が活発になされているように思います。
もちろん、こうした問題に関心が集まっているのは日本だけではありません。世界的に見ても、薬剤処方数は年々増加しており[1][2][3]PubMedに収載されている「Polypharmacy」に関する論文報告数の推移も2010年以降、急上昇しています。
処方薬剤数が増えてしまう理由として、医療アクセスの向上、高齢化、新薬の開発とその普及、診療ガイドラインの整備、あるいは新規保険病名の追加など、様々な要因が考えられます。
しかし、複数の薬剤が同時に処方されたとしても、患者が、指示された用法通りに全て服用できているかといえば、必ずしもそうではありません。
服薬アドヒアランスは、薬剤の用法が複雑になるほど低下することが示されています[4]。
また、そもそも一般的な心血管疾に対する予防的薬剤の服薬アドヒアランスは、一次予防において50~60%とそれほど高くはないのです[5]。認知機能が低下している人では、さらに低く、その服薬アドヒアランスは10.7%~38%と報告されています[6]。
社会問題化する“残薬”
ここから先は
8,293字
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
