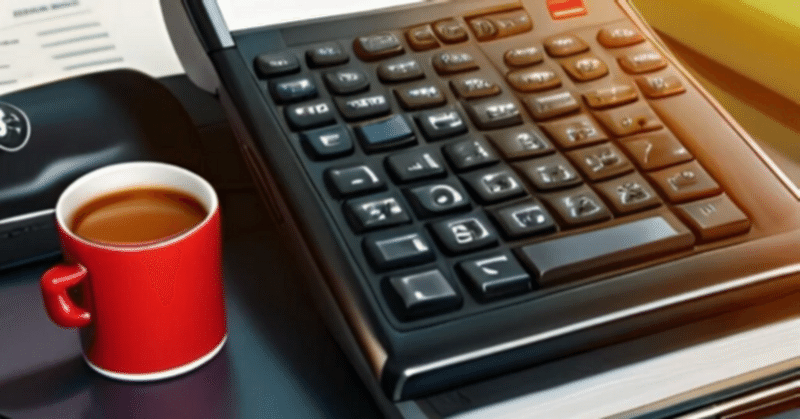
【ビジネス教養としての簿記・会計(第5回)】法定耐用年数と実際の耐用年数のギャップに着目せよ!-ASNOVAのビジネスモデルとコンドーテックの成長性
この不定期連載では、社会人として知っておきたい簿記や会計の重要論点を、実際の経済ニュースなどの事例をふまえて解説します。ビジネス教養としてはもちろん、株式投資を始めた方にも有用なコンテンツを目指します。なお、本連載は全文を無料公開します。
連載も5回目となりましたが、今回の記事で取り上げるテーマの一つは減価償却費です。減価償却とは、有形固定資産における取得原価の費用配分を意味する会計処理と言ってよいでしょう。減価償却は適正な期間損益計算を行う上で、必須の会計手続きです。
例えば、100万円の機械装置(有形固定資産)を購入した場合、その取得原価(購入代価と付随費用の合計)の全額を購入した日の支出(費用)とする場合を考えてみましょう。直観的には、何も問題なさそうに思えますが、会計上は重大な問題が発生するのです。
機械装置は、その使用(稼働)によって、製品を製造し、企業に収益をもたらすものです。将来のキャッシュ獲得に貢献するからこそ資産としての存在意義があります。
しかし、機械装置を購入してすぐに収益が生み出されるものではありません。一方、機械装置の稼働によって期待される収益は、装置の購入から数年にわたるものでしょう。
企業の損益計算は1年という会計期間で実施されます。機械装置の取得原価の全額を、購入日に費用処理してしまうと、機械装置が生み出す収益と、当該費用の対応関係が適切ではありませんよね。
財務会計においては、実現収益に対応する費用のみを計上することが基本的な考え方であり、機械装置の取得原価を購入日に費用処理することは、この基本的な考え方に反するのです。そのため、機械装置の取得原価は、1会計期間に対応する費用のみを配分するわけです。この費用配分の仕方を原価償却と呼んでいます。
例に挙げた100万円の機械装置について、事業の利用に耐えうる期間、すなわち耐用年数を4年とすれば、定額法による減価償却を採用している企業であれば100/4=25万円が毎年の償却額(減価償却費)です。
取得から4年目で減価償却は完了しますので、以降は費用の発生はありません。ただし、機械装置の経済価値も低下しており、資産の買い替えを検討する時期ということになるでしょう【図1】。

減価償却費は、売上原価や販売費および一般管理費として計上され、企業の売上高から差し引かれます。固定資産に対する投資額が大きな企業では、減価償却費も大きくなり、当期純利益を圧迫することになります。
固定資産の耐用年数とは、資産の使用に耐えうる期間のことです。ただし、実際の耐用年数と法人税法における法定耐用年数(会計上の耐用年数)は必ずしも一致しません。
この場合における実際の耐用年数とは、固定資産の経年劣化よって、最終的に使用できなくなるまでの年数を指します。 一方で、法定耐用年数とは税務上必要な減価償却費を算出するために定められている年数です
法定耐用年数と実際の耐用年数にギャップがある固定資産では、減価償却による帳簿上の経済価値低下と、実際の資産価値の低下に相違を認めます【図2】。

このような帳簿上の未償却残高と実際の資産価値のギャップを、巧みにビジネスモデルに組み込んだ企業として、株式会社ASNOVA(証券コード9223)を挙げることができます。同社は、愛知県名古屋市に本社を置く、建設工事用足場のレンタルを行っている企業です。
足場とは、工事現場などで作業するための仮設の作業床や通路およびそれらを支持する構造物のことです。ASNOVAが取り扱っている足場は耐久性が高く、20〜30年以上にわたって使用可能とされています【図3】。

ASNOVAが保有している足場は、当然ながら資産(賃貸資産)であり、減価償却の対象となります。2023年3月期の有価証券報告書によれば、賃貸資産は定率法5年で償却しているようです。つまり、法定耐用年数が5年に対して、実際の耐用年数は20~30年と、大きなギャップがあるのです。
ASNOVAと一般的な小売業者の決定的な違いは、減価償却を行わない商品(棚卸資産)で収益を上げるのではなく、賃貸資産(有形固定資産)で収益を上げるビジネスモデルであることです。
そして、同社の賃貸資産の減価償却は5年で終了し、6年目以降は減価償却費が発生しません。実際の耐用年数を少なく見積もって20年だとしても、15年という長きにわたり、当期純利益を圧迫する減価償却費が発生しないのです。
これは、同社の利益率を高めることに強く寄与します。実際、ASNOVAの決算資料においても、足場の減価償却費が減少していくことでさらなる営業利益の向上が見込めるとの記載があります【図4】。

上述の収益モデルが市場でも高く評価され、ASNOVAのPERは35.33倍、PBRは2.36倍と、同業他社と比べてもかなり割高となっています。PERが拡大するような成長産業とは言えない印象もあり、バランスシートの特性を利用したビジネスモデルで、どこまで企業価値を高めることができるかに注目です。
一方、ASNOVAと同じように足場を扱う企業として、コンドーテック株式会社(証券コード:7438)を挙げることができます。同社は、建設資材、電設資材、管⼯機材を幅広く取り扱う企業ですが、この数年で⾜場事業にも参入しました。

コンドーテックの企業分析については、ヘム(@pygmy_hem)さんという投資家の方が、詳細に企業分析されていますので、ぜひ参考にしてみてください。コンドーテックに関する企業分析においては、日本で最も詳しい記事だと思います。
もはや付け加える情報の余地などない精細な分析ですが、足場事業の中核を担うコンドーテックの子会社、日本足場ホールディングス株式会社もまた、ASNOVAと同様のビジネスモデルを展開できるポテンシャルがあると考えてます。
足場は必要な時に必要な数だけ、迅速に調達できることが重要です。その意味において、全国に展開するコンドーテックの販路は同社の強みと言っても良いでしょう。
また、日本足場ホールディングス株式会社においては、一部の営業所で足場のレンタルを既に展開しているとのことです。ただし、2023年3⽉期におけるレンタル構成比は6%にとどまっています【図6】。
レンタル事業に対して、より一層の注力をすることで、高い収益性の実現と、企業価値の向上が図れるように思います。その意味で、ニッチな市場分野でありながら、まだまだ成長の余地は大きいとみています。

2024年2月7日現在において、コンドーテックのPBRは0.95倍、PERも10.65倍と過熱感はありません。時価総額300億円に対して、利益剰余金が296億、現預金も100億円以上あります。ASNOVAと比べれば、かなり割安に放置されている印象ですね。
本文はここまでです。以下、記事をご購入いただくと、掲載した【図1】および【図2】のパワーポイントファイルがダウンロードできるようになっています。「記事が面白かった」「内容が役に立った」と感じていただけましたら、是非サポートいただけると励みになります。何卒よろしくお願いいたします。
利益相反開示:筆者はコンドーテック株式会社の株式を保有しています。
免責事項:本記事は特定の株式に対して投資を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
