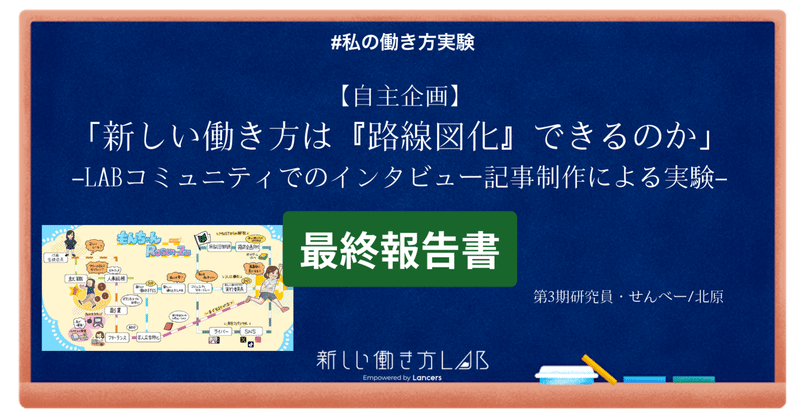
『路線図化』してたら、"インタビュイーのための記事づくりがしたい”という気持ちを自覚した。
研究員の実験、これで三度目なんですけど・・・やっぱり思ったようには進みませんね。でも、三回やってようやく腑に落ちた気がします。実験なんだから思い通り進むわけないだろ、ということが(笑)。
でも、一回目・二回目の実験もアウトプットや活動量は大きくなかったけれど、今では自分の生活に根付き、全く違う形で実を結んでいるなと思います。
今回もマイペースですが、おもしろい実験・おもしろいチャレンジになりました。9,000字とやたら長いですが、最終報告書です✨
(12月25日、えの季さんに作っていただいたグラフィックが完成したため、編集・追記しました✨)
【実験の目的と背景】
新しい働き方LABのHPの働き方図鑑Webメディア『Rosen−zu』の中に、新たなインタビュー企画記事をつくるのが今回の自主企画の主な目的でした。
コンセプト、いいですよね。
「このコンセプトの魅力をもっと引き出せたらおもしろそう!このコンセプトで記事・企画を作ってみたい!!」
その気持ちからチャレンジを計画しました。
▼初期の構想では、以下の2要素を含めることに▼
⑴個人がキャリアを模索する上で役立つ『新しい働き方の路線図』を可視化する
⑵「新しい働き方LAB」というコミュニティの中で、それぞれがじぶんらしいキャリアを模索するのに役立つインタビュー&記事にする
【実験で検証したいと思っていたこと】
⑴制作物:『Rosen-zu』のコンセプトの魅力を引き出すコンテンツとは何か
「フリーランスの人をインタビューして、その人の人生を路線図化したら、それぞれが”じぶんらしい働き方”を見つける法則みたいなものが体系化できるんじゃないか?」というのが当初実証したかったテーマです。
ただ、翻って考え直すと、『Rosen-zu』というメディアのコンセプトに沿い、その魅力が最も引き出されていく形とはどんなものだろうかということがより検証したいことがより中心にある動機だったように思います。
⑵個人:自ら他者に働きかけ、巻き込むことで何が見えるか
ライターさんやクリエイターさんに自ら依頼する
チームを自ら組成する
制作資金の獲得やWebメディア上での掲載に自ら動く
二つ目は個人的な観点です。これまでの自分自身のフリーランスの活動は、基本的にまず誘われてから動く受動型でした。なので、今回は自分から問題を発見し、企画・提案・チーム組成まで行う能動型で仕事をしてみようと考えました。研究員第3期テーマに掲げられていた「運転席に座る」というやつですね。
新たな領域に踏み込んだときに、どんな世界が見えるのか。自分はどうなるのか。それを検証したいと考えました。
【活動と制作物】
『Rosen-zu』に掲載するプロトタイプを1記事制作。
(作成質問リスト×2,実施インタビュー×1,文字起こし×1,構成案×1,記事×1)
制作資金獲得⇒獲得できず。プロトタイプ作成のため、自腹で制作。
(イラスト依頼料)かねてより仕事を依頼したいと思っていたえの季さん(研究員1期生)に依頼、路線図のイラストを依頼。


今回のプロジェクト中に関わったのは自分を含め4名 インタビュアー兼ライター・北原 インタビュイー・もんちゃん イラストレーター・えの季さん、 期間中メンターをしてくださっていた榮田さん
メディア掲載にあたって相談に乗ってくださり、協力してくださった方々も4名 市川瑛子所長 ハリーさん(PM) シモカタセイジさん(サブPM) ハマさん
関わってくださったみなさん、本当にありがとうございました😭 シモカタさん、ハマさん、LOY受賞おめでとうございます!
当初計画していた複数記事から路線図を体系化するところまでは行けませんでしたが、プロトタイプを制作するところまでできたのは良かったです。
【⑴制作物の過程・検証・考察】
さて、ここから振り返ります。
「やるぜ、ウェーイ!」と息をまいたものの、制作ではいきなり壁にあたってしまい、当初の構想とアウトプットの形自体はそこまで変わっていないのですが、目指すものが大きくピボットしました。
Rosen-zuというメディアのコンセプトに沿ったものを作ろうと思ったら、現行のRosen-zuからズレてきた。
という現象が起こりました。あ、あれ、おかしいな。なぜそんなことになったのか。それがコレです。▼▼
同じようなターゲット、課題解決を目指すメディアはすでにある
『Rosen-zu』は、未来のじぶんと「つながる」メディア。
①読者は「じぶんらしい働き方」を模索してフリーランスに興味を持った人、またはフリーランスとして働いている人に設定している
②「新しい働き方LAB」で活動のそれぞれの働き方を記事化することで、①の読者が「未来の自分」と記事で出会い「つながる」ことをコンセプトにしている
と、僕は捉えました。
でも、『Rosen-zu』立ち上げから数年、今すでに同じ領域には素敵なメディアが確立されていました。
編集体制も確立され、しっかりと動いているものがすでにある。
『路線図』というものを核に据えているので、もちろん打ち出し方は違うのですけど、根本的には一緒であるように思えました。
そもそも、誰かが形にして、すでにソリューションを提供しているものにチャレンジする必要はあるのか?と考えると、僕にとっては「NO」。方向性を変えた方がいいのでは?と思ってきました。
「コミュニティ」だからこそのコンテンツも形にならなかった
もちろん、ターゲット層がほぼ一緒でも『Rosen-zu』は『新しい働き方LAB』というコミュニティに紐付くメディアという違いがあります。
「コミュニティだからこその『つながり』という部分を活用して、ネットワーク内で先輩にインタビューできるという機能を持たせたら、まったく別の機能を果たすメディアになるんじゃないか?」
そう考えて、LAB内の先輩にインタビューしてそれを記事化するコンテンツでいこうと考えました。
これは、数年間編集として関わってきた若者向けキャリア探究メディアで実験して手応えを掴んでいて、そのノウハウが使えると思ったからです。
で、実際、1回目のインタビューをこれで進めようと思ったのですが、つまづきました。
まず僕自身が「こんなことが聞きたいです」とインタビューしたい人に相談したのですが、「ちょっと難しい」という回答をいただきました。質問リストを見返して改めて考えると、確かになと。
大人が大人に「聞きたいこと」を聞くと、興味や悩みのポイントは絞られます。そこにインタビュイーが答えられるか、答えられる状態にあるか、答えられたとしても記事にするのが適切な内容になるかは、若者がするそれに比べてずっと難しい気がしました。読者が聞きたいことにフォーカスしてインタビューをしても、それがインタビュイーにとって心地良い体験、心地良い記事になるかというと、怪しい。
結果、この企画の在り方も再考せざるを得ませんでした。
インタビュイーのための記事にする
未来のじぶんと「つながる」メディア
キャリアを「路線図」に落とし込むコンセプト
じぶんらしい生き方や働き方を見つけるヒントになる
これらはとても魅力的。でも、今からメディアで記事を作っていくとすると、当初の方向性でつくってもおもしろいと感じられなさそう。どうしよう。ここまで詰まったところで、僕は開き直りました。
だったら戻って、一から考え直すしかなくない?
考えた結果、すでにあるRosen-zuのコンセプトの形ともしかしたら違うものになるかもしれないけど、これは自分の自主企画。自分が「価値がある」と思えることをまず追求しよう。
ということで、さまざまな前提を疑い、自分自身の感覚に正直になって根っこから考えなおすことにしました。
①”読者のための記事”って、なんだ?
フリーランスのためのWebメディアだけど、既存のメディアと違う打ち出しをする。そのために、まず「読者って誰?」とか、「そもそも読者のために記事を書くのか?」という前提を疑ってみることにしました。
よく、Webメディアで「読者ファーストです」「読者に役に立つ記事を書きましょう」「読んでもらえなければ意味がありません」、という言葉を耳にします。
確かにそうです。記事を書いても、読み手がいなければ望んだ効果は発揮しない。 読もうと思えない記事は、届かない。それは間違いない事実。だけど、ついこの言葉を単純化して思考停止してしまう気がしていました。
でも、「読者」って「誰」なんでしょうか?
もし読者が検索するフリーランサーの方々だったとして、本当にその人達をファーストに、僕は記事を書きたいのか。
インタビューで生き方をシェアしてもらい、記事にする。その行為を見知らぬ読者を一番に考えて行うか?
段々違和感があぶり出されてきました。
これは、誰かの生き方や働き方、キャリアに触れる内容を常にインタビューしてきたからなのかもしれません。色々考え始めます。
インタビューを通して語られるその人のキャリアは、いつも驚きに満ち、個別の素晴らしさを持っていると感じてきた。
インタビューという時間は、その人が生きてきた道のエッセンスを凝縮して聞かせてもらえるもの。
自分自身、いつもそのことに深い感謝と喜びを感じ、記事の制作においては最大の敬意を示したいと思ってきたはず。
読者のために書く。それはもちろんだけど、もっとその前に、大前提として据えておかなくてはならないのは「インタビュイーの思考やキャリアが尊重され、記事の発信がインタビュイーためになる」ということではないのか?
メディアがどうのこうのという枠組を超えて、キャリアインタビュー記事制作で僕にとってまず大切なのは「インタビュイー」だったと、気づいてきました。
ここまで来て、なんとなく腑に落ちるイメージが湧いてきます。
そもそもの考え方を逆にした方が考えやすいのではないかと。関係性の遠いまだ見ぬ読者からではなく、記事制作の一番近いところから、読者を考えていってはどうか。
キャリアインタビュー記事制作の最初の読者で、最も真剣に読む人。それは「インタビュイー自身」ではないか。
ここに行き着いて、すごくしっくりきました。
そう、キャリアインタビューの記事は、インタビュイー自身のためにまず書きたい。僕にとって、この感覚は外せないもの。これを言葉にしたら猛烈な勢いで思考が回転いきました。
読者の興味や読み物としての面白さを優先するあまりにインタビュイーへの敬意を欠く記事を自分はよしとしない。
人のキャリアストーリーは、語りによって認知可能になるもの。
それは常に一定ではなく、「誰に語るか」によって変化するという性質があるし、文脈から切り出されることによっても意味は容易に変化してしまう。
生き方に触れるインタビューを行うなら、インタビュイーの存在をまず中心に据えたものにしないと、その人の生き方そのものをねじ曲げて世に出すことになる。
だから、まずインタビュイーから考え始める。
ファースト読者がインタビュイーであるとすれば、そのインタビュー記事を読むことで、その人のキャリアや価値観にこそ最大の効果をもたせたい。
『Rosen-zu』の中の記事なら『新しい働き方LAB』の中で”じぶんらしい働き方”を模索してきたインタビュイーが、改めて自分の語りから発生した”じぶんらしい働き方”と出会い、その先の”じぶんらしい働き方”の形成が加速するものなら良いのでは?
第一の機能としてインタビュイーにとって、言語化、統合、図案化された”じぶんらしい働き方”を客観的な視点で見つめることで、それを起点に”じぶんらしい働き方”を作っていけるようになるのではないか。
そういう考えに至ってきました。
②じゃあ、その次に記事を誰が読むの?
もちろん、インタビュイーにとって意味があっても、インタビュイーのためだけのものがもっとも役立つものかというと、そうではないはずです。
自分のキャリアストーリーをWebメディアという媒体に載せることでこそ生まれるメリットもあるはず。それに、「自分の生き方が誰かのためになること」は、やはりインタビュイーの望むところのはず。
では、近いところから順に読者を考えていくことにしました。
インタビュイーの周辺から考えていくと、次はインタビュイーの知人・友人・関係者です。インタビューされたことを周囲の方々に知らせる自然な流れが生まれます。この人達に「そう、この人ってこういう人なんだよな。これからも応援したいな」と思われることで、インタビュイーへのアクセス経路は広がっていきます。
次の読者は、その人のことをこれから知ろうとする「出会ったばかりの人」、「これから出会う人」になるでしょう。
たとえば「北原泰幸」と出会い、ライターだと知って興味がわいた人は「どんな人なんだろう」と調べますよね。フリーランスとしてどんな実績があるのか、どんな人なのか。
また、まだ会っていなくてもその人とこれから会うことになった人がいれば、相手がどんな人か知っておきたいので情報収集として調べるだろうと思います。(もちろん日常の約束程度ではそうはなりませんが)
フリーランスにとって自分がどんな人間であるのか、どんな仕事の仕方をしているのかを伝えることはとても重要です。それぞれが働き方に自由度を求めたり、大切にしている信念があったりするからこそフリーランスをしているわけで、そこのすり合わせをきちんとしておかないと、お互いにとって満足のいく仕事が成立しないからです。書いていて気づきましたが、フリーランスでなくてもそうかもしれませんね。
ですが、キャリアのストーリーは、単純ではなく説明が難しい。目に見える経歴の根に這う内的キャリア、時々で大切にしてきた価値観を説明するのはなおさらです。だからこそ、こうした新たに出会う人達に、整理して伝わりやすいキャリアの記事があることは大きな価値を生む気がします。
その次がコミュニティ自体に興味がある人でしょうか。『新しい働き方LAB』のことが気になり、どんな人がいるのか、どんなコミュニティなのか、どのようなじぶんらしい働き方を模索できるのか、それらを知るのにWebページ上から『Rosen-zu』に到達する。おそらく、これがもともとの想定読者ですが、この期待にはしっかりと応える必要があります。そして、コミュニティに興味を持っている人は、高い確率でインタビュイーとコンタクトをとる可能性がある人になるはずです。
そして、最後がフリーランスの仕事に興味がある人達で、検索で流入する人達です。
インタビュイー⇒知人・友人・関係者⇒インタビュイーとこれから出会う人⇒コミュニティに興味がある人⇒フリーランスに興味がある人の順に並べたとき、最大のターゲットになるのはインタビュイーとこれから出会う人で、次点がコミュニティに興味がある人ではないかと考えました。
③このメディア・企画で何が実現したいのか
「インタビュイーのためになる」ということを大前提に据えたキャリアストーリーメディアで、インタビュイーがこれから出会う人を最大の読者として設定する。
ここにRosen-zuの、
未来のじぶんと「つながる」メディア
キャリアを「路線図」に落とし込むコンセプト
じぶんらしい生き方や働き方を見つけるヒントになる
というコンセプトをもう一度流し込んで考えてみることにしました。
新しい働き方LABは、それぞれがじぶんらしい働き方を模索する共創型コミュニティ
『Rosen-zu』にはじぶんらしい働き方を一定期間模索し、その形がおぼろげながら見えてきた人のキャリアストーリーが掲載される。
掲載されたフリーランスの方とこれから出会う人が、『Rosen-zu』上で記事と出会う。それによって路線図の先を読み手が想像し、「この人にはこんな仕事をお願いしたい」とその人らしい新たな働き方をプロデュースしたり、提案したりしたくなる。
出会いの質がより濃密になる。
インタビュイーが『Rosen-zu』というメディアによって「未来のじぶん」と「つながる」。
こうしたインタビュイーを見て、「自分も新しい働き方LABでなら、じぶんらしい働き方を見つけられるかも。一緒に自分の働き方を創っていける人達と出会っていけるかもしれない」と、コミュニティに興味を持った人が思い、コミュニティが活性化していく。
おお、イイ感じ!
これならメディア自体がコミュニティの機能として働き、コミュニティの参加者・コミュニティの運営者・コミュニティの外部の人達に対して価値のあるものになりそうな気がしてきました。
「『Rosen-zu』には、フリーランスとして個性の光るおもしろい人達が載る。フリーランスとして一緒に仕事をしたい人を探すなら、このメディアをチェックしよう」
そうやって注目されるメディアになれば「フリーランスはたくさんいすぎるし、マッチングがうまくいかない問題」に対するソリューションの一つになりうるんじゃないかと、ワクワクしてくるところまで持って来られました。
そうして出来たのが、今回の路線図インタビュー記事のプロトタイプです。これを読んで「やばっ、もんちゃん最高!」「もんちゃんとこんなコンテンツ作りたい!」「こんなもんちゃんとならこんな新しい最高の仕事ができそう!」と思う人が出現したら、大成功。
このあたり、読み進めた方で「いいね!」とか「もっとこうでは?」とか思うところがあった方はぜひ教えてください🙇
【⑵自分自身のチャレンジの過程・検証・考察】
計画との大幅なズレ。
計画時は第1ステージから第6ステージまで設定していて「10記事ぐらいできたらいな」なんて考えていたんですけど、このあたりの数字は全然達成できませんでした。
原因は下記です。
同じ時期にWebメディアの立ち上げが仕事として舞い込んだ
もともと関わっていたWebメディアのリニューアルが重なった
個人で行っている中学受験サポートに大きなウェートを割いた
わが子の創作サポートや地域活動に時間を割いた
純粋に自分の優先順位の中で、研究を上位に上げることができなかった。これに尽きます。ライターの人にも期間内に結局依頼できずでした。感覚の合うライターの方々とも出会っていきたいなというのは、編集長業務を今年担うようになって日々重要だと感じてはいるのですが。
でも、やってみてよかった
実際、自分で企画を動かそうと能動的に動いてみた結果、気づいたことは以下でした。
やっぱりコンセプトって大事。何のためのWebメディアなのか。何のための企画なのか。
そもそもの言い出しっぺである自分が考える大事にしたいこと、判断軸が何より大事。話せるようにするにはコンセプトを煮詰める必要がある。
が、それは手を動かしながら対話しないと見えてこない。
あやふやながらもこちらの意を尊重して付き合ってくれる信頼できる少数の人の協力のもとプロトタイプを作る必要があった。
プロトタイプがあると、協力を依頼しやすい。
プロトタイプを作る中で、ゴロゴロと気づきが生まれた。
自分自身が「この人と仕事をしたい」と思った人と仕事をしたいし、なんとなくでチームに誘って「やっぱりごめんなさい」はしたくないし、ノンアクティブなメンバーを生むことは好まない。
プロジェクトを動かすと考えることが異様に多く、連絡する関係者も増える。忙しくもなり「連絡漏れ」が生まれやすくなることがわかった。
この状態になって初めて「あ、みんな忙しいんだ」と「リマインドしてもらえるって、結構助かるんだ」と思えた。リマインド連絡を躊躇しなくなった。
Rosen-zu含め、期間中4つのメディアについて編集として関わっていたので完全にキャパオーバーだったのですが、この視点での学びは大きく、やってよかったと感じました。
自分がやりたいことと、人とどう共創したいか
メディアを一から作る経験も期間中する中、『Rosen-zu』というメディアの企画作りを能動的に行うことで、「自分の時間と能力を使って、何を社会に提供したいのか。何ができるのか。」という問いが自分の中で熟成されたように思います。
クライアントワークをしている間はどこか「選んでもらう側」で、「誰かのやりたいこと」を一緒につくったりサポートしたりするイメージがあったのだと思います。でも、自ら企画して動くようになって中心になってきたのは「自分のやりたいこと」は何かということ。
「一人では作れないそれを、誰とどのように共創するのか」という問いの中で、自分自身の在り方、どんな人と一緒に働きたいのかという「選ぶ」としての視点が生まれてきました。
僕は、インタビュイーのために機能するWebメディアを作りたい。
すでにあるメディアと同じものなら、作る必要は感じない。
誰と一緒にするかは、自分で選びたい。
判断に迷えばアドバイスを求めるが、決断は自ら行う。
これらは、この実験以前にはハッキリと言語化できていなかった自分自身の感覚です。
以前よりもずっと判断力は増しました。それは良いか悪いか「自分の感覚ではどう感じているのか」を言語化して、それを信じられるようになったからだと思います。
【今後】
コミュニティにたくさんの研究員さんがいて、多くのメンバーで共創している人が多かったですよね。頑張って活動して、成果をあげる人達を横目に「相変わらず僕はマイペースに、大きな流れの中に入っていないんだよなー」と自分にモヤモヤしなかったわけではありません。
でも、半年第3期を活動してみて、「三期という枠組に限らず、自分が偶然にもコミュニティ内で出会うことが出来て心惹かれた人とプロジェクトがしたいんだ」という思いに気づけました。
そんなところから依頼したえの季さん。出来上がってきたグラフィックは自分が思っていたよりもずっと素敵なもので、「人にお願いするって、こういうことか」と、誰かにお願いする喜びを感じる得がたい経験にもなりました。
2024年1月からすでに仕事がカツカツなので、この自主企画をどのタイミングでどれだけ進めていけるかは分かりません。でも、また自分でこのプロジェクト続けていくなら、多くはないかもしれないけれど、僕は自分が一緒に仕事をしたいと思える人と進めていきたいと思っています。改めて、『Rosen-zu』のコンセプトってすごくいいと思うし、携わりたいです。
あ、もちろんこんなロングな報告書を読み切ってなおかつ「コイツおもしれぇな」「ちょっと喋ってみたい」って思ってくださる奇特な方は、高確率で合う気がするのでぜひお友達にならせてください🙇
『Rosen-zu』というメディアにこうした実験的な記事を載せさせてくださった関係者のみなみなさま、ありがとうございました!
そして、自分のキャリアを快くシェアしてくれたもんちゃん、忙しい中イラストを書いてくださったえの季さん、期間中メンターをしてくださった榮田さん、本当に感謝です!✨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
