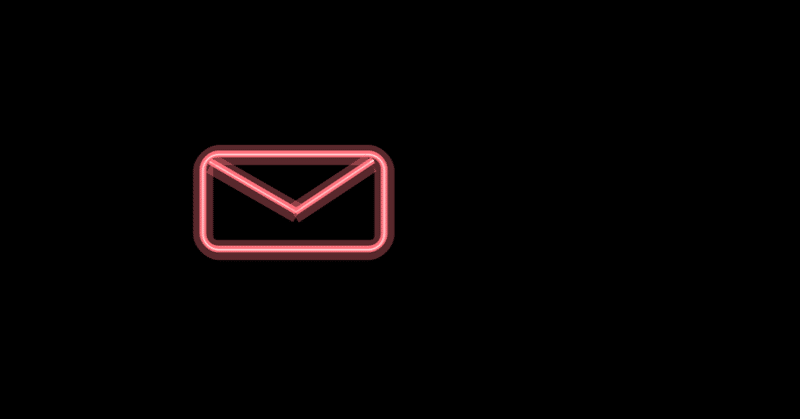
ネオンピンクにあなたの名前
〈着いたよ〉の文字が光って見えた。
鏡を見ながら前髪をつまんで整えて、〈着いたよ〉の文字をもう一度、眺める。声が聴こえる気がして不思議だった。
両親の寝静まった寝室の横を泥棒のような足取りで通り抜けて、階段を降りる。玄関ドアはどうしても音が立ってしまうから、下駄箱から黒のコンバースを選んで持ってきて、かつて祖母がいた部屋の窓からそっと落とした。「この部屋がいちばん安全だから」悪びれずにそう言った17歳の姉の勇敢さを思い出す。同じことをしている今、私もあの頃の姉みたいに勇敢だろうか。
外へ出ると、霧雨だった。1秒でも早く駆け付けたくなって、急いで窓を閉めた。
真夜中に、暗闇を見上げて走っている。ドラマの中でだけ起こる現象だと思っていたのに、誰かに会いたいと、人は本当に走るらしい。ミストのように柔らかい雨が降っていて、祝福のように優しかった。空には細い月も在って、“こっちだよ”と教えてくれていた。
最寄りのコンビニの駐車場の真ん中に、ぽつんと一台車が停まっていて、目を凝らすと中に君がいた。息を切らしてドアを開けると、まるで昨日も一緒にいたような眼をした君が私を見ている。
「そんな、走らなくていいのに」
「早く会いたかったから」
きっと乱れている前髪を手櫛でなおして、躊躇いなく差し出される手のひらに自分も躊躇いなくそれを合わせた。
助手席も君の隣も、だいぶ体に馴染んだ。走り出した車のドリンクホルダーには、いつも通りジュースを刺してくれていて、今日は大きな瓶だった。
「これ、飲みたいって言ったやつ! 嬉しい、持ってきてくれたの?」
「うん。一緒に飲むために買ったから」
「ありがとう」
そのジュースが入った瓶は、底がホルダーの直径とほぼ同じだったせいで刺さりきらず、不安定に揺れていた。落ち着きがなくて、可笑しくて、そしてここにある。
「あれ? これ飲みかけ? しかもまあまあ減ってる」
「うん、一緒に飲むために買ったから」
なんの遠慮もない。思わず笑っていた。
「私、この大きさの瓶でジュース飲むの初めてだよ」とさらに笑ってから飲む。「美味しい!」と率直な感想を伝えると、「まあ普通のジュースだけど」と何度も言うので、君も嬉しかったのかもしれない。
少しぬるくなっていたジュースがとても美味しかった。
君がここにいてくれることは私の人生に起きた奇跡だよ、とたくさん伝えたかった。君が私に降る雨に似ていることも。
幼い頃、深夜に父の怒鳴り声で目を覚ますと、姉を追いかける父を、母と祖母が追いかけているところだった。
まるでぶかぶかの服を着たこどものように不自然なメイクをした17歳の姉がいて、その姉を捕まえた父が、こぶしで頭を2回殴る。家に男は父しかいないから、こんなとき、父の衝動を止められる人間が私しかいなかった。母も祖母も、簡単に振り払われてしまう。
私はその頃9歳で、身長は140cmもなく、誰がどう見てもこどもであったし、自分がこどもであることもよく知っていた。
駆け寄って、姉の体にしがみつく。怖くて声は出せないけれど、次に殴られるかもしれない体を、とにかく庇う。父は幼いこどもに手をあげない人だったから、暴力はそこで止んだ。
母を振り返って「おまえの育て方が悪いから、こんなことになるんだろうが!」と捨て台詞を吐くと、父は部屋を出て行った。強がりから解放された姉はしゃくりあげて、母は姉の背中をさすりながら声をかけていた。私を布団まで連れて行くのは祖母の仕事だった。深夜にこんなことがあって、落ち着かないのは祖母だって同じだろう。けれど、こどもの私はどうしても優先されてしまうから、大丈夫、という代わりにいつも寝たふりをした。
だけど、どきどきは簡単に治らなくて、再び父が怒鳴り出すのではないかと、目を閉じたまま耳をそばだてていると、ときどき、雨の音が聞こえた。
窓の外、屋根の上、じっと耳を澄ませていると、自分が透明のカプセルの中で、雨に守られているようで気が和らいだ。
君はあの頃の雨に似ている。
たとえば5月の、午後5時過ぎのクリーム色にくすんだ街の空気は、銀色夏生の古い詩集のイメージだから、思い出したら景色を見てみてほしいってことを伝えたい。ほんのいっとき、クリーム色に染まる風景では、家も木も人も車も、柔らかい。きっと何かの物質が他の時間帯よりも軽いんだ。
美味しい、と思うものがよく一致して嬉しかった。カウンターで焼き鳥を食べた日に、「甘いだけのジュース」と君が表現したピンク色の飲み物の味を、なぜか今もしっかり覚えている。そのとき幼い頃にずっと飲んでいたネオンピンクの薬を思い出したことも。
君が連れて行ってくれて気に入ったあの店の名前が、自分の中で未だに曖昧。ふたりで夕暮れの土手に寝転んだとき、これも青春、と感じたこと。君がお菓子を口に入れてくれるペースが、ちょっと早過ぎて焦ったこと。家に同じ本があっただけで、密かに運命を感じたこと。
実はよく笑う人だと知って、未来でも、変わらずふたりで笑っている気がしたこと。
誰かと心が通じることを、そんなの無理だよって諦める自分と、切望する自分とがいた。こんなことを言うのは恥ずかしいけれど、ここにいていいよって誰かに優しく言われたかった。そしたらちゃんと、そこにいたかった。
私たちはほとんど真逆のふたりで、よくお互いを驚かせた。それでもなぜか、ふたりでいると心が強かった。君はにやけながら私を見て、私が近づくともっと近づいた。
熱さを表に出さず隠し持っていて、泣くことも、怒ることも、笑うことも、喜ぶことも、少しずつ遠慮してきたような君にはきちんとした体温があって、世界でただひとり、生身の私をあたためることのできる人間だった。
車のほとんど走っていない夜更けに海へきて、エンジンを切ると、細い雨の音がした。だだっ広い駐車場に、人影も車もない。
両親が起き出す前にベッドに戻っていなければならないし、窓から入る姿を、近所の誰かに見つかるわけにもいかないから、ここにいられるのは午前4時まで。
君がアラームをかけてくれて、私の眼を見つめた。
髪を撫でたり頬に触れたりする大きな手にされるがままになる。「可愛いなぁ」と口癖のように言う君は、私の好きなところベスト3を自主的に発表してくれることがあったけれど、毎回、性格が顔に負けていた。すごく幸せで少し複雑だ、と考えて「あのね、年を取れば顔は崩れるよ」と現実を伝えると「俺も年を取るよ」と当然のことを当然のように君は答えた。まるで、もうずっと一緒にいるよ、と言われたみたいで、体中に水分が行き渡った。雨の音がはっきりと聞こえて、ふたりきりのこの車が、あの頃の雨のように優しかった。
車を降りるとまた霧雨だった。
終電が去った小さな駅のホームはしんとして、白かった。
薄い体にワンピースを着た私がぼんやり立っていると、君が来てパーカーを着せてくれた。フードまで被せて、そのまましばらくじっと見下ろして、黙って見上げている私を強く抱きしめた。
私たち以外、ほんとうに誰もいないところまでやって来たみたいだった。
「愛されたいって、初めて思った。今まで思ったことなかったから」
呟くように君が言って、出てきそうな涙を堪えた。ずっと遠くで生きてきた君の、感じることに蓋をしてきた歳月の痛みが、合わせた心から流れてきた。
その蓋を、できるだけ丁寧に、怖くないように、時間をかけてふたりで開けよう、そう誘いたかった。自由になっても大丈夫だよ、君にはもう、私がいる。
真夜中の海と空の境は曖昧だったけれど、色とりどりの漁火が煌めきながら揺れている。砂浜に延びたふたりの影はひとつみたいに重なっていて、君と手を繋いでいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
