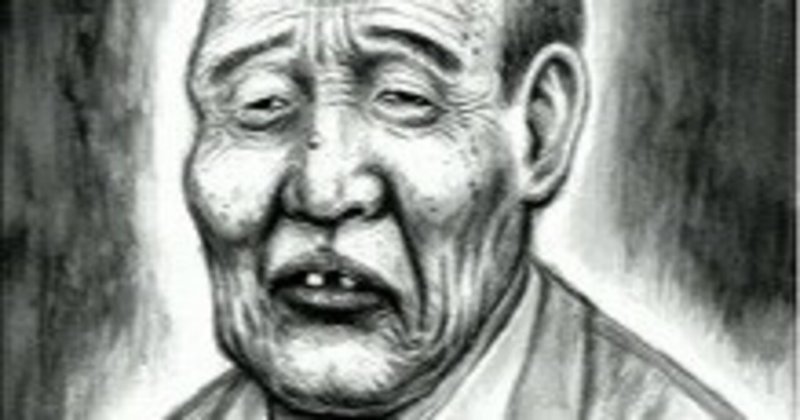
おじさんがいちばん美しいって感じるものって、なに?
おじさんは3秒間考えた後に答える、「モナリザ!」
ぼくは爆笑してしまう。だって、それは嘘だろ、っておもうから。こういうふうにおじさんは(けっして自分の心に問いかけることなく)つねに無難な答えを探してしまう。逆に言えば、おじさんがふだんの暮らしのなかで美に心を動かされることがないことが、このせりふでバレてしまう。
美はどこにでもある。夜明けの昏青い空。近所に咲いている淡いピンクの薔薇。どこにでもいる鳩のなかにだってときに美しい鳩もいる。ふんわりした髪と優しい笑顔のスーパーマーケットのレジ打ち女性。一本のステンレス製のフォークにだって美しいものはある。わざわざレオナルドを借りてくる必要はありません。
では、(デザイナー、ミュージシャン、美容師、陶芸家などを除いて)なぜおじさんは美と無縁に生きているでしょう? その理由は、なるほど美に値段がつくことはあるし、美人コンテストなんてものもあるとはいえ、しかし、美そのものはけっして序列化できず、また情報化もできないからでしょう。いまの世の中、情報化できないものは存在しないと同じです。
つまり、男はおじさんになると収益、効率、法秩序、人事そのほかにがんじがらめになって、いつのまにか情報社会にすっかり適応してしまって、結果、美を感じる心を失ってしまう。なるほど、おじさん社会でもしも美なんてものに気をとられていたならば、仕事のできない奴と見なされてしまいかねません。おじさんの哀しみはそこにあります。
したがって、そんなおじさんがカネ持ちになってグルメを気取ったところで、ミシュランやゴエミヨを読み漁って、名店を食べ歩いたりするばかり。(もしもその経験からなにか感じるものがあるならば、それもまた楽しいでしょうけれど。)同様に、おじさんが定年退職して風雅に目覚めたならば、春には「桜の名所百選」とか読んじゃってトップ3を見に行ったり、秋には「お勧めの紅葉の名所」を参照してラコステのヤッケなど羽織ってウォーキングシューズ穿いて出かけたりする。(もしも旅の途中でおじいさんが山頭火の俳句でもつぶやいてくれたならサイコーです。)たしかにそれもまた楽しいとはおもうけれど、ただし、逆に言えばそれは美の基準を社会に奪われていることでもあって。どこまでいっても、おじさん~おじいさんは哀しいもの。
1992年当時22歳だったアイドルでミュージシャンの森高千里さんが自作の詞で『わたしがおばさんになっても』という挑発的な歌を歌って、年長女性たちをむかつかせたもの。もっとも、この歌詞じたいにはリアリズムがあって、〈いまの自分は若い娘だけれど、しかしいつか自分もおばさんになってゆくという不安〉が吐露されている他方で、〈なぜ、男はおじさんになっても若い女が好きなのか?〉という疑問を男たちに突きつけてもいて。さらに踏み込んでいえば、〈あのね、おじさんの若い女の子好きは恥ずかしいものなのよ〉というおじさん批判さえも匂わせています。フェミニストはこの歌を高く評価すべきでしょう。
いまではその森高千里さんご自身が該当年齢におなりになりましたけれど、しかし、彼女はいまも美しく溌剌としてらっしゃいますね。すばらしい!
さて。では、おばさんが哀しいかと言えば、おばさんはちっとも哀しくありません。なぜなら、おばさんはけっしておじさんほどには頭でっかちではない。しかも、女は若いときから髪型、化粧、服の着方に習熟していますから、人それぞれに美の基準を持っています。だから、おばさんは美がどこにでもあることをわかっています。なにげないものに美を感じる心があるからこそ、平凡な日常を楽しく生きてゆける。他方、おじさんにはそれができない。世に熟年離婚が増えている理由の一端がわかろうというものです。
そもそも美とはなんでしょう? もしも美に関心を持つ少年少女が大学で哲学科を選び美学を専攻したとしても、おそらく待っているのは失望でしょう。それでもカントはこう考える、〈善/悪〉〈真/偽〉〈美/醜〉はそれぞれ別の審級に属している。すなわち、美は善悪や真偽では測れないものであるということ。なるほどたしかにそのとおりではあるのだけれど、逆に言えば、そういうふうに外堀を埋める(cut a clear pathする)ことによってしか、美をとらえられないことを示しています。余談ながら、美という字は支那の言葉では〈大きな羊〉に由来しています。もはやなにがなんだかわかりません。
なお、画像は漫☆画太郎先生の作品をお借りしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
