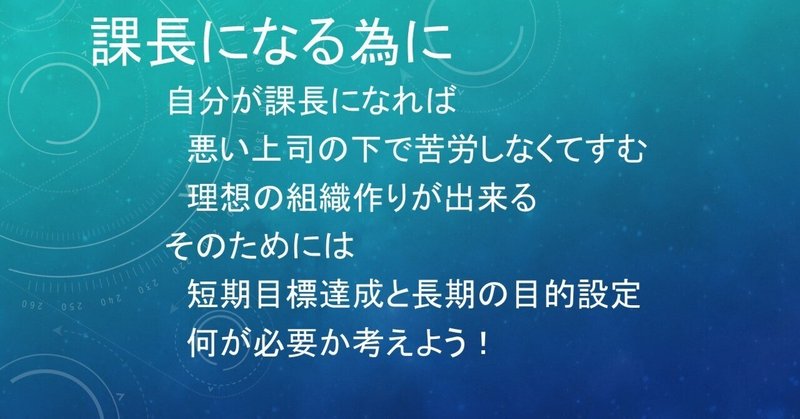
課長になる為に
1.課長になるべきか
今の世の中、管理職への昇進を望まない人も増えています。何も考えずに課長と言う立場ばかりを求める人よりは、課長になるべきかについて真剣に悩んだ人材こそ、課長になるべき資格と言うか値打ちがあると思います。
「何も考えずに、なりたがる人より、周辺が求めてなってほしい人」
が、課長になるのはまだ望ましいでしょう。しかしながら、例外もあるが、いやいや課長になるよりは、理想や希望に燃えて、課長になる人の方が、周囲の人間と会社にとって、もっと良い結果をもたらすこでしょうでしょう。
以下に課長になることのメリットと、課長の立場について改めて見直してみました。
1-1課長になるメリット
課長になると何が良いでしょう?一般的には、以下のように考えられています。
1)ステータスの変化
特に社外での人の見方が違って、名刺の力が出る
2)収入
管理職にならないと収入は伸びない
しかしながら、管理職になるもっと大きな意味と言うか、喜びは以下の点にあります。
末端とは言え、経営に参画し、自分の意向を入れることで、自分が持っている理想の組織とその運営の実現が出来る。
これは逆の見方をすれば
「悪い上司の下で、苦労せずにすむ」
と言うことです。自分の失敗や能力不足ならあきらめもつくが、無能な上司に自分の運命を狂わされるつらさは、体験した者にしかわからないが、定年前ごろになると重くのしかかってくるものです。
他人を変えることは難しいが、自分を成長させることは、自分の努力で出来ます。
自らがチャレンジしないで、後で後悔するより、与えられた機会はできるだけ生かすべきでしょう。
1-2課長の立場
課長の立場は、最低限でも経営に関与してきまう。従って、会社側の立場で、物事を考える必要があります。このため、以下の疑問に答えられるようになっておくべきです。
1)会社とは何か?
2)給与はなぜ支払われるのか?
「会社とは?」と言う疑問に対して以下の答えがあります。
会社は、顧客の必要とするモノを、継続的に供給する仕組みを維持するために存在する。そのために、必要な人材や設備を確保し、会社を維持するための適正な利潤を得るように努力する。その実現のために、関係者の満足を得るように努力する。
ここで大切なことは、「お客様の必要とするモノ」と「継続的に供給」、という2つのキーワードです。お客さんの求めていない物は、いくら良い物でも売れないでしょう。また、一時的な活動なら、ボランティアでも対応できるが、継続的な供給となると、しっかりした組織が必要であり、これを維持する為には適正な利潤が必要です。
次に給与に関しては、以下のような考え方があります。
まず生産体制維持ということで、労働力の維持と言う側面があり、そのためには生計を維持できる給与というのが最低限必要です。一方、労働者の貢献に報いて、利益の配分と言う発想があります。これは売り上げ等の成果が反映します。また、労働力の商品価値として、他社に引き抜かれない為の世間相場を加味した給与設定も必要になります。

一方、賃金を管理する立場では、総額を管理する適正人件費管理と、個人に対する適正な評価としての個人別賃金の管理があります。このような見方に切り替えることが課長になる条件です。なお人件費の構造は以下のように、単なる給与だけでないことに注意すべきである。

なお、報酬は賃金だけでなく、広く考えるべきです。無形報酬を上手に使い、従業員の満足度を高めることも、管理職の重要な仕事です。

2.課長の業務
課長の業務は、通常の業務遂行に関係する短期的なものから、市場構造を予測し対応する組織の姿を構想する長期的なものまで広がっています。現時点での収益を確保する短期の仕事をきちんと行うことはもちろん重要ですが、将来的に経営面の要求に合った組織であるように、戦略的な対応を考えることも重要です。片手の算盤(年度計画の達成)と片手のロマン(長期戦略による理想の組織作り)の両立が大切です。
ドラッカーの言う経営者の貢献は以下の3つですが、同じことを言っています。
(1)直接の成果を上げること・・・年度計画の達成
(2)価値の創造と価値の再定義・・市場拡大の戦略
(3)明日のための人材の育成・・・成長のために内部能力の充実
このように短期の成果と、長期の成長を考えるのが経営者の仕事です。
なお、課長業務の成果は、あくまで組織としての成果が評価されるのであって、例えプレイングマネージャーであっても、実務成果ではありません。実務の成果で部下が表彰されることが、課長の勲章です。
管理職は
「部下を頼るようになって一人前」
とも言われています。それだけの部下を育てることが管理職の義務です。プレイングマネージャーでも、実務においては部下に負けるといえる様に、後継者育成をしっかり行うべきです。
3.短期的業務
管理職の仕事として、まず大事なことは、日常の組織運営です。業務の計画をしっかり立て、実行している状況を確認し、必要に応じてフォローや支援を行います。そして、計画齟齬の理由を明らかにし、その上で改善活動を行います。この中で、各人のモラルを維持する為に、適切な評価とフィードバックを行うことも重要です。

表3に業務概要と分担を書いたが、組織としての方針を決め、皆に周知させる、特に、品質を優先するのか、利益を優先するのかなどの価値観をしっかり定めることが大切です。この部分は、組織のトップの責任です。部下と相談しても良いが決断はトップの仕事です。なお、組織としてのルールつくりは、できるだけ部下を参画させて作ることが望ましいが、各種利害関係を調整し決定するのはトップの仕事です。
次に実際の業務遂行に当たっては、計画をきちんとすることが大切です。個別の計画は、業務のリーダー達に任せる場合もあるが、しっかりした人員配置が出来ているか、資源の投入は適切かの評価を、きちんと見るのは課長の仕事です。また、業務関係者の動機付けをしっかり行うのも課長業務です。その後実行に関しては、上手く言っている間は余分な口出しはしないが、
他部門や担当者間で調整する事項が出たら、調整業務を行います。更に支援すべき時、修正すべき時には、時期を失わずに介入して傷口を広げないようにします。なお、必要資源が不足している場合には、部下の意見などもよく聞いた上で、管理職が必要性を決断しないといけません。より上の立場の人間に対して、その職場として最善の検討をした上での、必要資源である旨を説得しないといけません。このための決断と説明の責任は、管理職にあります。言い換えると、部下のレベルで、「~~が欲しい」は、我儘や言い訳になるが、管理職の「~~がないとできいい」は、立派な経営判断です。それだけの重みを感じることが大切です。
最後に業務が完了した後は、正しく評価を行います。そして必要があれば、改善活動を指示します。その他、朝礼などの機会を通じて、よいモノを褒めることは、価値観の教育に有効です。
集会や会議を上手に使い、良し悪しの具体例を示しながら、価値観の普及を図ることは、組織の一体化を図るためにも有効です。
各人の動機付けをきちんと行う為には、自己申告や面談などの形式的なツールの活用も大切ですが、常日頃の対話も大切です。特に課員の話を聴いて、相手を大切にしていると言うことを伝えて、納得して仕事を行うようにもっていく、これが動機付けの有効な手段となります。自分が個人として大切にされているとわかれば、例え自分の仕事がなくなるような大胆な業務の改善提案も行えます。
更に、成果に関しても即時に口頭で褒め感謝することで、無形の報酬を与えることが出来ます。このようにコミュニケーションを上手くとることで、職場の活性化を図りながら仕事を進めることが出来ます。
なお、動機付けなどに関しては、色々な手法や理論がWeb上などに溢れていますが、注意すべきは、仕事の形態や従業員の成長度合いによって、管理の形が変わると言うことです。基本はは人間を大事にしながら個々人の能力を引き出すと言うことですが、自分の職場の状況を見ながら適切な手法を採用すればよいのです。従業員の成熟度を見て、任せることができる範囲は任せ
るようにすることは一つの考え方です。
また、現在の社会は勤務の多様化なども考慮しないといけません。従来の単一的男社会では滅私奉公的に、長時間残業や休日出勤、会社の急な呼び出しなどに対応することで忠誠心を図っていました。しかし現在では、子育て中や介護中の社員等の多様な勤務者を、上手に活用することも大切です。会社に対して、長時間の関与で貢献する人もいるし、集中的に成果を出す人
もいます。このような個人の特性を生かすことも、管理の重要な仕事です。
3-1目標達成手段としての人員と設備の検討
定常的な負荷が見込める場合には、人員を採用し、設備を手配する必要がああります。但し、この場合でも、長期的な見通しを持って、人員や設備を計画する必要があります。
1)長期的に安定な負荷が望める場合
この場合には、設備をしっかり起業計画し保有し、人員は以下の考えで対応します。
1-1)技能習熟により改善が望める場合
比較的継続的な雇用を前提として、契約社員を採用するか正社員の増員を考えます。
1-2)単純作業で作業改善が望めない場合
パートタイマーで人員の採用を考え、指導者としての契約社員の割り当てが、有効であるかを考えます。
2)数年程度の負荷しか望めない場合
この場合には、設備はリースすることも考え、人員に関しては、仕事の指導する契約社員のレベルと、実行すするパートタイマーでの実現を考えます。
補足)正社員と契約社員の違いについて
契約社員は、特定の業務を行うことで、契約をします。従って、現在の仕事ができるかできないかで評価を行います。この時、正社員より給与や賞与が高い契約社員がいても当然です。
一方、正社員は会社に継続的に、利益をもたらすという、現在の可能性を超える潜在的なものまで含めて採用します。このため、給与には将来の期待と言うか、会社への拘束を含めた分が入っています。正社員は、能力を買っているので、仕事の配置転換なども、契約社員よりは可能性が多くなります。
4.長期的な仕事
4-1市場の見極め
課長の長期的な仕事は、まず自分達の存在価値を見極める仕事です。自部門が会社の経営にとって、どのような貢献をしているかしっかり理解します。そして貢献を増やすように方向を見定めます。例えば、市場を見出すなども一つの考えです。そのためMBA教材のポートフォリオ分析などの発想も有効です。この時、非成長分野や撤退分野に自分がいるという、あまり好ましくない結論に達するかもしれません。しかし、自分が会社に勤めているということを忘れずに、与えられた仕事をきちんと行うことも大切です。自部門のことだけ考えて、上司に要求するのではなく、戦略的に適当な資源でしっかり任務を行うことも重要です。撤退作戦は、一番難しいが、それを見事に行えば高い評価を受けることは、歴史が示しています。

図2にMBA教材で、よく出てくる『市場のポートフォリオ』を示しておきます。余談ですが、MBAの経験者の中には、目の奥に『田』の字が見えるというジョークがあります。このような見方は、全てではないですが、考え方を整理したり、説明したりするためにはある程度効果があります。手法を使いこなすことが大切です。
4-2組織論
管理職になってよいことの一つは、自分の部下達の組織構成を自分で決めることができることです。組織についても仕事の規模や部下たちの成熟度で、色々なパターンがあるります。一つの極端な例は、階層型組織であるオーケストラと、アメーバ型組織雅楽です。
(1)階層型(オーケストラ型)組織

階層型組織では、指導者と部下の権限と責任の関係が明確で、指導者の指示に部下が従います。意思決定の効率は良いが、実行に移すことができるかどうかが問題です。部下を縛るために、規則を決めて締めつけたり、マニュアル化したりして指導する必要があります。いわゆる欧米型の組織です。指揮者の役割が重要なオーケストラのイメージです。
なお、オーケストラの指揮者にも、大別すると2つのパターンがあります。一つは、個々人の楽器の演奏を完全に聴き分けて、事細かに指示する指揮者がいます。一方、曲のイメージを皆に伝えて、個人に任せる指揮者もいます。管理者の対応も、このように部下の成熟度に合わせて、切り替えていくべきです。
このような組織では、トップの業務を支える、スタッフ的な立場の人間が付くことも多いくあります。
このような体制では、管理層のオーバーヘッドが大きくなるが、部下のスキルは高くなくても、管理面の配慮で使える場合もあります。
(2)アメーバ型(雅楽型)組織

アメーバ型組織では、権限と責任が不明確で、場の空気に全員が従います。規則より暗黙の了解が優先する、いわゆる日本型組織です。他人のパートも能力的には受け持てる、雅楽の演奏イメージです。お互いの思いやりによる、運営の円滑化がこの組織の特徴であり、相互支援もスムーズに行われます。アメーバ組織では、全員が全体を見ているので、融通性も高く管理のオーバーヘッドも高くないが、個人の能力が必要です。従って能力のある人材を置く集めることで、ある意味贅沢な運営となります。また新人や素人が入り込みにくい運営になる欠点があります。
(3)理想の組織とは?
すべての状況に対して、理想的な組織は存在しません。しかし、理想的な組織の運営とは、以下のように言えます。
「構成員が常によくしようと継続的に改善を続ける組織運営」
これが実現するためには、各構成員の積極的な関与が必要です。さらに、自分たちの仕事を改善しても、収入減などの自分たちにとって不利にならない状況を納得していないと、抜本的な改善まで踏み込めません。このようなモラルを維持するように、各人を大切にすることも管理職の大事な仕事です。
なお、改善をする場合に各人が参画しても、方向が決まっていないと、バラバラになってしまいます。そのため、進むべき方向性をきちんと示し、状況により良否の判断をきちんと行うことは、トップの大切な仕事です。

理想の組織運営に関して図5 にアイデアをまとめてました。参考にしてください。
(4)軍隊組織
組織について学ぶとき、一つの極端な形として、近代軍隊組織を理解することは避けて通れません。
多くの組織論の話は、軍隊組織の応用や反発から生まれてくる。軍隊組織について、まとめたものを
軍隊組織の説明|鈴木良実 (note.com)
に公開しているので参考にして下さい。
4-3長期的な投資
経営的立場に立って一番重要で部下に任せられない仕事は、将来構想を立てそれに対する投資を行うことです。投資は、技術的な開発計画、それに対応した設備計画、そして人員の強化方針を、整合性を持って行う必要があります。
まず、市場動向などの変化を見据えて、組織の将来の姿を描き、その上で現在不足しているものを明確にします。それを補う開発計画や、設備投資の計画を立てます。また設備に関しては、老朽化の補充なども考えないといけません。そしてこれを生かす人材の育成計画も重要です。人材育成に関しては、新分野向けの人材の育成も重要ですが、世代交代を考えた育成も重要です。特に、管理職は自分の後継者を育てることも重要な仕事です。
なお、この人材育成は、一般的な生産性向上のためのスキル訓練とは異なり、各人の潜在的な可能性をしっかり見極めて、長期的な育成方針を立てることが大切です。
5.トラブル対応
管理職の仕事では、色々なトラブルがあります。これに対して逃げずに立ち向かうことが、大切です。但し、自分一人で抱え込まず、上司や部下に相談することも同様に大切です。以下に、管理職特有のトラブル事例を、2つ説明します。
5-1プレイングマネージャーのトラブル
現在の管理職の多くは、自分も実務を行う、プレイイングマネジャーとなることが、多くなっています。この場合のトラブルについて、少し考えて見ましょう。解りやすいトラブルは以下のものです。
(1)自分の担当業務の成果ばかりを追求し、組織としての成果が出ていない
これは、組織の成果を優先と言う原則を、きちんと心がけることで、直すことができます。
しかし次のトラブルは、もっと根が深く対処が難しいです。
(2)上司の仕事ぶりが下手な時、誰も直せない
これを具体的な例で示すと、野球解説などで有名な、野村克也監督時代の話があります。
「マウンド上の投手が、監督兼務の捕手のサインに首を振れるか?」
これは、彼が南海ホークスの野村克也監督兼捕手に対して、セーブ王の佐藤投手が直面した問題です。監督には、査定権や他球団への放出を決定する権限があります。そのような立場の相手に、真正面から異議を唱えることができるかという問題です。
原則として、プレイングマネージャーでも、実戦担当者としては、皆と同一戦線で戦っているのであり、間違いの指摘を謙虚に受け入れる体制が必要です。なお、野村克也監督は、監督時代には肩が衰えていて、盗塁を許すことが多くあり、投手に牽制球を多く投げさせ、投手のリズムを狂わせることもありました。このように、プレイングマネージャーのために、担当者
を狂わせることは困ったことです。
ただし、プレイングマネージャーでないといけないこともあります。当時の野村捕手の相手選手の癖を見抜き、狙い球を読む技量は群を抜いていました。それどころか、「相手選手の癖を見て、対応を考える」と言う発想すら、当時の他の選手にはなかったものです。このような、革新的なモノは、自分がやって見せないと人が追従できません。このような時は、他の欠点があってもプレイイングマネジャーとして現場に立つことも必要です。
このような評価を、客観的に行えることが、管理職としての力の一つです。
5-2成果主義のトラブル
現在の査定は、成果主義として運営することが多いですが、成果主義の運営に関しては、色々とトラブルが発生していまする。この対策としては、とにかく管理職自身が、自分で聞いて納得する説明を、作っておくことが大切です。自分自身が揺らいでいると、他人を説得することはできません。なお、誰が見ても納得する正しい評価などと言うものは、実際は存在しないので、最後は自分の主観的な評価です。
その時、
「自分はこのような前提で評価した。自分が評価するとき、優先する項目はXXである。」
と言い切ることができれば、少しは自信を持つことができます。どのような評価を行っても、不満を持つ人間はいます。その時自分として自信を持って、説明できればそれで良しとするぐらいの、割り切りも必要です。
ただし、この時他人の意見にも謙虚に耳を傾ける姿勢は大切です。決断するまでの参考意見は、多くあっても良いのです。しかし、最後の決断は自分または上司が行う、この原則を守ればよいのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

